Archive for the ‘いろいろ’ Category
失踪宣告で生命保険の請求
1失踪宣告で死亡と見なされる
①普通失踪は生死不明7年満了で死亡
行方不明になってから長期間経過している場合、死亡している可能性が高いことがあります。
失踪宣告は、死亡した可能性が高い行方不明者を法律上死亡した取り扱いにする手続です。
失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
普通失踪は、行方不明になってから7年経過後に失踪宣告の申立てをすることができます。
普通失踪は、生死不明7年満了で死亡と見なされます。
②危難が去ってから1年で特別(危難)失踪
行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。
大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。
特別失踪(危難失踪)とは、次の事情がある人が対象です。
(1)戦地に行った者
(2)沈没した船舶に乗っていた者
(3)その他死亡の原因となる災難に遭遇した者
死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。
特別(危難) 失踪では、失踪期間が1年です。
特別(危難) 失踪は、危難が去ってから1年経過後に失踪宣告の申立てをすることができます。
特別失踪(危難失踪)では、危難が去ったときに死亡と見なされます。
③失踪届で戸籍に反映
失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。
失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。
失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。
死亡したときに提出する死亡届とは別の書類です。
失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。
失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。
失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。
④行方不明のまま認定死亡で死亡届
人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。
海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。
遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。
海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。
死亡の報告書を添えて、市区町村役場に死亡届を提出することができます。
死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。
行政機関が市町村長に対して死亡の報告をしたら、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。
事実上、死亡の推定が認められます。
⑤単なる行方不明は生存扱い
行方不明の人は、法律上生きている人です。
長期間行方不明になっていても、法律上生きている人のままです。
生きているままだから、生命保険の死亡保険金は支払われません。
単なる行方不明の人は、生命保険の死亡保険金は支払われません。
2失踪宣告で生命保険の請求
①戸籍に反映したら生命保険の請求
失踪宣告の審判が確定した場合、市区町村役場に失踪届を提出します。
認定死亡の場合、市区町村役場に死亡届を提出します。
失踪届や死亡届が受理された場合、戸籍に記載されます。
死亡したことが確認できなくても、死亡と取り扱われます。
失踪宣告や死亡の記載がある戸籍謄本を提出して、生命保険を請求します。
生命保険の死亡保険金は、死亡によって給付されます。
失踪宣告や認定死亡は、死亡と同様の効果があります。
生命保険の死亡保険金は、失踪宣告や認定死亡であっても給付されます。
被保険者の死亡が戸籍に反映したら、生命保険を請求することができます。
②団体信用生命保険で住宅ローン完済
団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済に特化した生命保険です。
住宅ローンの債務者が死亡したとき、保険金で住宅ローンが完済になります。
民間の金融機関で住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているのがほとんどです。
住宅ローンの債務者が失踪宣告を受けた場合、保険金で住宅ローンが完済になります。
失踪宣告は、死亡と見なす制度だからです。
団体信用生命保険で住宅ローンは完済になります。
③契約が終了していると保険金が支払われない
生命保険の死亡保険金が給付されるのは、契約が継続している場合のみです。
被保険者が死亡と見なされる前に契約が終了している場合、死亡保険金は給付されません。
保険料の納入ができなくても、直ちに契約が終了するわけではありません。
契約内容によって異なるものの、1か月の猶予期間があります。
生命保険の多くは、解約した場合に解約返戻金が支払われるでしょう。
解約返戻金がある保険で猶予期間内に保険料が納入されなかった場合、保険商品によっては自動振替貸付がされます。
自動振替貸付とは、解約返戻金の範囲で保険料を立て替えて契約を維持する制度です。
普通失踪であれば、失踪期間は7年です。
特別(危難) 失踪であれば、失踪期間は1年です。
自動振替貸付を利用できても、デメリットが大きいでしょう。
保険契約を継続させるため、保険料を納入する必要があります。
④普通失踪は災害特約の対象外
普通失踪は、生死不明7年満了で死亡と見なされます。
生死不明の理由は、問われません。
生命保険商品によっては、災害特約がついていることがあります。
災害特約とは、災害で死亡した場合に保険金を増額してもらうことができる特約です。
普通失踪では、災害による死亡とは認められません。
普通失踪は、災害特約の対象外です。
⑤生きていたら保険金は返還
失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。
失踪宣告がされたけど、実は本人は新天地で元気に生きていたということがあります。
失踪宣告を受けた人が生きていた場合、失踪宣告は取り消されます。
失踪宣告は取り消された場合、受け取った生命保険金は返還しなければなりません。
返す財産は、現に利益を受けている限度においてのみとされています。
手許に現金が残っているのなら、受け取った現金をそのまま返すことができます。
不動産などを購入したのであれば、不動産に形を変えて利益を保有しています。
生活費などで使ったのであれば、その分の預貯金などが減らさずに済んでいるでしょう。
現に利益を受けている限度において、生命保険の保険金を返還しなければなりません。
3生命保険を解約できるのは契約者だけ
①行方不明者が契約していると家族は解約できない
普通失踪であれば、失踪期間は7年です。
特別(危難) 失踪であれば、失踪期間は1年です。
失踪期間経過後に、失踪宣告の申立てができます。
失踪期間経過後に失踪宣告の申立てをしても、失踪宣告がされるとは限りません。
裁判所の調査で、生存が確認されることがあるからです。
失踪宣告がされるまで、保険契約を維持する必要があります。
不確実な死亡保険金をあてにするより、解約返戻金を受け取りたいと考えるかもしれません。
生命保険契約を解約することができるのは、契約者のみです。
契約者以外の人が手続をする場合、契約者から委任状が必要です。
行方不明の人が契約者の場合、契約を解約することはできません。
契約者を差し置いて家族が勝手に解約することはできません。
②不在者財産管理人は解約できる
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を保存管理する人です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
生命保険契約は、行方不明の人の財産です。
生命保険の解約は、行方不明の人の財産の処分と言えます。
本来、不在者財産管理人は、財産の保存と管理しかできません。
行方不明の人の生命保険を解約するためには、家庭裁判所に権限外行為の許可が必要です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て保険契約を解約することができます。
4生命保険契約は調べることができる
①口座の引落記録等で判明
生命保険に入っているはずだが、保険証書がどうしても見つからないこともあるでしょう。
保険証書が見つからなくても、保険契約が無効になることはありません。
保険契約は、保険証書がなくても有効です。
契約の条件を満たせば、保険金は支払われます。
保険証書が見つからなくても、保険会社からの通知が見つかるでしょう。
銀行口座からの引落記録などで、保険会社が判明することも多いものです。
保険会社を探して、相談しましょう。
通常、保険証書には保険の種類や保険の番号が書いてあります。
保険金の支払請求をするとき、保険の種類や番号があると、比較的スムーズに手続できます。
保険の種類や番号が分からない場合、通常より手続に時間がかかります。
②生命保険契約照会制度
保険証書が見つからない場合、どこの保険会社に入っているのかすら分からないこともあるでしょう。
生命保険契約があるかどうか分からない場合、一般社団法人生命保険協会に対して、調査をしてもらうことができます。
調査は、インターネットや郵便で依頼することができます。
調査をしてもらう対象は、一般社団法人生命保険協会に加入している保険会社のみです。
本人が死亡した場合、調査を依頼することができる人は、次のとおりです。
(1)法定相続人
(2)遺言執行者
本人が死亡した場合に必要な書類は、次のとおりです。
(1)調査を依頼する人の本人確認書類
(2)本人と依頼する人の身分関係が分かる戸籍謄本
(3)死亡診断書
調査を依頼するためには、所定の手数料がかかります。
水害や大震災のような災害にあった場合、保険証書が流失したり、焼失することもあります。
自然災害による被害で保険証書を紛失しても、保険契約が無効になることはありません。
多くの方が保険証書を紛失する事態になるので、照会センターが設置されて、特別体制がとられます。
5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
行方不明の相続人や長期間行方不明で死亡の可能性の高い相続人がいる例は、少なくありません。
相続人が行方不明の場合、相続手続を進められなくなります。
相続手続を進めたいのに、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立てなどは、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になるでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続手続の期限一覧
1 【7日以内】死亡届
①死亡診断書(死体検案書)の受取
家族が死亡した後に、最初にすることは死亡診断書(死体検案書)の受取です。
死亡診断書(死体検案書)は、医師が作成します。
死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書です。
死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したときに作成されます。
死体検案書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したとき以外に作成されます。
死亡診断書と死体検案書の効力に、ちがいはありません。
②死亡届の提出
死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。
人が死亡したら、7日以内に死亡届の提出が義務付けられています。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、1枚の用紙に印刷されています。
左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。
死亡届の届出人は、次のとおりです。
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。
死亡診断書(死体検案書)の受取ったら、届出人が死亡届を記入します。
市区町村役場に持って行くのは、届出人以外の人でも差し支えありません。
③埋火葬許可申請
死亡届の提出と一緒に、埋火葬許可証の発行申請をします。
埋火葬許可証とは、死亡した人を埋火葬する許可を証明する書類です。
死亡してから24時間経過した後、火葬します。
埋火葬許可証がないと、火葬を執行することができません。
2【10日以内】年金の死亡届
厚生年金の受給権者が死亡した場合、10日以内に年金受給権者死亡届を提出します。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、年金受給権者死亡届を省略することができます。
マイナンバーが登録されているから死亡届の提出を省略する場合でも、未支給年金の請求は必要です。
3【14日以内】健康保険の資格喪失
①健康保険・介護保険の資格喪失
健康保険・介護保険の被保険者が死亡した場合、14日以内に資格喪失手続が必要です。
保険証は、資格喪失届をするときに一緒に返却します。
②年金の死亡届
国民年金の受給権者が死亡した場合、14日以内に年金受給権者死亡届を提出します。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、年金受給権者死亡届を省略することができます。
③世帯主変更届
被相続人が世帯主であった場合、原則として、14日以内に世帯主変更届が必要です。
世帯主が死亡したことで世帯に属する人が1人になった場合、世帯主変更届は不要です。
世帯主変更届は、同一世帯の人か新しく世帯主になる人が届出します。
別世帯の人が届出をする場合、委任状が必要になります。
4【3か月以内】相続放棄
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を引き継ぐものです。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を引き継がないものです。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄の申立ての期限は、3か月です。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続が発生した後、相続財産を利用・処分した場合、単純承認を見なされます。
単純承認をした後に家庭裁判所から相続放棄が認められても、相続放棄は無効です。
5【4か月以内】準確定申告
準確定申告とは、所得税の申告のひとつです。
所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年3月15日までに申告と納税をします。
この申告を、確定申告と言います。
1年の途中で死亡した場合、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告と納税をします。
通常の確定申告と死亡した人の申告を区別するため、準確定申告と言います。
準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。
申告と納税をするのは、相続が発生したことを知ってから4か月以内です。
家庭裁判所から相続放棄が認められた場合、準確定申告をする義務はありません。
はじめから相続人でなくなるからです。
それでも税務署から準確定申告をするように通知が来る場合があります。
税務署から通知が来た場合、あわてて準確定申告をする必要はありません。
準確定申告をした場合、相続放棄が無効になります。
準確定申告は、相続人がするものだからです。
自分は相続人であると認めたから、準確定申告をしたと判断されることになります。
6【10か月以内】相続税申告
相続税は、相続した財産の額に応じて課される税金です。
相続税が課される場合、10か月以内に申告納税をします。
相続税申告が必要になるのは、10%未満のわずかな人です。
相続税には、基礎控除があるからです。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
相続財産が基礎控除以下である場合、相続税申告は不要です。
7【1年以内】遺留分侵害額請求
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に、認められます。
被相続人は自分の死後、財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっているとはいえ、無制約の自由を認めることはできません。
財産は家族の協力があってこそ、築くことができたはずだからです。
遺留分に満たない財産の分配しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権を長期間行使しない場合、権利が消滅します。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
8【2年以内】給付金の請求
①高額療養費の請求
高額療養費とは、健康保険の被保険者が高額な医療費を負担したときに支給される給付金です。
自己負担限度額を超えた場合、超えた分が給付されます。
高額療養費を受け取るためには、2年以内に申請が必要です。
高額な医療を受ける場合、事前に予定されていることが多いでしょう。
医療を受ける前に、限度額適用認定証を取得しておくと便利です。
限度額認定証を病院の窓口に提示した場合、病院は自己負担限度額だけ請求します。
病院への支払いが少なくなるうえに、原則として、高額療養費支給申請が不要になります。
②埋葬料・葬祭費の請求
埋葬料・葬祭費とは、健康保険の被保険者が死亡したときに支給される給付金です。
埋葬を行った人に給付されます。
埋葬料・葬祭費を受け取るためには、2年以内に申請が必要です。
③死亡一時金の請求
死亡一時金とは、国民年金保険料を3年以上納めた人が死亡したときに遺族に給付される給付金です。
年金ではなく、文字どおり一回だけ支給されます。
死亡一時金を受け取るためには、2年以内に申請が必要です。
9【3年以内】相続登記と生命保険の請求
①相続登記
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記を怠ると、ペナルティーが課されます。
相続登記が義務化されるのは、2024年4月からです。
2024年4月以前に発生した相続と2024年4月以降に発生した相続の両方が対象です。
②生命保険の死亡保険金
被相続人が生命保険をかけていた場合、受取人は死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金を長期間請求しない場合、権利が消滅します。
生命保険の死亡保険金の請求権は、3年で時効消滅します。
被保険者が生命保険をかけていたか分からない場合、生命保険協会に照会することができます。
10【5年以内】未支給年金の請求
年金は、死亡の月まで支給されます。
例えば、5月10日に死亡した場合、5月分の年金まで支給されます。
年金は、前2か月分まとめて偶数月15日に支給されます。
例えば、2月分と3月分の年金は、4月15日に支給されます。
金融機関は口座の持ち主が死亡したことを知った場合、口座を凍結します。
口座の凍結とは、口座の取引をできなくすることです。
口座が凍結されたら、年金が振り込まれても受け取ることはできません。
5月分までの年金を受け取れるはずなのに、受け取れなくなります。
これが未支給年金です。
未支給年金は、一定の範囲の家族が受け取ることができます。
未支給年金は、5年以内に請求する必要があります。
一定の範囲の家族は、法律で決められています。
未支給年金を請求することができる人は、相続人とは別の扱いです。
相続放棄をして相続人でなくなった人であっても、未支給年金を請求することができます。
未支給年金は、相続財産ではないからです。
11【5年10か月以内】相続税の更正請求
相続税申告をした後に、申告内容に誤りがあったことに気づくことがあります。
相続税申告のやり直しをして、納め過ぎの税金を返してもらうことができます。
相続税申告のやり直しを更正請求と言います。
更正請求の期限は、相続税の申告期限から5年以内です。
相続税の申告期限は10か月以内だから、更正請求の期限は5年10か月以内です。
12期限はないけど早めに着手した方がいいこと
①相続人調査
相続人になる人は、法律で決まっています。
家族にとって、だれが相続人になるかは当然知っていることでしょう。
家族以外の第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。
相続人であることを客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意することです。
相続人調査自体に期限はありません。
相続人調査は、期限がある手続の前提として必要になります。
相続人調査は、早めに着手することがおすすめです。
②相続財産調査
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産の両方があります。
被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、連帯保証人の義務も相続します。
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
どのような財産が相続財産であるのか分からないと、相続人は判断できないでしょう。
相続財産調査自体に期限はありません。
相続財産調査は、期限がある手続の前提として必要になります。
相続財産調査は、早めに着手することがおすすめです。
③遺産分割協議
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に、相続手続をすることはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があるからです。
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができたら、文書に取りまとめます。
相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の作成自体に期限はありません。
遺産分割協議書の作成を先延ばしすると、合意があいまいになります。
早めに遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
13相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。
相続手続するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。
負担の大きい相続手続を司法書士などの専門家に依頼すれば、遺族の疲れも軽減されるでしょう。
被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。
悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。
調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍等の提出が求められます。
戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。
相続手続でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
再配達削減のための取組
オリーブの木司法書士事務所では、再配達削減の取組に協力しています。
働き方改革を推進し、働きやすい環境づくりを進めます。
オリーブの木司法書士事務所がお約束することは、次のとおりです
○ 時間帯指定の活用します
○ 各事業者の提供しているコミュニケーション・ツール等(メール・アプリ等)の活用します
○ コンビニ受取や駅の宅配ロッカー、置き配など、多様な受取方法の活用します
○ 発送時に送付先の在宅時間を確認します
再配達削減のために送る立場、受け取る立場で協力します。


相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
口約束の相続でトラブル
1口約束で遺言はできない
①自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんど
遺言書の種類は、民法という法律で決められています。
大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言は、次の3つです。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
特別方式の遺言は、次の4つです。
(1)死亡の危急に迫った者の遺言
(2)伝染病隔離者の遺言
(3)在船者の遺言
(4)船舶遭難者の遺言
特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。
ごく稀な遺言と言えるでしょう。
多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。
なかでも(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。
②自筆証書遺言は自分で書いて作成
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。
筆記用具や紙に、制約はありません。
封筒に入れなければならないといった決まりもありません。
自筆証書遺言は、文字どおり自分で書いて作った遺言書です。
遺言者本人が自分で書くことが、条件です。
被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。
被相続人が言い遺した約束だから、財産を譲ってもらえると期待するかもしれません。
口頭で言い遺した約束は、自筆証書遺言ではありません。
口約束で自筆証書遺言をすることは、できません。
③公正証書遺言は公証人が関与
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
原則として、公証役場に出向く必要があります。
公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。
公証人が関与せずに、公正証書遺言を作ることはできません。
被相続人が生前に自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、公証人は関与していないでしょう。
単なる口約束は、公正証書遺言ではありません。
口約束で公正証書遺言をすることは、できません。
④一般危急時遺言の条件は厳しい
特別方式の遺言に、一般危急時遺言があります。
死亡の危急に迫った者がする特別な遺言です。
死亡の危急に迫った人は、自分で遺言書を書くことが困難です。
遺言者から遺言の内容を聞いて、証人が遺言書を作成します。
一般危急時遺言では、証人3人に確認してもらいます。
証人のひとりが遺言内容を書面に取りまとめ、証人全員が署名押印します。
一般危急時遺言を作成した後20日以内に、家庭裁判所に確認の審判の申立てをします。
20日以内に家庭裁判所への審判の申立てがされなければ、一般危急時遺言は無効になります。
一般危急時遺言は、死亡の危急に迫った者がする特別な遺言です。
遺言を作成した後、死亡の危急から脱することがあります。
死亡の危急から脱した場合、普通方式の遺言ができるはずです。
わざわざ一般危急時遺言を維持するメリットがなくなります。
普通方式の遺言ができるようになってから6か月経過で、一般危急時遺言は無効になります。
単なる口約束は、一般危急時遺言ではありません。
2口約束で遺贈はできない
①遺贈は遺言書で財産を譲ること
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。
譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
②遺贈には遺言書が必要
遺贈は、遺言書で財産を譲ってあげることです。
遺贈をするためには、遺言書が必要です。
遺言書の形式は、問いません。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺贈をすることができます。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。
口約束で自筆証書遺言をすることは、できません。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
口約束で公正証書遺言をすることは、できません。
死亡の危急に迫った者の場合、一般危急時遺言ができます。
一般危急時遺言を作成した後20日以内に、家庭裁判所に確認の審判の申立てが必要です。
単なる口約束は、一般危急時遺言ではありません。
単なる口約束で、遺贈をすることはできません。
③遺言書作成は公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。
公正証書遺言は、法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。
遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。
作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
紛失するおそれがありません。
遺言書が作られていることが分かっていれば、容易に探してもらえます。
公正証書遺言は、安心確実です。
自筆証書遺言は、ひとりで作ることができます。
作るだけであれば、費用はかかりません。
専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。
世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。
専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。
せっかく遺言書を作成しても、無効になったら意味はありません。
相続人がトラブルにならないようにと考えるのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
3口約束で死因贈与
①死因贈与は契約
贈与は、契約です。
死因贈与契約は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。
財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、契約は成立します。
被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。
口約束で、遺言をすることはできません。
口約束で、遺贈をすることはできません。
口約束で、贈与をすることができます。
口約束で、死因贈与をすることができます。
贈与契約は、書面を作成しなくても有効だからです。
②口約束の贈与は信用されない
財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、契約は成立します。
口約束だけの贈与契約は、証拠がないでしょう。
財産を譲ると約束してもらったと主張しても、信用してもらえません。
死因贈与は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。
贈与がなければ、相続人が相続する財産だったはずです。
相続人から見ると、相続財産を奪われる気持ちになるでしょう。
被相続人が複数の人に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。
周りの人の気を引きたい気持ちがあったのでしょう。
口約束だけの贈与契約は、証拠はありません。
複数の人が約束したと主張する場合、ウソを言っている人がいるかもしれません。
たとえ本当に約束していたとしても、口約束の死因贈与契約は信用されません。
③死因贈与の実現には相続人全員の協力が必要
財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、贈与契約は成立します。
財産を譲り渡す人に相続が発生した場合、財産を譲り渡す義務は相続人全員に相続されます。
死因贈与が有効に成立していたとしても、贈与の実現には相続人全員の協力が必要です。
一部の相続人が死因贈与に疑いを持つ場合、死因贈与の実現に協力は得られないでしょう。
相続財産を奪われる気持ちになっている相続人は、死因贈与の実現に協力しないでしょう。
死因贈与が有効に成立していたとしても、一方的に財産を奪うことはできません。
死因贈与の実現には、相続人全員の協力が必要です。
④死因贈与は仮登記ができる
自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、譲る財産が不動産であることがあります。
死因贈与契約は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。
詳しく言うと、贈与する人の死亡を始期とする贈与契約です。
仮登記とは、将来の登記の順位を保全する登記です。
通常の登記は、仮登記と比較して本登記と言います。
不動産の権利変動はまだ発生していないけど権利変動を発生させる請求権が発生しているとき、仮登記を申請することができます。
贈与する人が死亡するまで、財産は贈与を受ける人のものになりません。
不動産の権利変動は、まだ発生していません。
所有権を移転させる請求権は、すでに発生しています。
死因贈与契約をした場合、仮登記をすることができます。
死因贈与の仮登記をするには、譲り渡す人の協力が必要です。
⑤死因贈与契約は公正証書にできる
死因贈与契約は、財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば成立します。
口約束で、死因贈与をすることができます。
口約束で死因贈与契約をした場合、他の人に信用してもらうことは難しいでしょう。
財産を譲り渡す人が死亡した後に、相続人とトラブルになるおそれがあります。
自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、相続人とトラブルになることは望んでいないでしょう。
トラブルを防止するため、死因贈与契約を書面に取りまとめるといいでしょう。
死因贈与契約は、公正証書にすることができます。
公正証書は公証人が関与して作成するから、安心確実です。
公正証書は、公証役場で厳重に保管されます。
契約書の紛失や改ざんの心配がありません。
公正証書で死因贈与契約をする場合、公正証書に仮登記の同意を盛り込むことができます。
仮登記の同意がある公正証書を提出する場合、譲り受ける人は仮登記を単独で申請することができます。
公正証書で死因贈与契約をする場合、死因贈与の執行者を指名することができます。
執行者は、死因贈与を実現する人です。
執行者がいる場合、相続人の協力は不要です。
死因贈与の執行者と財産を譲り受ける人が協力して、仮登記の本登記をすることができます。
死因贈与契約を公正証書にする場合、費用がかかります。
かかる費用に見合うだけの大きなメリットがあります。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないから、トラブルになる例はたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
SDGs宣言
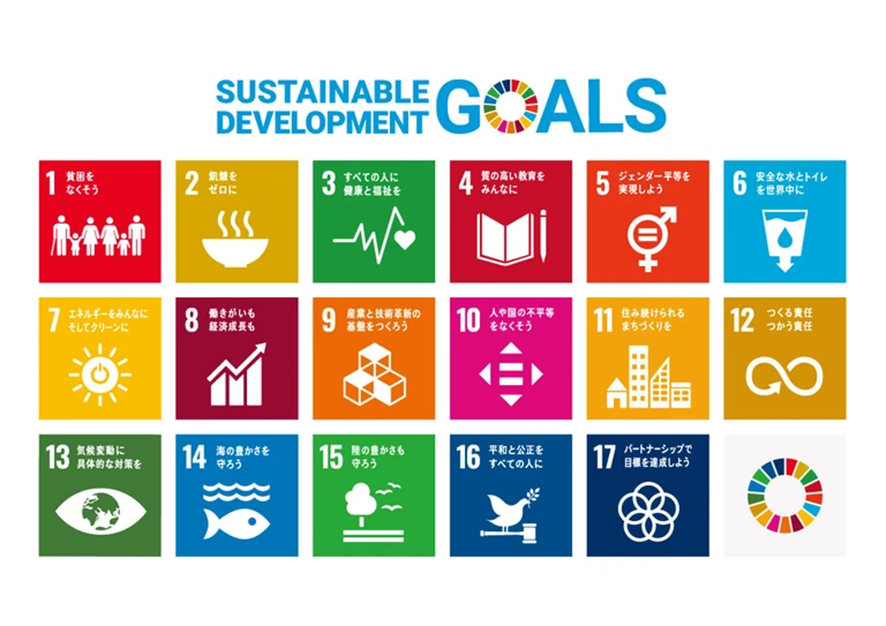
1すべての人が安心して暮らせる仕組みづくり
オリーブの木司法書士事務所では、SDGs宣言をしました。
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保できるように努めます。
2ワークライフバランスの推進
働きやすい環境づくりを進めるため、ワーク・ライフ・バランスを推進する取組をします。
SDGsの取り組みを目にしつつも、行動に移せないことがあります。
SDGsの目標を達成すべく、働きやすい環境づくりを推進します。
3地球市民として活動を推進
すべての人が安心して暮らすため、地球環境は無視できません。
オリーブの木司法書士事務所では、ペーパーレス化を進めています。
事務所の省エネルギー化を積極的に推進します。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
Myじんけん宣言
・ 人権尊重の方針に基づき、事務所内整備を行います。
・ 働きがいのある人間らしい仕事の実現に取り組みます。
・ ハラスメント防止のため、対策を実践します。
・ 共同企業とともに人権デュー・ディリジェンスを実施します。
・ ユニバーサルデザインを推進します。
・ 障害者雇用を促進します。
・ 女性活躍を推進します。
・ 性的志向・性自認への理解・受容を促進します。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
消費者志向自主宣言
オリーブの木司法書士事務所では、消費者庁の目指す消費者経営を推進しています。
消費者全体の視点に立ち、持続可能な社会の実現を目指すものです。
オリーブの木司法書士事務所は、消費者志向自主宣言をしました。
消費者の視点から、SDGsの推進し消費者経営の趣旨に賛同しています。
SDGsの推進、消費者経営の促進のため、関係団体や消費者と連携に努めます。
1経営理念
・オリーブの木司法書士事務所のサービスを通じてお客さま満足のみならず、地域社会や次世代のために取組を推進し、持続可能な社会への貢献を目指します。
・お客さまの期待に答え、新たな価値を創造し提案をします。
・お客様のお話に耳を傾け、謙虚に誠実に対応します。
2取組方針
①お客さま満足度の向上
私たちは、常にプロ意識を持ち、丁寧、迅速な仕事を行います。
お客さまとのコミュニケ-ションを深化させ、お客さまからの信頼を獲得します。
私たちはお客さま満足度向上に繋がる対応を心掛けます。
お客さまの声を謙虚に受け止め、サービスの品質向上に反映させます。
司法書士業務を通して、地域社会の課題解決の一翼を担います。
②未来・次世代のために取り組むこと
「SDGs の取組方針」を明確化し、社内外に発信しています。
登記実務を通じて、安心な社会社会への貢献を目指します。
③コンプライアンスの強化をすること
消費者関連法規の遵守を徹底します。
情報収集した消費者相談内容等を集約し、コンプライアンスを徹底します。
④消費者・社会の要望を踏まえた改善・開発
お客さまに寄り添うサービス開発を行い、豊かで安心できる暮らしづくりに努めます。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。





