Archive for the ‘いろいろ’ Category
公証役場の住所電話番号一覧
| 都道府県 | 公証役場 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX |
| 北海道 | 札幌大通 | 060-0001 | 札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 | 011-241-4267 | 011-241-4269 |
| 北海道 | 札幌中 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 | 011-271-4977 | 011-281-0278 |
| 北海道 | 小樽 | 047-0031 | 小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 | 0134-22-4530 | 0134-22-4530 |
| 北海道 | 岩見沢 | 068-0024 | 岩見沢市4条西1-2-5 MY岩見沢ビル2階 | 0126-22-1752 | 0126-22-1752 |
| 北海道 | 室蘭 | 050-0074 | 室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階 | 0143-44-8630 | 0143-44-8655 |
| 北海道 | 苫小牧 | 053-0022 | 苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 | 0144-36-7769 | 0144-36-7779 |
| 北海道 | 滝川 | 073-0022 | 滝川市大町1-8-1 滝川産経会館3階 | 0125-24-1218 | 0125-24-1218 |
| 北海道 | 函館合同 | 040-0063 | 函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 | 0138-22-5661 | 0138-22-5662 |
| 北海道 | 旭川合同 | 070-0036 | 旭川市6条通8-37-22 68ビル 5階 | 0166-23-0098 | 0166-22-5553 |
| 北海道 | 名寄 | 096-0011 | 名寄市西1条南9-35 | 01654-3-3131 | 01654-3-3131 |
| 北海道 | 釧路合同 | 085-0016 | 釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル4階 | 0154-25-1365 | 0154-68-5163 |
| 北海道 | 帯広合同 | 080-0016 | 帯広市西6条南6-3 ソネビル3階 | 0155-22-6789 | 0155-22-6789 |
| 北海道 | 北見 | 090-8509 | 北見市大通西2-1 まちきた大通ビル5階 | 0157-31-2511 | 0157-31-2518 |
| 青森県 | 青森合同 | 030-0861 | 青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階 | 017-776-8273 | 017-776-8273 |
| 青森県 | 弘前 | 036-8002 | 弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階 | 0172-34-3084 | 0172-88-8788 |
| 青森県 | 八戸 | 031-0041 | 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201 | 0178-43-1213 | 0178-43-1213 |
| 岩手県 | 盛岡合同 | 020-0022 | 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階 | 019-651-5828 | 019-651-6551 |
| 岩手県 | 宮古 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階 | 0193-63-4431 | 0193-63-4431 |
| 岩手県 | 一関 | 021-0885 | 一関市田村町2-25 | 0191-21-2986 | 0191-21-2986 |
| 岩手県 | 花巻 | 025-0075 | 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階 | 0198-23-2002 | 0198-23-2002 |
| 宮城県 | 仙台合同 | 980-0802 | 仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 | 022-266-8398 | 022-268-0011 |
| 宮城県 | 仙台一番町 | 980-0811 | 仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階 | 022-224-6148 | 022-224-6149 |
| 宮城県 | 仙台本町 | 980-0014 | 仙台市青葉区本町二丁目10番33号(第2日本オフィスビル3階) | 022-261-0744 | 022-261-0773 |
| 宮城県 | 石巻 | 986-0826 | 石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階 | 0225-22-5791 | 0225-90-3876 |
| 宮城県 | 古川 | 989-6162 | 大崎市古川駅前大通2-6-16 古川土地ビル3階 | 0229-22-2332 | 0229-25-6626 |
| 宮城県 | 大河原 | 989-1245 | 柴田郡大河原町字新南35-3 | 0224-53-2265 | 0224-86-3931 |
| 秋田県 | 秋田合同 | 010-0921 | 秋田市大町3-5-8 ウィング・グラン3階 | 018-864-0850 | 018-864-0854 |
| 秋田県 | 能代 | 016-0845 | 能代市通町9-48 大丸ビル2階 | 0185-52-7728 | 0185-88-8070 |
| 山形県 | 山形 | 990-0038 | 山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階 | 023-625-1693 | 023-633-0938 |
| 山形県 | 鶴岡 | 997-0044 | 鶴岡市新海町17-68 鶴岡法務総合ビル2階 | 0235-22-9996 | 0235-22-9348 |
| 山形県 | 米沢 | 992-0012 | 米沢市金池2-6-23 舟山ハイツ1階 | 0238-22-6886 | 0238-27-9920 |
| 福島県 | 福島 | 960-8035 | 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階 | 024-521-2557 | 024-521-2558 |
| 福島県 | 郡山 | 963-8017 | 郡山市長者1-7-20 東京海上日動ビル2階 | 024-932-6037 | 024-922-5888 |
| 福島県 | 白河 | 961-0856 | 白河市新白河1-38 グラン玉屋A101 | 0248-23-2203 | 0248-23-2228 |
| 福島県 | 会津若松 | 965-0022 | 会津若松市滝沢町5-40 市原ビル1階 | 0242-37-1955 | 0242-37-1956 |
| 福島県 | いわき | 970-8026 | いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター4階 | 0246-23-4066 | 0246-38-6463 |
| 福島県 | 相馬 | 976-0042 | 相馬市中村字北町63番地3 相馬市役所1階 | 0244-36-1008 | 0244-26-5331 |
| 茨城県 | 水戸合同 | 310-0801 | 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階 | 029-231-5328 | 029-221-8758 |
| 茨城県 | 土浦 | 300-0813 | 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階 | 029-821-6754 | 029-826-9368 |
| 茨城県 | 日立 | 317-0073 | 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階 | 0294-21-5791 | 0294-23-4430 |
| 茨城県 | 取手 | 302-0004 | 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階 | 0297-74-2569 | 0297-74-2569 |
| 茨城県 | 下館 | 308-0031 | 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内 | 0296-24-9460 | 0296-24-9460 |
| 茨城県 | 鹿嶋 | 314-0031 | 鹿嶋市宮中8-12-6 | 0299-83-4822 | 0299-83-4822 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 320-0811 | 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階 | 028-624-1100 | 028-624-7600 |
| 栃木県 | 足利 | 326-0814 | 足利市通3-2589 足利織物会館3階 | 0284-21-6822 | 0284-21-6822 |
| 栃木県 | 小山 | 323-0807 | 小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階 | 0285-24-4599 | 0285-24-4599 |
| 栃木県 | 大田原 | 324-0041 | 大田原市本町1-2714 | 0287-23-0666 | 0287-23-5208 |
| 群馬県 | 前橋合同 | 371-0023 | 前橋市本町1-3-6 | 027-223-8277 | 027-223-8150 |
| 群馬県 | 太田 | 373-0851 | 太田市飯田町1245-1 金十清水ビル1階 | 0276-45-8469 | 0276-45-8469 |
| 群馬県 | 高崎合同 | 370-0849 | 高崎市八島町20-1 武蔵屋ビル4階 | 027-325-1574 | 027-324-5767 |
| 群馬県 | 桐生 | 376-0011 | 桐生市相生町2-376-13 | 0277-54-2168 | 0277-54-2168 |
| 群馬県 | 伊勢崎 | 372-0014 | 伊勢崎市昭和町3919 伊勢崎商工会議所会館3階 | 0270-24-3252 | 0270-24-7113 |
| 群馬県 | 富岡 | 370-2316 | 富岡市富岡1477-1 富岡市水道会館1階 | 0274-64-1075 | 0274-64-8341 |
| 埼玉県 | 浦和 | 330-0063 | さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 | 048-831-1951 | 048-831-6808 |
| 埼玉県 | 川口 | 332-0012 | 川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 | 048-223-0911 | 048-223-0912 |
| 埼玉県 | 春日部 | 344-0067 | 春日部市中央1-51-1 春日部大栄ビル3階 | 048-792-0811 | 048-792-0812 |
| 埼玉県 | 川越 | 350-0043 | 川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 | 049-224-9454 | 049-225-6014 |
| 埼玉県 | 熊谷 | 360-0037 | 熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 | 048-524-9733 | 048-526-0825 |
| 埼玉県 | 越谷 | 343-0808 | 越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 | 048-962-2796 | 048-962-5869 |
| 埼玉県 | 秩父 | 368-0033 | 秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 | 0494-23-3788 | 0494-26-7017 |
| 埼玉県 | 東松山 | 355-0028 | 東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 | 0493-23-4413 | 0493-25-0623 |
| 埼玉県 | 大宮 | 330-8669 | さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階 | 048-642-4355 | 048-642-3101 |
| 埼玉県 | 所沢 | 359-0035 | 所沢市西新井町20-10 | 04-2994-2323 | 04-2992-8913 |
| 千葉県 | 千葉 | 260-0015 | 千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 | 043-222-2876 | 043-222-0503 |
| 千葉県 | 船橋 | 273-0011 | 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 | 047-437-0058 | 047-437-0394 |
| 千葉県 | 市川合同 | 272-0021 | 市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 | 047-321-0665 | 047-321-0670 |
| 千葉県 | 木更津 | 292-0057 | 木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 | 0438-22-2243 | 0438-22-2203 |
| 千葉県 | 銚子 | 288-0044 | 銚子市西芝町3-9 大樹ビル2階 | 0479-23-6071 | 0479-23-6061 |
| 千葉県 | 松戸 | 271-0091 | 松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 | 047-363-2091 | 047-369-2109 |
| 千葉県 | 柏 | 277-0011 | 柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 | 04-7166-6262 | 04-7166-6373 |
| 千葉県 | 成田 | 286-0033 | 成田市花崎町956 | 0476-22-1035 | 0476-22-1073 |
| 千葉県 | 館山 | 294-0047 | 館山市八幡32-2 | 0470-22-5528 | 0470-22-5529 |
| 千葉県 | 茂原 | 297-0026 | 茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 | 0475-22-5959 | 0475-22-5959 |
| 東京都 | 霞ヶ関 | 100-0011 | 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 | 03-3502-0745 | 03-3502-3840 |
| 東京都 | 日本橋 | 103-0026 | 中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 | 03-3666-3089 | 03-6661-7611 |
| 東京都 | 渋谷 | 150-0041 | 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 | 03-3464-1717 | 03-3464-2799 |
| 東京都 | 神田 | 101-0044 | 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 | 03-3256-4758 | 03-3256-1200 |
| 東京都 | 池袋 | 170-6008 | 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 | 03-3971-6411 | 03-3984-2740 |
| 東京都 | 大森 | 143-0016 | 大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 | 03-3763-2763 | 03-3763-4500 |
| 東京都 | 新宿 | 160-0023 | 新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 | 03-3365-1786 | 03-3365-3835 |
| 東京都 | 文京 | 112-0003 | 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 | 03-3812-0438 | 03-3812-0413 |
| 東京都 | 上野 | 110-0015 | 台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 | 03-3831-3022 | 03-3831-3025 |
| 東京都 | 浅草 | 111-0034 | 台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 | 03-3844-0906 | 03-3845-2523 |
| 東京都 | 丸の内 | 100-0005 | 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 | 03-3211-2645 | 03-3211-2647 |
| 東京都 | 京橋 | 104-0031 | 中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 | 03-3271-4677 | 03-3271-3606 |
| 東京都 | 銀座 | 104-0061 | 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 | 03-3561-1051 | 03-3561-1053 |
| 東京都 | 新橋 | 105-0004 | 港区新橋1-18-1 航空会館6階 | 03-3591-4845 | 03-3591-5590 |
| 東京都 | 芝 | 105-0003 | 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 | 03-3434-7986 | 03-3434-7987 |
| 東京都 | 麻布 | 106-0045 | 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 | 03-3585-0907 | 03-3585-0908 |
| 東京都 | 目黒 | 141-0021 | 品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 | 03-3494-8040 | 03-3494-8041 |
| 東京都 | 五反田 | 141-0022 | 品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 | 03-3445-0021 | 03-3445-1136 |
| 東京都 | 世田谷 | 154-0024 | 世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 | 03-3422-6631 | 03-3487-5925 |
| 東京都 | 蒲田 | 144-0051 | 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 | 03-3738-3329 | 03-3730-5052 |
| 東京都 | 王子 | 114-0002 | 北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 | 03-3911-6596 | 03-3911-6594 |
| 東京都 | 赤羽 | 115-0044 | 北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 | 03-3902-2339 | 03-3902-2420 |
| 東京都 | 小岩 | 133-0057 | 江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 | 03-3659-3446 | 03-3671-0486 |
| 東京都 | 葛飾 | 125-0062 | 葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階 | 03-6662-9631 | 03-6662-9632 |
| 東京都 | 錦糸町 | 130-0022 | 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 | 03-3631-8490 | 03-3635-1540 |
| 東京都 | 向島 | 131-0032 | 墨田区東向島2-29-12 102号室 | 03-3612-5624 | 03-3612-2890 |
| 東京都 | 千住 | 120-0026 | 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 | 03-3882-1177 | 03-3882-1178 |
| 東京都 | 練馬 | 176-0012 | 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 | 03-3991-4871 | 03-3993-3428 |
| 東京都 | 中野 | 164-0001 | 中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 | 03-5318-2255 | 03-5318-2266 |
| 東京都 | 杉並 | 167-0032 | 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 | 03-3391-7100 | 03-3391-7103 |
| 東京都 | 板橋 | 173-0004 | 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 | 03-3961-1166 | 03-3962-2810 |
| 東京都 | 麹町 | 102-0083 | 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 | 03-3265-6958 | 03-3265-6959 |
| 東京都 | 浜松町 | 105-0012 | 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 | 03-3433-1901 | 03-3435-0075 |
| 東京都 | 八重洲 | 103-0028 | 中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 | 03-3271-1833 | 03-3275-3595 |
| 東京都 | 大塚 | 170-0005 | 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 | 03-6913-6208 | 03-6913-6237 |
| 東京都 | 赤坂 | 107-0052 | 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階 | 03-3583-3290 | 03-3584-4987 |
| 東京都 | 高田馬場 | 169-0075 | 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 | 03-5332-3309 | 03-3362-3370 |
| 東京都 | 昭和通り | 104-0061 | 中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 | 03-3545-9045 | 03-3545-9080 |
| 東京都 | 新宿御苑前 | 160-0022 | 新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 | 03-3226-6690 | 03-3226-6692 |
| 東京都 | 武蔵野 | 180-0004 | 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 | 0422-22-6606 | 0422-22-7210 |
| 東京都 | 立川 | 190-0023 | 立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階 | 042-524-1279 | 042-522-2402 |
| 東京都 | 八王子 | 192-0082 | 八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 | 042-631-4246 | 042-631-4247 |
| 東京都 | 町田 | 194-0021 | 町田市中町1-5-3 | 042-722-4695 | 042-722-5693 |
| 東京都 | 府中 | 183-0023 | 府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 | 042-369-6951 | 042-362-9075 |
| 東京都 | 多摩 | 206-0033 | 多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 | 042-338-8605 | 042-338-8659 |
| 神奈川県 | 博物館前本町 | 231-0005 | 横浜市中区本町6丁目52番地 本町アンバービル 5階 | 045-212-2033 | 045-212-3613 |
| 神奈川県 | 横浜駅西口 | 220-0004 | 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 | 045-311-6907 | 045-311-0660 |
| 神奈川県 | 関内大通り | 231-0047 | 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 | 045-261-2623 | 045-243-2532 |
| 神奈川県 | 尾上町 | 231-0015 | 横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.(リストイーストビル)8階 | 045-212-3609 | 045-212-5560 |
| 神奈川県 | みなとみらい | 231-0011 | 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 | 045-662-6585 | 045-662-7898 |
| 神奈川県 | 鶴見 | 230-0051 | 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202 | 045-521-3410 | 045-521-3435 |
| 神奈川県 | 上大岡 | 233-0002 | 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2 | 045-844-1102 | 045-352-7102 |
| 神奈川県 | 川崎 | 210-0007 | 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 | 044-222-7264 | 044-222-5894 |
| 神奈川県 | 溝ノ口 | 213-0001 | 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 | 044-811-0111 | 044-812-4232 |
| 神奈川県 | 藤沢 | 251-0025 | 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 | 0466-22-5910 | 0466-22-5958 |
| 神奈川県 | 横須賀 | 238-0006 | 横須賀市日の出町一丁目7番地16 よこすか法務ビル202 | 046-823-0328 | 046-827-8328 |
| 神奈川県 | 小田原 | 250-0011 | 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 | 0465-22-5772 | 0465-23-3992 |
| 神奈川県 | 平塚 | 254-0807 | 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 | 0463-21-0267 | 0463-22-7726 |
| 神奈川県 | 厚木 | 243-0018 | 厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 | 046-221-1813 | 046-221-1819 |
| 神奈川県 | 相模原 | 252-0231 | 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階) | 042-758-1888 | 042-758-2228 |
| 新潟県 | 新潟合同 | 950-0917 | 新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階) | 025-240-2610 | 025-243-2439 |
| 新潟県 | 長岡合同 | 940-0053 | 長岡市長町1丁目甲1672-1 | 0258-86-6925 | 0258-33-5438 |
| 新潟県 | 上越 | 943-0834 | 上越市西城町2-10-25 大島ビル1階 | 025-522-4104 | 025-522-4104 |
| 新潟県 | 三条 | 955-0047 | 三条市東三条1-5-1 川商ビル4階 | 0256-32-3026 | 0256-32-3054 |
| 新潟県 | 新発田 | 957-0054 | 新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階 | 0254-24-3101 | 0254-24-3124 |
| 富山県 | 富山合同 | 930-0094 | 富山市安住町2-14 北日本スクエア北館8階 | 076-442-2700 | 076-442-2713 |
| 富山県 | 高岡 | 933-0872 | 高岡市芳野185 グランディ芳野 1階 | 0766-25-5130 | 0766-30-8058 |
| 富山県 | 魚津 | 937-0051 | 魚津市駅前新町5-30 サンプラザ2階 | 0765-24-6747 | 0765-33-5587 |
| 石川県 | 金沢合同 | 920-0855 | 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階 | 076-263-4355 | 076-231-7030 |
| 石川県 | 小松 | 923-0868 | 小松市日の出町1-126 ソレアード2階 | 0761-22-0831 | 0761-22-0736 |
| 石川県 | 七尾 | 926-0816 | 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102 | 0767-52-6508 | 0767-52-6505 |
| 福井県 | 福井合同 | 910-0023 | 福井市順化1-24-43 ストークビル9階 | 0776-22-1584 | 0776-22-1505 |
| 福井県 | 武生 | 915-0813 | 越前市京町2-1-6 善光寺ビル1階 | 0778-23-5689 | 0778-23-2183 |
| 福井県 | 敦賀 | 914-0811 | 敦賀市中央町1-13-32 M&Mビル101 | 0770-23-3598 | 0770-23-3598 |
| 山梨県 | 甲府 | 400-0024 | 甲府市北口1-3-1 | 055-252-7752 | 055-252-7813 |
| 山梨県 | 大月 | 401-0011 | 大月市駒橋1-2-27 大月織物協同組合2階 | 0554-23-1452 | 0554-23-1457 |
| 長野県 | 長野合同 | 380-0872 | 長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1階 | 026-234-8585 | 026-234-8558 |
| 長野県 | 上田 | 386-0023 | 上田市中央西1-15-32 フコク生命上田ビル3階 | 0268-22-5477 | 0268-28-5007 |
| 長野県 | 松本 | 390-0874 | 松本市大手2-5-1 モモセビル3階 | 0263-35-6309 | 0263-35-7309 |
| 長野県 | 諏訪 | 392-0026 | 諏訪市大手2-17-16 信濃ビル3階 | 0266-53-4641 | 0266-78-9030 |
| 長野県 | 飯田 | 395-0033 | 飯田市常盤町30 飯伊森林組合ビル2階 | 0265-23-6502 | 0265-23-6502 |
| 長野県 | 伊那 | 396-0023 | 伊那市山寺298-1 福祉まちづくりセンター3階 | 0265-73-8622 | 0265-73-8622 |
| 長野県 | 佐久 | 385-0027 | 佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階 | 0267-54-8305 | 0267-54-8306 |
| 岐阜県 | 岐阜合同 | 500-8856 | 岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階 | 058-263-6582 | 058-262-3929 |
| 岐阜県 | 大垣 | 503-0888 | 大垣市丸の内1-35 | 0584-78-6174 | 0584-78-6271 |
| 岐阜県 | 美濃加茂 | 505-0034 | 美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階 | 0574-26-4436 | 0574-26-1447 |
| 岐阜県 | 高山 | 506-0009 | 高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階 | 0577-32-4148 | 0577-32-4140 |
| 岐阜県 | 多治見 | 507-0033 | 多治見市本町5-15-2 | 0572-23-6782 | 0572-26-7132 |
| 静岡県 | 静岡合同 | 420-0853 | 静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階 | 054-252-8988 | 054-251-0944 |
| 静岡県 | 沼津合同 | 410-0801 | 沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階 | 055-962-5731 | 055-962-5766 |
| 静岡県 | 熱海 | 413-0005 | 熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階 | 0557-82-7770 | 0557-82-7788 |
| 静岡県 | 富士 | 417-0055 | 富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階 | 0545-51-4958 | 0545-51-4957 |
| 静岡県 | 浜松合同 | 430-0946 | 浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 | 053-452-0718 | 053-452-4308 |
| 静岡県 | 掛川 | 436-0056 | 掛川市中央2-4-27 中央ビル5階 | 0537-22-2304 | 0537-22-2459 |
| 静岡県 | 袋井 | 437-0023 | 袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階 | 0538-42-8412 | 0538-30-7587 |
| 静岡県 | 下田 | 415-0036 | 下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階 | 0558-22-5521 | 0558-22-5521 |
| 静岡県 | 焼津 | 421-0205 | 焼津市宗高900番地 焼津市役所大井川庁舎2階 | 054-668-9933 | 054-668-9934 |
| 愛知県 | 葵町 | 461-0002 | 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 | 052-931-0353 | 052-931-0327 |
| 愛知県 | 熱田 | 456-0031 | 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 | 052-682-5973 | 052-682-5561 |
| 愛知県 | 名古屋駅前 | 450-0003 | 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 | 052-551-9737 | 052-571-0138 |
| 愛知県 | 春日井 | 486-0844 | 春日井市鳥居松町4-52 | 0568-85-9351 | 0568-85-9352 |
| 愛知県 | 一宮 | 491-0858 | 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 | 0586-72-4925 | 0586-72-1866 |
| 愛知県 | 半田 | 475-0902 | 半田市宮路町273 柊ビル2階 | 0569-22-1551 | 0569-22-1529 |
| 愛知県 | 岡崎合同 | 444-0813 | 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター2階 | 0564-58-8193 | 0564-58-8221 |
| 愛知県 | 豊田 | 471-0027 | 豊田市喜多町6-3-4 | 0565-34-1731 | 0565-41-6167 |
| 愛知県 | 豊橋合同 | 440-0888 | 豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 | 0532-52-2312 | 0532-53-9090 |
| 愛知県 | 西尾 | 445-0852 | 西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 | 0563-54-5699 | 0563-54-5874 |
| 愛知県 | 新城 | 441-1374 | 新城市字町並16 | 0536-23-5768 | 0536-23-7590 |
| 三重県 | 津合同 | 514-0036 | 津市丸之内養正町7-3 山田ビル | 059-228-9373 | 059-228-9731 |
| 三重県 | 松阪合同 | 515-0034 | 松阪市南町178-5 | 0598-23-7883 | 0598-23-7249 |
| 三重県 | 四日市合同 | 510-0074 | 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階 | 059-353-3394 | 059-352-6903 |
| 三重県 | 伊勢 | 516-0037 | 伊勢市岩渕2-5-1 伊勢駅前三交ビル5階 | 0596-28-6506 | 0596-28-6508 |
| 三重県 | 伊賀上野 | 518-0873 | 伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階 | 0595-23-6549 | 0595-23-6557 |
| 滋賀県 | 大津 | 520-0043 | 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階 | 077-523-1728 | 077-523-5028 |
| 滋賀県 | 長浜 | 526-0042 | 長浜市勝町715 | 0749-63-8377 | 0749-68-1771 |
| 滋賀県 | 近江八幡 | 523-0892 | 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階 | 0748-33-2988 | 0748-32-6763 |
| 京都府 | 京都合同 | 604-8187 | 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階 | 075-231-4338 | 075-231-0550 |
| 京都府 | 宇治 | 611-0021 | 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階 | 0774-23-8220 | 0774-23-8320 |
| 京都府 | 舞鶴 | 624-0855 | 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階 | 0773-75-6520 | 0773-75-6503 |
| 京都府 | 福知山 | 620-0045 | 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階 | 0773-23-6309 | 0773-45-8090 |
| 大阪府 | 平野町 | 541-0046 | 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階 | 06-6231-8587 | 06-6231-7551 |
| 大阪府 | 本町 | 541-0052 | 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 | 06-6271-6265 | 06-6266-4069 |
| 大阪府 | 江戸堀 | 550-0002 | 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 | 06-6443-9489 | 06-6449-0527 |
| 大阪府 | 難波 | 556-0011 | 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 | 06-6643-9304 | 06-6643-5020 |
| 大阪府 | 上六 | 543-0021 | 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 | 06-6763-3648 | 06-6762-5690 |
| 大阪府 | 梅田 | 530-0012 | 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階 | 06-6376-4158 | 06-6374-3670 |
| 大阪府 | 枚方 | 573-0027 | 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 | 072-841-2325 | 072-841-2326 |
| 大阪府 | 堺合同 | 590-0076 | 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 | 072-233-1412 | 072-233-1441 |
| 大阪府 | 岸和田 | 596-0054 | 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 | 072-422-3295 | 072-422-4649 |
| 大阪府 | 東大阪 | 577-0809 | 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 | 06-6725-3882 | 06-6725-3883 |
| 大阪府 | 高槻 | 569-1123 | 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階西 | 072-681-8500 | 072-681-2252 |
| 兵庫県 | 神戸 | 650-0037 | 神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階 | 078-391-1180 | 078-391-2803 |
| 兵庫県 | 伊丹 | 664-0846 | 伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 | 072-772-4646 | 072-772-4656 |
| 兵庫県 | 阪神 | 661-0012 | 尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階 | 06-4961-6671 | 06-4961-6685 |
| 兵庫県 | 明石 | 673-0891 | 明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 | 078-912-1499 | 078-914-9414 |
| 兵庫県 | 姫路東 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 | 079-223-0526 | 079-223-0531 |
| 兵庫県 | 姫路西 | 670-0935 | 姫路市北条口2-18 宮本ビル2階 | 079-222-1054 | 079-222-1053 |
| 兵庫県 | 洲本 | 656-0025 | 洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 | 0799-24-3454 | 0799-24-3454 |
| 兵庫県 | 豊岡 | 668-0024 | 豊岡市寿町2-20 寿センタービル203 | 0796-22-0796 | 0796-34-6266 |
| 兵庫県 | 龍野 | 679-4167 | たつの市龍野町富永300-13 中岡ビル2階 | 0791-62-1393 | 0791-62-1393 |
| 兵庫県 | 加古川 | 675-0031 | 加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 | 0794-21-5282 | 0794-21-5474 |
| 奈良県 | 奈良合同 | 630-8115 | 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階 | 0742-81-8511 | 0742-81-8910 |
| 奈良県 | 高田 | 635-0095 | 大和高田市大字大中98 おがわビル2階 | 0745-22-7166 | 0745-22-1254 |
| 和歌山県 | 和歌山合同 | 640-8157 | 和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階 | 073-422-3376 | 073-428-0541 |
| 和歌山県 | 田辺 | 646-0032 | 田辺市下屋敷町37 西原ビル2階 | 0739-22-1873 | 0739-22-1873 |
| 和歌山県 | 御坊 | 644-0012 | 御坊市湯川町小松原549-1 アスリービル1階 | 0738-22-7320 | 0738-22-7320 |
| 和歌山県 | 新宮 | 647-0043 | 新宮市緑ケ丘2-1-31 カマツカビル3階 | 0735-21-2344 | 0735-21-2378 |
| 和歌山県 | 橋本 | 648-0073 | 橋本市市脇1-3-18 橋本商工会館3階 | 0736-32-9745 | 0736-32-9745 |
| 鳥取県 | 鳥取合同 | 680-0845 | 鳥取市富安2-159 久本ビル5階 | 0857-24-3030 | 0857-24-6773 |
| 鳥取県 | 米子 | 683-0823 | 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206 | 0859-32-3399 | 0859-32-3440 |
| 鳥取県 | 倉吉 | 682-0816 | 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階 | 0858-22-0437 | 0858-22-0437 |
| 島根県 | 松江 | 690-0886 | 松江市母衣町95 古田ビル2階 | 0852-21-6309 | 0852-21-6309 |
| 島根県 | 浜田 | 697-0016 | 浜田市野原町1826-1 いわみーる2階 | 0855-22-7281 | 0855-28-7281 |
| 岡山県 | 岡山公証センター | 700-0815 | 岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル4階 | 086-223-9348 | 086-225-5874 |
| 岡山県 | 岡山合同 | 700-0821 | 岡山市北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階 | 086-222-7537 | 086-232-7080 |
| 岡山県 | 倉敷 | 710-0824 | 倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館5階 | 086-422-4057 | 086-422-4069 |
| 岡山県 | 津山 | 708-0076 | 津山市上紺屋町1番地 モスト21ビル2階 | 0868-22-5310 | 0868-22-5310 |
| 岡山県 | 笠岡 | 714-0081 | 笠岡市笠岡507-74 | 0865-62-5409 | 0865-62-5409 |
| 広島県 | 広島合同 | 730-0037 | 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 | 082-247-7277 | 082-247-7276 |
| 広島県 | 東広島 | 739-0043 | 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 | 082-422-3733 | 082-422-3733 |
| 広島県 | 呉 | 737-0051 | 呉市中央3-1-26 第一ビル3階 | 0823-21-2938 | 0823-36-6771 |
| 広島県 | 尾道 | 722-0014 | 尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 | 0848-22-3712 | 0848-22-3727 |
| 広島県 | 福山 | 720-0034 | 福山市若松町10-7 若松ビル3階 | 084-925-1487 | 084-925-1489 |
| 広島県 | 三次 | 728-0014 | 三次市十日市南1-4-11 | 0824-62-3381 | 0824-62-3381 |
| 山口県 | 山口 | 753-0045 | 山口市黄金町3-5 | 083-925-0035 | 083-925-0036 |
| 山口県 | 徳山 | 745-0034 | 周南市御幸通2-12 秋本ビル5階 | 0834-31-1745 | 0834-31-1746 |
| 山口県 | 岩国 | 740-0022 | 岩国市山手町1-16-10 山手町ビル2階 | 0827-22-5116 | 0827-22-5116 |
| 山口県 | 下関唐戸 | 750-0004 | 下関市中之町6-4 大和交通ビル4階 | 083-222-6693 | 083-222-6696 |
| 山口県 | 宇部 | 755-0032 | 宇部市寿町3-8-21 | 0836-34-2686 | 0836-34-2823 |
| 山口県 | 萩 | 758-0071 | 萩市大字瓦町16 三好ビル2階 | 0838-22-5517 | 0838-21-7665 |
| 徳島県 | 徳島 | 770-0841 | 徳島市八百屋町3-15 サンコーポ徳島ビル7階 | 088-625-6575 | 088-652-2314 |
| 香川県 | 高松 | 760-0050 | 高松市亀井町2番地1 朝日生命高松ビル7階 | 087-813-3536 | 087-813-3546 |
| 香川県 | 丸亀 | 763-0024 | 丸亀市塩飽町9-1 | 0877-23-4734 | 0877-23-4734 |
| 愛媛県 | 松山合同 | 790-0801 | 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階 | 089-941-3871 | 089-943-3727 |
| 愛媛県 | 八幡浜 | 796-0048 | 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階 | 0894-22-2070 | 0894-22-2070 |
| 愛媛県 | 新居浜 | 792-0025 | 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階 | 0897-35-3110 | 0897-35-3126 |
| 愛媛県 | 宇和島 | 798-0003 | 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階 | 0895-25-2292 | 0895-22-5076 |
| 愛媛県 | 今治 | 794-0042 | 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階 | 0898-23-2778 | 0898-23-2778 |
| 高知県 | 高知合同 | 780-0870 | 高知市本町1-1-3 朝日生命高知本町ビル3階 | 088-823-8601 | 088-872-4736 |
| 高知県 | 中村 | 787-0033 | 四万十市中村大橋通6-3-7 第一とらやビル4階 | 0880-34-1728 | 0880-34-9766 |
| 福岡県 | 福岡 | 810-0073 | 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 | 092-741-0310 | 092-741-0540 |
| 福岡県 | 博多 | 812-0011 | 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 | 092-400-2560 | 092-432-6681 |
| 福岡県 | 久留米 | 830-0023 | 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル | 0942-32-3307 | 0942-39-2321 |
| 福岡県 | 大牟田 | 836-0843 | 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 | 0944-52-5944 | 0944-52-5953 |
| 福岡県 | 小倉合同 | 803-0811 | 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階 | 093-561-5059 | 093-561-5060 |
| 福岡県 | 八幡合同 | 806-0021 | 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 | 093-644-1525 | 093-644-1526 |
| 福岡県 | 田川 | 826-0031 | 田川市千代町8-46 | 0947-44-4130 | 0947-44-4130 |
| 福岡県 | 直方 | 822-0015 | 直方市新町2-1-24 | 0949-24-6226 | 0949-24-6226 |
| 福岡県 | 飯塚 | 820-0067 | 飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 | 0948-22-3579 | 0948-22-6810 |
| 福岡県 | 行橋 | 824-0001 | 行橋市行事4-20-61 | 0930-22-4870 | 0930-22-4870 |
| 福岡県 | 筑紫 | 818-0105 | 太宰府市都府楼南5-5-13 | 092-925-9755 | 092-925-2010 |
| 佐賀県 | 佐賀合同 | 840-0801 | 佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命駅前ビル7階 | 0952-22-4387 | 0952-22-4039 |
| 佐賀県 | 唐津 | 847-0016 | 唐津市東城内17-29 唐津商工共済ビル2階 | 0955-72-1083 | 0955-72-1083 |
| 長崎県 | 長崎合同 | 850-0033 | 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階 | 095-821-3744 | 095-820-7877 |
| 長崎県 | 諫早 | 854-0016 | 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階 | 0957-23-4559 | 0957-23-4559 |
| 長崎県 | 佐世保 | 857-0052 | 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階 | 0956-22-6081 | 0956-22-2703 |
| 長崎県 | 島原 | 855-0034 | 島原市田町675-6 | 0957-62-7822 | 0957-62-7822 |
| 熊本県 | 熊本合同 | 862-0976 | 熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階 | 096-364-2700 | 096-364-2702 |
| 熊本県 | 八代 | 866-0861 | 八代市本町2-4-29 | 0965-32-6289 | 0965-32-6253 |
| 熊本県 | 天草 | 863-0037 | 天草市諏訪町2-10 武内ビル1階 | 0969-22-3666 | 0969-22-3758 |
| 大分県 | 大分合同 | 870-0045 | 大分市城崎町2-1-9 城崎MKビル2階 | 097-535-0888 | 097-535-0891 |
| 大分県 | 中津 | 871-0031 | 中津市大字中殿558-2 ハーブタウンⅢ1階 | 0979-25-2695 | 0979-25-2695 |
| 大分県 | 日田 | 877-0024 | 日田市南元町5-28 | 0973-24-6751 | 0973-24-6791 |
| 宮崎県 | 宮崎合同 | 880-0802 | 宮崎市別府町2-5コスモ別府ビル2階 | 0985-28-3038 | 0985-28-3809 |
| 宮崎県 | 都城 | 885-0025 | 都城市前田町15街区10-1 | 0986-22-1804 | 0986-57-0770 |
| 宮崎県 | 延岡 | 882-0823 | 延岡市中町2-1-7 延岡ビル5階 | 0982-21-1339 | 0982-21-1340 |
| 宮崎県 | 日南 | 887-0031 | 日南市戸高1-3-2 | 0987-23-5430 | 0987-23-5430 |
| 鹿児島県 | 鹿児島合同 | 892-0817 | 鹿児島市小川町1-11 | 099-222-2817 | 099-222-2391 |
| 鹿児島県 | 川内 | 895-0061 | 薩摩川内市御陵下町14-1 | 0996-22-5448 | 0996-24-0151 |
| 鹿児島県 | 鹿屋 | 893-0014 | 鹿屋市寿1-19-2-1 | 0994-41-3339 | 0994-41-3339 |
| 鹿児島県 | 名瀬 | 894-0006 | 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階 | 0997-52-2661 | 0997-52-2661 |
| 沖縄県 | 那覇公証センター | 902-0067 | 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階 | 098-862-3161 | 098-862-4211 |
| 沖縄県 | 沖縄 | 904-2153 | 沖縄市美里1-2-3 | 098-938-9380 | 098-938-5131 |
相続税申告不要でも確定申告が必要になる
1遺産相続で確定申告は原則不要
①確定申告は所得税の申告
確定申告とは、所得税の申告です。
1年間の所得から納めるべき所得税を計算して、国に申告します。
毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて、翌年3月15日までに申告し納税します。
遺産相続で多額の財産を引き継ぐことがあるでしょう。
遺産相続で財産を引き継いでも、所得ではありません。
所得税の申告は、原則として不要です。
確定申告は、所得税の申告です。
②準確定申告は被相続人の確定申告
確定申告は、毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて申告します。
所得税を申告・納税すべき人が年の途中で死亡することがあります。
準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。
生きている人の確定申告と区別するため、準確定申告を言います。
準確定申告は、被相続人の確定申告です。
③遺産相続は相続税の対象
遺産相続で多額の財産を手にしても、原則として所得税の対象ではありません。
相続によって財産を引き継いだ場合、相続税の対象になります。
相続税と所得税は、課税される対象が異なります。
相続税申告が必要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。
相続税申告が不要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。
相続税申告が不要であるうえ、確定申告が不要であることがあります。
相続税と所得税は、課税される対象が異なるからです。
遺産相続は、相続税の対象です。
2遺産相続で相続人の確定申告が必要になるケース
①生命保険の死亡保険金を受取
被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡保険金が払われます。
被相続人が自分で保険料を負担していた場合、死亡保険金は相続税の対象です。
死亡保険金の受取人が保険料を負担していた場合、死亡保険金は所得税の対象です。
死亡保険金の受取人と保険料負担者が同一人物の場合、確定申告が必要です。
死亡保険金の受取方法によって、一時所得または雑所得で課税されます。
生命保険の死亡保険金を受取ったケースでは、確定申告が必要です。
②相続した不動産を売却
相続した不動産を売却することがあります。
不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。
不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。
不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。
不動産の売却によって損失が出たときは、確定申告は不要です。
譲渡所得には、さまざまな控除や特例があります。
控除や特例を受けて、所得が0円になることがあります。
控除や所得を受けるため、所得0円であっても確定申告が必要です。
相続した不動産を売却したケースでは、確定申告が必要です。
③事業を引継
被相続人が個人事業を営んでいることがあります。
相続の発生で、相続人が事業を引き継ぐことがあるでしょう。
被相続人の事業を引き継いだ場合、相続発生後は相続人の収入になります。
相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。
事業を引継いだケースでは、確定申告が必要です。
④収益不動産を引継
被相続人が収益不動産などを保有していることがあります。
遺産相続にによって、収益不動産を引き継ぎます。
相続発生日以降にも、収益を生み続けるでしょう。
相続発生日以降の収益は、相続人の収入です。
相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。
収益不動産を引継いだケースでは、確定申告が必要です。
⑤国などへ遺産を寄付
相続した財産から国などへ寄付をすることがあります。
寄付した団体によっては、寄付金控除を受けることができます。
寄付を受けた団体からの受領書を添えて、確定申告をすることができます。
確定申告をすることは、義務ではありません。
寄付金控除を受けることで、所得税を減らすチャンスがあります。
せっかく寄付をするのだから、確定申告をするのがおすすめです。
国などへ遺産を寄付したケースでは、確定申告がおすすめです。
⑥換価分割
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の大部分が高価な不動産である場合、相続財産の分け方の合意が難しくなるでしょう。
換価分割とは、高価な不動産を売却してお金にして分ける方法です。
不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。
不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。
不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。
換価分割では、売却代金を合意した割合で相続人に分割します。
不動産の値上がり益は、合意した割合で相続人が得たと言えます。
遺産分割協議書を添付して、各相続人が確定申告をします。
売却代金を受け取っただけの相続人は、確定申告を忘れがちです。
確定申告を怠ると、ペナルティーの対象になります。
換価分割したケースでは、確定申告が必要です。
⑦未支給年金の受取
年金は、後払いで支給されます。
年金受給者が死亡した月の分まで、支給されます。
例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。
年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。
4月分の年金は、6月に振込みがされます。
多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。
6月に支給される年金の振込みを受けることができません。
4月分の年金が未支給年金です。
未支給年金は、遺族の固有の財産です。
税務上は、遺族の一時所得として取り扱われます。
一時所得がある場合、原則として確定申告の対象です。
一時所得には、50万円の特別控除があります。
未支給年金を含めて一時所得が50万円未満であれば、確定申告は不要です。
未支給年金の受取したケースでは、確定申告が必要です。
3被相続人の準確定申告が必要になるケース
①準確定申告が必要になる人
準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。
準確定申告が必要になるのは、主に次の人です。
・事業所得や不動産所得があった人
・給与所得が2,000万円を超えている人
・2か所以上から給与所得を受け取っている人
・公的年金による収入が400万円を超える人
・給与、退職金以外で20万円以上の所得があった人
・生前に不動産や株式を売却し、譲渡所得があった人
②準確定申告をすると還付金が発生することがある
準確定申告は、被相続人の所得を取りまとめ適切に納税するために行います。
確定申告をするときに、さまざまな控除や特例を利用することがあるでしょう。
準確定申告で控除や特例を申告すると、納め過ぎた税金が還付されることがあります。
準確定申告をする義務はなくても、準確定申告をすることで還付金を得られるかもしれません。
③準確定申告の期限は4か月
準確定申告は、期限があります。
相続があったことを知った日の翌日から起算して、4か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。
相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。
あっという間に、4か月の期限になります。
準確定申告の期限は、相続が発生してから4か月です。
4相続税申告が必要なケースは10%未満
①基礎控除額以内なら相続税申告不要
税制は複雑なうえに、改正が度々あります。
相続税大増税!最高税率55%!!などと不安を煽っている専門家がたくさんいます。
相続税申告が必要なケースは、全体のわずか10%未満です。
相続税の税率が55%になるのは、資産額6億円以上の富裕層です。
90%以上の庶民には、心配する必要がない税金です。
相続税の申告が必要になるのは、一定以上の資産額があるケースです。
申告する必要があるか判断する基準となる一定額のことを、基礎控除と言います。
資産額が基礎控除より少ないのであれば、相続税申告は必要ありません。
基礎控除額は、次の計算式で求められます。
基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円
基礎控除額以内なら、相続税申告は不要です。
②特例や控除を活用して相続税がかからない
相続税には、さまざまな特例や控除があります。
相続税申告をする人の中には、納める税金がない人がたくさんいます。
家族にとって自宅などは、重要な財産であることが多いでしょう。
例えば、相続税には小規模宅地の特例という特例があります。
小規模宅地の特例を利用できれば、宅地等の評価額が80%減になります。
相続財産の大部分が自宅であるケースは、少なくありません。
自宅の評価額が80%減になれば、相続税が課されないことが多いでしょう。
特例や控除を活用して、相続税がかからないケースは珍しくありません。
③相続税申告の期限は10か月
相続税申告は、期限があります。
相続があったことを知った日の翌日から起算して、10か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。
相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。
あっという間に、10か月の期限になります。
相続税申告の期限は、相続が発生してから10か月です。
5相続対策を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
穏やかで温厚な人でも、疲れ果てているとトラブルに巻き込まれがちです。
インターネットの普及によって、たくさんの情報を手にすることができるようになりました。
その中には、適切なものもそうでないものも入り混じっています。
法律の知識がないと適切なのものとそうでないものの区別がつきません。
あいまいな知識で相続人全員の話し合いをすると、合意できることでさえ、トラブルに発展しがちで
す。
被相続人の希望が尊重されて、相続人全員にとって納得のいく財産分配が行われるのが大切です。
家族をトラブルから守るためには、事前の対策が欠かせません。
まずは相続について、家族の考えを確認してみましょう。
家族がトラブルを起こさないように対策したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
裁判所の住所電話番号一覧
1家庭裁判所の住所電話番号一覧
| 都道府県 | 名称 | 〒 | 住所 | TEL |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西12 | 011-350-4659 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所浦河支部 | 057-0012 | 浦河郡浦河町常盤町19 | 0146-22-4165 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所静内支部 | 056-0005 | 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10 | 0146-42-0120 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所苫小牧支部 | 053-0018 | 苫小牧市旭町2-7-12 | 0144-32-3295 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所室蘭支部 | 050-0081 | 室蘭市日の出町1-18-29 | 0143-44-6733 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所岩見沢支部 | 068-0004 | 岩見沢市4条東4 | 0126-22-6650 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所夕張出張所 | 068-0411 | 夕張市末広1-92-16 | 0123-52-2004 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所滝川支部 | 073-0022 | 滝川市大町1-6-13 | 0125-23-2311 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所小樽支部 | 047-0024 | 小樽市花園5-1-1 | 0134-22-9157 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所岩内支部 | 045-0013 | 岩内郡岩内町字高台192-1 | 0135-62-0138 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所 | 040-8602 | 函館市上新川町1-8 | 0138-38-2370 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所松前出張所 | 049-1501 | 松前郡松前町字建石48 | 0139-42-2122 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所八雲出張所 | 049-3112 | 二海郡八雲町末広町184 | 0137-62-2494 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所寿都出張所 | 048-0401 | 寿都郡寿都町字新栄町209 | 0136-62-2072 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所江差支部 | 043-0043 | 檜山郡江差町字本町237 | 0139-52-0174 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所 | 070-8641 | 旭川市花咲町4 | 0166-51-6251 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所深川出張所 | 074-0002 | 深川市2条1-4 | 0164-23-2813 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所富良野出張所 | 076-0018 | 富良野市弥生町2-55 | 0167-22-2209 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所留萌支部 | 077-0037 | 留萌市沖見町2 | 0164-42-0465 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所稚内支部 | 097-0002 | 稚内市潮見1-3-10 | 0162-33-5289 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所天塩出張所 | 098-3303 | 天塩郡天塩町新栄通7 | 01632-2-1146 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所紋別支部 | 094-0006 | 紋別市潮見町1-5-48 | 0158-23-2856 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所名寄支部 | 096-0014 | 名寄市西4条南9 | 01654-3-3331 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所中頓別出張所 | 098-5551 | 枝幸郡中頓別町字中頓別166-5 | 01634-6-1626 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所 | 085-0824 | 釧路市柏木町4-7 | 0154-41-4171 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所根室支部 | 087-0026 | 根室市敷島町2-3 | 0153-24-1617 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所標津出張所 | 086-1632 | 標津郡標津町北2条西1-1-17 | 0153-82-2046 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所帯広支部 | 080-0808 | 帯広市東8南9-1 | 0155-23-5141 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所本別出張所 | 089-3313 | 中川郡本別町柳町4 | 0156-22-2064 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所北見支部 | 090-0065 | 北見市寿町4-7-36 | 0157-24-8431 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所遠軽出張所 | 099-0403 | 紋別郡遠軽町1条通北2-3-25 | 0158-42-2259 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所網走支部 | 093-0031 | 網走市台町2-2-1 | 0152-43-4115 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所 | 030-8523 | 青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所むつ出張所 | 035-0073 | むつ市中央1-1-5 | 0175-22-2712 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 039-3131 | 上北郡野辺地町字野辺地419 | 0175-64-3279 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所弘前支部 | 036-8356 | 弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-4371 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所五所川原支部 | 037-0044 | 五所川原市字元町54 | 0173-34-2927 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所八戸支部 | 039-1166 | 八戸市根城9-13-6 | 0178-22-3167 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所十和田支部 | 034-0082 | 十和田市西二番町14-8 | 0176-23-2368 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所 | 030-8523 | 青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所むつ出張所 | 035-0073 | むつ市中央1-1-5 | 0175-22-2712 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 039-3131 | 上北郡野辺地町字野辺地419 | 0175-64-3279 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所弘前支部 | 036-8356 | 弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-4371 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所五所川原支部 | 037-0044 | 五所川原市字元町54 | 0173-34-2927 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所八戸支部 | 039-1166 | 八戸市根城9-13-6 | 0178-22-3167 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所十和田支部 | 034-0082 | 十和田市西二番町14-8 | 0176-23-2368 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所 | 020-8520 | 盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所花巻支部 | 025-0075 | 花巻市花城町8-26 | 0198-23-5276 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所二戸支部 | 028-6101 | 二戸市福岡字城ノ内4-2 | 0195-23-2591 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所久慈出張所 | 028-0022 | 久慈市田屋町2-50-5 | 0194-53-4158 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所遠野支部 | 028-0515 | 遠野市東舘町2-3 | 0198-62-2840 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所宮古支部 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-30 | 0193-62-2925 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所一関支部 | 021-0877 | 一関市城内3-6 | 0191-23-4148 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所大船渡出張所 | 022-0003 | 大船渡市盛町字宇津野沢9-3 | 0192-26-3630 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所水沢支部 | 023-0053 | 奥州市水沢区大手町4-19 | 0197-24-7181 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所 | 020-8520 | 盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所花巻支部 | 025-0075 | 花巻市花城町8-26 | 0198-23-5276 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所二戸支部 | 028-6101 | 二戸市福岡字城ノ内4-2 | 0195-23-2591 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所久慈出張所 | 028-0022 | 久慈市田屋町2-50-5 | 0194-53-4158 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所遠野支部 | 028-0515 | 遠野市東舘町2-3 | 0198-62-2840 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所宮古支部 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-30 | 0193-62-2925 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所一関支部 | 021-0877 | 一関市城内3-6 | 0191-23-4148 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所大船渡出張所 | 022-0003 | 大船渡市盛町字宇津野沢9-3 | 0192-26-3630 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所水沢支部 | 023-0053 | 奥州市水沢区大手町4-19 | 0197-24-7181 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所 | 980-8637 | 仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-4165 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所大河原支部 | 989-1231 | 柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2102 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所古川支部 | 989-6161 | 大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1694 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所登米支部 | 987-0702 | 登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所石巻支部 | 986-0832 | 石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0363 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 988-0022 | 気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6626 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所 | 010-8504 | 秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所本荘支部 | 015-0872 | 由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所能代支部 | 016-0817 | 能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所大館支部 | 017-0891 | 大館市中城15 | 0186-42-0071 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所鹿角支部 | 018-5201 | 鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所大曲支部 | 014-0063 | 大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所角館支部 | 014-0372 | 仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所横手支部 | 013-0013 | 横手市城南町2-1 | 0182-32-4206 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所 | 010-8504 | 秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所本荘支部 | 015-0872 | 由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所能代支部 | 016-0817 | 能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所大館支部 | 017-0891 | 大館市中城15 | 0186-42-0071 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所鹿角支部 | 018-5201 | 鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所大曲支部 | 014-0063 | 大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所角館支部 | 014-0372 | 仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所横手支部 | 013-0013 | 横手市城南町2-1 | 0182-32-4206 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所 | 990-8531 | 山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所新庄支部 | 996-0022 | 新庄市住吉町4-27 | 0233-22-0265 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所米沢支部 | 992-0045 | 米沢市中央4-9-15 | 0238-22-2165 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 999-2211 | 南陽市赤湯316 | 0238-43-2217 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所長井出張所 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-7-20 | 0238-88-2073 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 997-0035 | 鶴岡市馬場町5-23 | 0235-23-6666 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所酒田支部 | 998-0037 | 酒田市日吉町1-5-27 | 0234-23-1234 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所 | 990-8531 | 山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所新庄支部 | 996-0022 | 新庄市住吉町4-27 | 0233-22-0265 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所米沢支部 | 992-0045 | 米沢市中央4-9-15 | 0238-22-2165 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 999-2211 | 南陽市赤湯316 | 0238-43-2217 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所長井出張所 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-7-20 | 0238-88-2073 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 997-0035 | 鶴岡市馬場町5-23 | 0235-23-6666 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所酒田支部 | 998-0037 | 酒田市日吉町1-5-27 | 0234-23-1234 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所 | 960-8112 | 福島市花園町5-38 | 024-534-2156 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所相馬支部 | 976-0042 | 相馬市中村字大手先48-1 | 0244-36-5162 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所郡山支部 | 963-8566 | 郡山市麓山1-2-26 | 024-932-5855 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所白河支部 | 961-0074 | 白河市郭内146 | 0248-22-5591 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 963-6131 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1 | 0247-33-3458 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所会津若松支部 | 965-8540 | 会津若松市追手町6-6 | 0242-26-5831 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所田島出張所 | 967-0004 | 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3 | 0241-62-0211 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所いわき支部 | 970-8026 | いわき市平字八幡小路41 | 0246-22-1376 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所 | 960-8112 | 福島市花園町5-38 | 024-534-2156 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所相馬支部 | 976-0042 | 相馬市中村字大手先48-1 | 0244-36-5162 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所郡山支部 | 963-8566 | 郡山市麓山1-2-26 | 024-932-5855 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所白河支部 | 961-0074 | 白河市郭内146 | 0248-22-5591 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 963-6131 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1 | 0247-33-3458 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所会津若松支部 | 965-8540 | 会津若松市追手町6-6 | 0242-26-5831 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所田島出張所 | 967-0004 | 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3 | 0241-62-0211 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所いわき支部 | 970-8026 | いわき市平字八幡小路41 | 0246-22-1376 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所 | 310-0062 | 水戸市大町1-1-38 | 029-224-8513 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所日立支部 | 317-0073 | 日立市幸町2-10-12 | 0294-21-4441 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所土浦支部 | 300-8567 | 土浦市中央1-13-12 | 029-821-4359 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部 | 301-0824 | 龍ヶ崎市4918 | 0297-62-0100 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所麻生支部 | 311-3832 | 行方市麻生143 | 0299-72-0091 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所下妻支部 | 304-0067 | 下妻市下妻乙99 | 0296-43-6781 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所 | 320-8505 | 宇都宮市小幡1-1-38 | 028-621-2111 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所真岡支部 | 321-4305 | 真岡市荒町5117-2 | 0285-82-2076 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所大田原支部 | 324-0056 | 大田原市中央2-3-25 | 0287-22-2112 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所栃木支部 | 328-0035 | 栃木市旭町16-31 | 0282-23-0225 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所足利支部 | 326-0057 | 足利市丸山町621 | 0284-41-3118 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所 | 371-8531 | 前橋市大手町3-1-34 | 027-231-4275 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所中之条出張所 | 377-0424 | 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 | 0279-75-2138 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所沼田支部 | 378-0045 | 沼田市材木町甲150 | 0278-22-2709 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所太田支部 | 373-8531 | 太田市浜町17-5 | 0276-45-7751 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所桐生支部 | 376-8531 | 桐生市相生町2-371-5 | 0277-53-2391 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所高崎支部 | 370-8531 | 高崎市高松町26-2 | 027-322-3541 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所 | 330-0063 | さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-8761 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 346-0016 | 久喜市久喜東1-15-3 | 0480-21-0157 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所越谷支部 | 343-0023 | 越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0132 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所川越支部 | 350-8531 | 川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3031 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 357-0021 | 飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 360-0041 | 熊谷市宮町1-68 | 048-500-3120 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所秩父支部 | 368-0035 | 秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所 | 260-0013 | 千葉市中央区中央4-11-27 | 043-333-5302 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所市川出張所 | 272-8511 | 市川市鬼高2-20-20 | 047-336-3002 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所佐倉支部 | 285-0038 | 佐倉市弥勒町92 | 043-484-1216 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所一宮支部 | 299-4397 | 長生郡一宮町一宮2791 | 0475-42-3531 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所松戸支部 | 271-8522 | 松戸市岩瀬無番地 | 047-368-5141 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所木更津支部 | 292-0832 | 木更津市新田2-5-1 | 0438-22-3774 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所館山支部 | 294-0045 | 館山市北条1073 | 0470-22-2273 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所八日市場支部 | 289-2144 | 匝嵯市八日市場イ-2760 | 0479-72-1300 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所佐原支部 | 287-0003 | 香取市佐原イ3375 | 0478-52-3040 |
| 東京都 | 東京家庭裁判所 | 100-8956 | 千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8311 |
| 東京都 | 東京家庭裁判所八丈島出張所 | 100-1401 | 八丈島八丈町大賀郷1485-1 | 04996-2-0619 |
| 東京都 | 東京家庭裁判所 | 100-0101 | 大島町元町字家の上445-10 | 04992-2-1165 |
| 東京都 | 東京家庭裁判所立川支部 | 190-8589 | 立川市緑町10-4 | 042-845-0365 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所 | 231-8585 | 横浜市中区寿町1-2 | 045-345-3505 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所相模原支部 | 252-0236 | 相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-755-8661 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所川崎支部 | 210-8537 | 川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-222-1315 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所横須賀支部 | 238-8513 | 横須賀市新港町1-9 | 046-825-0569 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所小田原支部 | 250-0012 | 小田原市本町1-7-9 | 0465-22-6586 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所 | 951-8513 | 新潟市中央区川岸町1-54-1 | 025-266-3171 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所三条支部 | 955-0047 | 三条市東三条2-2-2 | 0256-32-1758 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所新発田支部 | 957-0053 | 新発田市中央町4-3-27 | 0254-24-0121 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所村上出張所 | 958-0837 | 村上市三之町8-16 | 0254-53-2066 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所佐渡支部 | 952-1324 | 佐渡市中原356-2 | 0259-52-3151 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所長岡支部 | 940-1151 | 長岡市三和3-9-28 | 0258-35-2141 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所十日町出張所 | 948-0065 | 十日町市子442 | 025-752-2086 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所柏崎出張所 | 945-0063 | 柏崎市諏訪町10-37 | 0257-22-2090 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所南魚沼出張所 | 949-6680 | 南魚沼市六日町1884-子 | 025-772-2450 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所高田支部 | 943-0838 | 上越市大手町1-26 | 025-524-5160 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所糸魚川出張所 | 941-0058 | 糸魚川市寺町2-8-23 | 025-552-0058 |
| 富山県 | 富山家庭裁判所 | 939-8502 | 富山市西田地方町2-9-1 | 076-421-6324 |
| 富山県 | 富山家庭裁判所魚津支部 | 937-0866 | 魚津市本町1-10-60 | 0765-22-0160 |
| 富山県 | 富山家庭裁判所高岡支部 | 933-8546 | 高岡市中川本町10-6 | 0766-22-5151 |
| 富山県 | 富山家庭裁判所砺波出張所 | 939-1367 | 砺波市広上町8-24 | 0763-32-2118 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所 | 920-8655 | 金沢市丸の内7-1 | 076-221-3111 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所小松支部 | 923-8541 | 小松市小馬出町11 | 0761-22-8541 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所七尾支部 | 926-8541 | 七尾市馬出町ハ部1-2 | 0767-52-3135 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所輪島支部 | 928-8541 | 輪島市河井町15部49-2 | 0768-22-0054 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所珠洲出張所 | 927-1297 | 珠洲市上戸町北方い46-3 | 0768-82-0218 |
| 福井県 | 福井家庭裁判所 | 910-8524 | 福井市春山1-1-1 | 0776-22-5000 |
| 福井県 | 福井家庭裁判所武生支部 | 915-8524 | 越前市日野美2-6 | 0778-23-0050 |
| 福井県 | 福井家庭裁判所敦賀支部 | 914-8524 | 敦賀市松栄町6-10 | 0770-22-0812 |
| 福井県 | 福井家庭裁判所小浜出張所 | 917-8524 | 小浜市城内1-1-2 | 0770-52-0003 |
| 山梨県 | 甲府家庭裁判所 | 400-0032 | 甲府市中央1-10-7 | 055-213-2541 |
| 山梨県 | 甲府家庭裁判所都留支部 | 402-0052 | 都留市中央2-1-1 | 0554-56-7668 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所 | 380-0846 | 長野市旭町1108 | 026-403-2008 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所飯山出張所 | 389-2253 | 飯山市大字飯山1123 | 0269-62-2125 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所上田支部 | 386-0023 | 上田市中央西2-3-3 | 0268-40-2201 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所佐久支部 | 385-0022 | 佐久市岩村田1161 | 0267-67-1538 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所松本支部 | 390-0873 | 松本市丸の内10-35 | 0263-32-3043 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所木曾福島出張所 | 397-0001 | 木曽郡木曽町福島6205-13 | 0264-22-2021 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所大町出張所 | 398-0002 | 大町市大町4222-1 | 0261-22-0121 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所諏訪支部 | 392-0004 | 諏訪市諏訪1-24-22 | 0266-52-9211 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所飯田支部 | 395-0015 | 飯田市江戸町1-21 | 0265-22-0189 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所伊那支部 | 396-0026 | 伊那市西町4841 | 0265-72-2770 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所 | 500-8710 | 岐阜市美江寺町2-4-1 | 058-262-5121 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所郡上出張所 | 501-4213 | 郡上市八幡町殿町63-2 | 0575-65-2265 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所多治見支部 | 507-0023 | 多治見市小田町1-22-1 | 0572-22-0698 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所中津川出張所 | 508-0045 | 中津川市かやの木町4-2 | 0573-66-1530 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所御嵩支部 | 505-0116 | 可児郡御嵩町御嵩1177 | 0574-67-3111 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所大垣支部 | 503-0888 | 大垣市丸の内1-22 | 0584-78-6184 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所高山支部 | 506-0009 | 高山市花岡町2-63-3 | 0577-32-1140 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所 | 420-8604 | 静岡市葵区城内町1-20 | 054-273-5454 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所島田出張所 | 427-0043 | 島田市中溝4-11-10 | 0547-37-1630 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所沼津支部 | 410-8550 | 沼津市御幸町21-1 | 055-931-6000 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所熱海出張所 | 413-8505 | 熱海市春日町3-14 | 0557-81-2989 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所富士支部 | 417-8511 | 富士市中央町2-7-1 | 0545-52-0386 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所下田支部 | 415-8520 | 下田市4-7-34 | 0558-22-0161 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所浜松支部 | 430-8620 | 浜松市中区中央1-12-5 | 053-453-7155 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所掛川支部 | 436-0028 | 掛川市亀の甲2-16-1 | 0537-22-3036 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所 | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-223-3411 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所半田支部 | 475-0902 | 半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所一宮支部 | 491-0842 | 一宮市公園通4-17 | 0586-73-3191 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 444-8550 | 岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-8972 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 440-0884 | 豊橋市大国町110 | 0532-52-3212 |
| 三重県 | 津家庭裁判所 | 514-8526 | 津市中央3-1 | 059-226-4171 |
| 三重県 | 津家庭裁判所松阪支部 | 515-8525 | 松阪市中央町36-1 | 0598-51-0542 |
| 三重県 | 津家庭裁判所伊賀支部 | 518-0873 | 伊賀市上野丸之内130-1 | 0595-21-0002 |
| 三重県 | 津家庭裁判所伊勢支部 | 516-8533 | 伊勢市岡本1-2-6 | 0596-28-3135 |
| 三重県 | 津家庭裁判所熊野支部 | 519-4396 | 熊野市井戸町784 | 0597-85-2145 |
| 三重県 | 津家庭裁判所尾鷲出張所 | 519-3615 | 尾鷲市中央町6-23 | 0597-22-0448 |
| 三重県 | 津家庭裁判所四日市支部 | 510-8526 | 四日市市三栄町1-22 | 059-352-7185 |
| 滋賀県 | 大津家庭裁判所 | 520-0044 | 大津市京町3-1-2 | 077-503-8104 |
| 滋賀県 | 大津家庭裁判所高島出張所 | 520-1623 | 高島市今津町住吉1-3-8 | 0740-22-2148 |
| 滋賀県 | 大津家庭裁判所彦根支部 | 522-0061 | 彦根市金亀町5-50 | 0749-22-0167 |
| 滋賀県 | 大津家庭裁判所長浜支部 | 526-0058 | 長浜市南呉服町6-22 | 0749-62-0240 |
| 京都府 | 京都家庭裁判所 | 606-0801 | 京都市左京区下鴨宮河町1 | 075-722-7211(※) |
| 京都府 | 京都家庭裁判所園部支部 | 622-0004 | 南舟市園部町小桜町30 | 0771-62-0840 |
| 京都府 | 京都家庭裁判所舞鶴支部 | 624-0853 | 舞鶴市字南田辺小字南裏町149 | 0773-75-0958 |
| 京都府 | 京都家庭裁判所宮津支部 | 626-0017 | 宮津市字島崎2043-1 | 0772-22-2393 |
| 京都府 | 京都家庭裁判所福知山支部 | 620-0035 | 福知山市字内記9 | 0773-22-3663 |
| 大阪府 | 大阪家庭裁判所 | 540-0008 | 大阪市中央区大手前4-1-13 | 06-6943-5321 |
| 大阪府 | 大阪家庭裁判所堺支部 | 590-0078 | 堺市堺区南瓦町2-28 | 072-223-7001 |
| 大阪府 | 大阪家庭裁判所岸和田支部 | 596-0042 | 岸和田市加守町4-27-2 | 072-441-6803 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所 | 652-0032 | 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 078-521-5221 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所明石支部 | 673-0881 | 明石市天文町2-2-18 | 078-912-3233 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所伊丹支部 | 664-8545 | 伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3074 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所柏原支部 | 669-3309 | 丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所洲本支部 | 656-0024 | 洲本市山手1-1-18 | 0799-25-2332 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所尼崎支部 | 661-0026 | 尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所姫路支部 | 670-0947 | 姫路市北条1-250 | 079-281-2011 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所社支部 | 673-1431 | 加東市社490-2 | 0795-42-0123 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所龍野支部 | 679-4179 | たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所豊岡支部 | 668-0042 | 豊岡市京町12-81 | 0796-22-2881 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所浜坂出張所 | 669-6701 | 美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
| 奈良県 | 奈良家庭裁判所 | 630-8213 | 奈良市登大路町35 | 0742-26-1271 |
| 奈良県 | 奈良家庭裁判所葛城支部 | 635-8502 | 大和高田市大字大中101-4 | 0745-53-1774 |
| 奈良県 | 奈良家庭裁判所五條支部 | 637-0043 | 五條市新町3-3-1 | 0747-23-0261 |
| 奈良県 | 奈良家庭裁判所吉野出張所 | 638-0821 | 吉野郡大淀町大字下渕350-1 | 0747-52-2490 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所 | 640-8143 | 和歌山市二番丁1 | 073-422-4191 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所妙寺出張所 | 649-7113 | 伊都郡かつらぎ町妙寺111 | 0736-22-0033 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所田辺支部 | 646-0033 | 田辺市新屋敷町5 | 0739-22-2801 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所御坊支部 | 644-0011 | 御坊市湯川町財部515-2 | 0738-22-0006 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所新宮支部 | 647-0015 | 新宮市千穂3-7-13 | 0735-22-2007 |
| 鳥取県 | 鳥取家庭裁判所 | 680-0011 | 鳥取市東町2-223 | 0857-22-2171 |
| 鳥取県 | 鳥取家庭裁判所倉吉支部 | 682-0824 | 倉吉市仲ノ町734 | 0858-22-2911 |
| 鳥取県 | 鳥取家庭裁判所米子支部 | 683-0826 | 米子市西町62 | 0859-22-2408 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所 | 690-8523 | 松江市母衣町68 | 0852-23-1701 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所雲南出張所 | 699-1332 | 雲南市木次町木次980 | 0854-42-0275 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所出雲支部 | 693-8523 | 出雲市今市町797-2 | 0853-21-2114 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所浜田支部 | 697-0027 | 浜田市殿町980 | 0855-22-0678 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所川本出張所 | 696-0001 | 邑智郡川本町大字川本340 | 0855-72-0045 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所益田支部 | 698-0021 | 益田市幸町6-60 | 0856-22-0365 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所西郷支部 | 685-0015 | 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-1 | 08512-2-0005 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所 | 700-0807 | 岡山市南方1-8-42 | 086-222-6771 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所玉野出張所 | 706-0011 | 玉野市宇野2-2-1 | 0863-21-2908 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所児島出張所 | 711-0911 | 倉敷市児島小川1-4-14 | 086-473-1400 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所倉敷支部 | 710-8558 | 倉敷市幸町3-33 | 086-422-1393 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所玉島出張所 | 713-8102 | 倉敷市玉島1-2-43 | 086-522-3074 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所笠岡出張所 | 714-0081 | 笠岡市笠岡1732 | 0865-62-2234 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所新見支部 | 718-0011 | 新見市新見1222 | 0867-72-0042 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所津山支部 | 708-0051 | 津山市椿高下52 | 0868-22-9326 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所 | 730-0012 | 広島市中区上八丁堀1-6 | 082-228-0494 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所三次支部 | 728-0021 | 三次市三次町1725-1 | 0824-63-5169 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所呉支部 | 737-0811 | 呉市西中央4-1-46 | 0823-21-4992 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所福山支部 | 720-0031 | 福山市三吉町1-7-1 | 084-923-2806 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所尾道支部 | 722-0014 | 尾道市新浜1-12-4 | 0848-22-5286 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所 | 753-0048 | 山口市駅通り1-6-1 | 083-922-1330 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所宇部支部 | 755-0033 | 宇部市琴芝町2-2-35 | 0836-21-3197 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所船木出張所 | 757-0216 | 宇部市大字船木183 | 0836-67-0036 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所周南支部 | 745-0071 | 周南市岐山通り2-5 | 0834-21-2698 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所萩支部 | 758-0041 | 萩市大字江向469 | 0838-22-0047 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所岩国支部 | 741-0061 | 岩国市錦見1-16-45 | 0827-41-3181 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所柳井出張所 | 742-0002 | 柳井市山根10-20 | 0820-22-0270 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所下関支部 | 750-0009 | 下関市上田中町8-2-2 | 0832-22-2899 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所 | 770-8528 | 徳島市徳島町1-5-1 | 088-603-0111 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所阿南支部 | 774-0030 | 阿南市富岡町西池田口1-1 | 0884-22-0148 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所牟岐出張所 | 775-0006 | 海部郡牟岐町大字中村字本村54-2 | 0884-72-0074 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所美馬支部 | 779-3610 | 美馬市脇町大字脇町1229-3 | 0883-52-1035 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所池田出張所 | 778-0002 | 三好市池田町マチ2494-7 | 0883-72-0234 |
| 香川県 | 高松家庭裁判所 | 760-8585 | 高松市丸の内2-27 | 087-851-1631 |
| 香川県 | 高松家庭裁判所土庄出張所 | 761-4121 | 小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 | 0879-62-0224 |
| 香川県 | 高松家庭裁判所丸亀支部 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-4-1 | 0877-23-5340 |
| 香川県 | 高松家庭裁判所観音寺支部 | 768-0060 | 観音寺市観音寺町甲2804-1 | 0875-25-2619 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所 | 790-0006 | 松山市南堀端町2-1 | 089-942-5000 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所大洲支部 | 795-0012 | 大洲市大洲845 | 0893-24-2038 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所今治支部 | 794-8508 | 今治市常盤町4-5-3 | 0898-23-0010 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所西条支部 | 793-0023 | 西条市明屋敷165 | 0897-56-0696 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所宇和島支部 | 798-0033 | 宇和島市鶴島町8-16 | 0895-22-4466 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所愛南出張所 | 798-4131 | 南宇和郡愛南町城辺甲3827 | 0895-72-0044 |
| 高知県 | 高知家庭裁判所 | 780-8558 | 高知市丸ノ内1-3-5 | 088-822-0340 |
| 高知県 | 高知家庭裁判所安芸支部 | 784-0003 | 安芸市久世町9-25 | 0887-35-2065 |
| 高知県 | 高知家庭裁判所須崎支部 | 785-0010 | 須崎市鍛冶町2-11 | 0889-42-0046 |
| 高知県 | 高知家庭裁判所中村支部 | 787-0028 | 四万十市中村山手通54-1 | 0880-35-4741 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所 | 810-8652 | 福岡市中央区大手門1-7-1 | 092-711-9651 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所甘木出張所 | 838-0061 | 朝倉市菩堤寺571 | 0946-22-2113 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所飯塚支部 | 820-8506 | 飯塚市新立岩10-29 | 0948-22-1150 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所直方支部 | 822-0014 | 直方氏丸山町1-4 | 0949-22-0522 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所田川支部 | 826-8567 | 田川市千代町1-5 | 0947-42-0163 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所久留米支部 | 830-8512 | 久留米市篠山町21 | 0942-39-6943 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所八女支部 | 834-0031 | 八女市本町537-4 | 0943-23-4036 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所柳川支部 | 832-0045 | 柳川市本町4 | 0944-72-3832 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所大牟田支部 | 836-0052 | 大牟田市白金町101 | 0944-53-3504 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所小倉支部 | 803-8532 | 北九州市小倉北区金田1-4-1 | 093-561-3431 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所行橋支部 | 824-0001 | 行橋市行事1-8-23 | 0930-22-0035 |
| 佐賀県 | 佐賀家庭裁判所 | 840-0833 | 佐賀市中の小路3-22 | 0952-23-3161 |
| 佐賀県 | 佐賀家庭裁判所武雄支部 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄5660 | 0954-22-2159 |
| 佐賀県 | 佐賀家庭裁判所鹿島出張所 | 849-1311 | 鹿島市大字高津原3575 | 0954-62-2870 |
| 佐賀県 | 佐賀家庭裁判所唐津支部 | 847-0012 | 唐津市大名小路1-1 | 0955-72-2138 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所 | 850-0033 | 長崎市万才町6-25 | 095-822-6151 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所大村支部 | 856-0831 | 大村市東本町287 | 0957-52-3501 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所諫早出張所 | 854-0071 | 諫早市永昌東町24-12 | 0957-22-0421 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所島原支部 | 855-0036 | 島原市城内1-1195-1 | 0957-62-3151 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所五島支部 | 853-0001 | 五島市栄町1-7 | 0959-72-3315 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所新上五島出張所 | 857-4211 | 南松浦郡新上五島町有川郷2276-5 | 0959-42-0044 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所巌原支部 | 817-0013 | 対馬市厳原町中村642-1 | 0920-52-0067 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所上県出張所 | 817-1602 | 対馬市上県町佐須奈甲639-22 | 0920-84-2307 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所佐世保支部 | 857-0805 | 佐世保市光月町9-4 | 0956-22-9175 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所平戸支部 | 859-5153 | 平戸市戸石川町460 | 0950-22-2004 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所壱岐支部 | 811-5133 | 壱岐市郷ノ浦町本村触624-1 | 0920-47-1019 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所 | 860-0001 | 熊本市千葉城町3-31 | 096-355-6121 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所御船出張所 | 861-3206 | 上益城郡御船町辺田見1250-1 | 096-282-0055 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所阿蘇支部 | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2476-1 | 0967-22-0063 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所高森出張所 | 869-1602 | 阿蘇郡高森町高森1385-6 | 0967-62-0069 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所玉名支部 | 865-0051 | 玉名市繁根木54-8 | 0968-72-3037 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所山鹿支部 | 861-0501 | 山鹿市山鹿280 | 0968-44-5141 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所八代支部 | 866-8585 | 八代市西松江城町1-41 | 0965-32-2175 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所水俣出張所 | 867-0041 | 水俣市天神町1-1-1 | 0966-62-2307 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所人吉支部 | 868-0056 | 人吉市寺町1 | 0966-23-4855 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所天草支部 | 863-8585 | 天草市諏訪町16-24 | 0969-23-2004 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所牛深出張所 | 863-1901 | 天草市牛深町2061-17 | 0969-72-2540 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所 | 870-8564 | 大分市荷揚町7-15 | 097-532-7161 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所杵築支部 | 873-0001 | 杵築市大字杵築1180 | 0978-62-2052 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所佐伯支部 | 876-0815 | 佐伯市野岡町2-13-2 | 0972-22-0168 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所竹田支部 | 878-0013 | 竹田市大字竹田2065-1 | 0974-63-2040 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所中津支部 | 871-0050 | 中津市二ノ丁1260 | 0979-22-2115 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所豊後高田出張所 | 879-0606 | 豊後高田市玉津894 | 0978-22-2061 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所日田支部 | 877-0012 | 日田市淡窓1-1-53 | 0973-23-3145 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所 | 880-8543 | 宮崎市旭2-3-13 | 0985-23-2261 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所日南支部 | 889-2535 | 日南市飫肥3-6-1 | 0987-25-1188 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所都城支部 | 885-0075 | 都城市八幡町2-3 | 0986-23-4131 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所延岡支部 | 882-8585 | 延岡市東本小路121 | 0982-32-3291 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所日向出張所 | 883-0036 | 日向市南町8-7 | 0982-52-2211 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所高千穂出張所 | 882-1101 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井118 | 0982-72-2017 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所 | 892-8501 | 鹿児島市山下町13-47 | 099-222-7121 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所種子島出張所 | 891-3101 | 西之表市西之表16275-12 | 0997-22-0159 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所屋久島出張所 | 891-4205 | 熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18 | 0997-42-0014 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所知覧支部 | 897-0302 | 南九州市知覧郡6196-1 | 0993-83-2229 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所指宿出張所 | 891-0402 | 指宿市十町244 | 0993-22-2902 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所加治木支部 | 899-5214 | 姶良市加治木町仮屋町95 | 0995-62-2666 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所大口出張所 | 895-2511 | 伊佐市大口里2235 | 0995-22-0247 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所川内支部 | 895-0064 | 薩摩川内市花木町2-20 | 0996-22-2154 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所鹿屋支部 | 893-0011 | 鹿屋市打馬1-2-14 | 0994-43-2330 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所名瀬支部 | 894-0033 | 奄美市名瀬矢之脇町1-1 | 0997-52-5141 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所徳之島出張所 | 891-7101 | 大島郡徳之島町亀津554-2 | 0997-83-0019 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所 | 900-8603 | 那覇市桶川1-14-10 | 098-855-1000 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所名護支部 | 905-0011 | 名護市字宮里451-3 | 0980-52-2742 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所沖縄支部 | 904-2194 | 沖縄市知花6-7-7 | 098-939-0017 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所平良支部 | 906-0012 | 宮古島市平良字西里345 | 0980-72-3428 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所石垣支部 | 907-0004 | 石垣市字登野城55 | 0980-82-3812 |
2簡易裁判所の住所電話番号一覧
| 都道府県 | 名称 | 〒 | 住所 | TEL |
| 北海道 | 札幌簡易裁判所 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西12 | 011-221-7281 |
| 北海道 | 浦河簡易裁判所 | 057-0012 | 浦河郡浦河町常盤町19 | 0146-22-4165 |
| 北海道 | 静内簡易裁判所 | 056-0005 | 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10 | 0146-42-0120 |
| 北海道 | 苫小牧簡易裁判所 | 053-0018 | 苫小牧市旭町2-7-12 | 0144-32-3295 |
| 北海道 | 室蘭簡易裁判所 | 050-0081 | 室蘭市日の出町1-18-29 | 0143-44-6733 |
| 北海道 | 伊達簡易裁判所 | 052-0021 | 伊達市末永町47-10 | 0142-23-3236 |
| 北海道 | 岩見沢簡易裁判所 | 068-0004 | 岩見沢市4条東4 | 0126-22-6650 |
| 北海道 | 夕張簡易裁判所 | 068-0411 | 夕張市末広1-92-16 | 0123-52-2004 |
| 北海道 | 滝川簡易裁判所 | 073-0022 | 滝川市大町1-6-13 | 0125-23-2311 |
| 北海道 | 小樽簡易裁判所 | 047-0024 | 小樽市花園5-1-1 | 0134-22-9157 |
| 北海道 | 岩内簡易裁判所 | 045-0013 | 岩内郡岩内町字高台192-1 | 0135-62-0138 |
| 北海道 | 函館簡易裁判所 | 040-8603 | 函館市上新川町1-8 | 0138-42-2151 |
| 北海道 | 松前簡易裁判所 | 049-1501 | 松前郡松前町字建石48 | 0139-42-2122 |
| 北海道 | 八雲簡易裁判所 | 049-3112 | 二海郡八雲町末広町184 | 0137-62-2494 |
| 北海道 | 寿都簡易裁判所 | 048-0401 | 寿都郡寿都町字新栄町209 | 0136-62-2072 |
| 北海道 | 江差簡易裁判所 | 043-0043 | 檜山郡江差町字本町237 | 0139-52-0174 |
| 北海道 | 旭川簡易裁判所 | 070-8642 | 旭川市花咲町4 | 0166-51-6251 |
| 北海道 | 深川簡易裁判所 | 074-0002 | 深川市2条1-4 | 0164-23-2813 |
| 北海道 | 富良野簡易裁判所 | 076-0018 | 富良野市弥生町2-55 | 0167-22-2209 |
| 北海道 | 留萌簡易裁判所 | 077-0037 | 留萌市沖見町2 | 0164-42-0465 |
| 北海道 | 稚内簡易裁判所 | 097-0002 | 稚内市潮見1-3-10 | 0162-33-5289 |
| 北海道 | 天塩簡易裁判所 | 098-3303 | 天塩郡天塩町新栄通7 | 01632-2-1146 |
| 北海道 | 紋別簡易裁判所 | 094-0006 | 紋別市潮見町1-5-48 | 0158-23-2856 |
| 北海道 | 名寄簡易裁判所 | 096-0014 | 名寄市西4条南9 | 01654-3-3331 |
| 北海道 | 中頓別簡易裁判所 | 098-5551 | 枝幸郡中頓別町字中頓別166-5 | 01634-6-1626 |
| 北海道 | 釧路簡易裁判所 | 085-0824 | 釧路市柏木町4-7 | 0154-41-4171 |
| 北海道 | 根室簡易裁判所 | 087-0026 | 根室市敷島町2-3 | 0153-24-1617 |
| 北海道 | 標津簡易裁判所 | 086-1632 | 標津郡標津町北2条西1-1-17 | 0153-82-2046 |
| 北海道 | 帯広簡易裁判所 | 080-0808 | 帯広市東8条南9-1 | 0155-23-5141 |
| 北海道 | 本別簡易裁判所 | 089-3313 | 中川郡本別町柳町4 | 0156-22-2064 |
| 北海道 | 北見簡易裁判所 | 090-0065 | 北見市寿町4-7-36 | 0157-24-8431 |
| 北海道 | 遠軽簡易裁判所 | 099-0403 | 紋別郡遠軽町1条通北2-3-25 | 0158-42-2259 |
| 北海道 | 網走簡易裁判所 | 093-0031 | 網走市台町2-2-1 | 0152-43-4115 |
| 北海道 | 仙台簡易裁判所 | 980-8636 | 仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-6111 |
| 北海道 | 大河原簡易裁判所 | 989-1231 | 柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2101 |
| 北海道 | 古川簡易裁判所 | 989-6161 | 大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1601 |
| 北海道 | 築館簡易裁判所 | 987-2252 | 栗原市築館薬師3-4-14 | 0228-22-3154 |
| 北海道 | 登米簡易裁判所 | 987-0702 | 登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 |
| 北海道 | 石巻簡易裁判所 | 986-0832 | 石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0361 |
| 北海道 | 気仙沼簡易裁判所 | 988-0022 | 気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6659 |
| 青森県 | 青森簡易裁判所 | 030-8524 | 青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
| 青森県 | むつ簡易裁判所 | 035-0073 | むつ市中央1-1-5 | 0175-22-2712 |
| 青森県 | 野辺地簡易裁判所 | 039-3131 | 上北郡野辺地町字野辺地419 | 0175-64-3279 |
| 青森県 | 弘前簡易裁判所 | 036-8356 | 弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-4362 |
| 青森県 | 五所川原簡易裁判所 | 037-0044 | 五所川原市字元町54 | 0173-34-2927 |
| 青森県 | 鰺ヶ沢簡易裁判所 | 038-2754 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町38 | 0173-72-2012 |
| 青森県 | 八戸簡易裁判所 | 039-1166 | 八戸市根城9-13-6 | 0178-22-3164 |
| 青森県 | 十和田簡易裁判所 | 034-0082 | 十和田市西二番町14-8 | 0176-23-2368 |
| 岩手県 | 盛岡簡易裁判所 | 020-8520 | 盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
| 岩手県 | 花巻簡易裁判所 | 025-0075 | 花巻市花城町8-26 | 0198-23-5276 |
| 岩手県 | 二戸簡易裁判所 | 028-6101 | 二戸市福岡字城ノ内4-2 | 0195-23-2591 |
| 岩手県 | 久慈簡易裁判所 | 028-0022 | 久慈市田屋町2-50-5 | 0194-53-4158 |
| 岩手県 | 遠野簡易裁判所 | 028-0515 | 遠野市東舘町2-3 | 0198-62-2840 |
| 岩手県 | 釜石簡易裁判所 | 026-0022 | 釜石市大只越町1-7-5 | 0193-22-1824 |
| 岩手県 | 宮古簡易裁判所 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-30 | 0193-62-2925 |
| 岩手県 | 一関簡易裁判所 | 021-0877 | 一関市城内3-6 | 0191-23-4148 |
| 岩手県 | 大船渡簡易裁判所 | 022-0003 | 大船渡市盛町字宇津野沢9-3 | 0192-26-3630 |
| 岩手県 | 水沢簡易裁判所 | 023-0053 | 奥州市水沢区大手町4-19 | 0197-24-7181 |
| 秋田県 | 秋田簡易裁判所 | 010-8504 | 秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
| 秋田県 | 男鹿簡易裁判所 | 010-0511 | 男鹿市船川港船川字化世沢21 | 0185-23-2923 |
| 秋田県 | 能代簡易裁判所 | 016-0817 | 能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
| 秋田県 | 本荘簡易裁判所 | 015-0872 | 由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
| 秋田県 | 大館簡易裁判所 | 017-0891 | 大館市中城15 | 0186-42-0071 |
| 秋田県 | 鹿角簡易裁判所 | 018-5201 | 鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
| 秋田県 | 大曲簡易裁判所 | 014-0063 | 大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
| 秋田県 | 角館簡易裁判所 | 014-0372 | 仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
| 秋田県 | 横手簡易裁判所 | 013-0013 | 横手市城南町2-1 | 0182-32-4130 |
| 秋田県 | 湯沢簡易裁判所 | 012-0844 | 湯沢市田町2-6-41 | 0183-73-2828 |
| 山形県 | 山形簡易裁判所 | 990-8531 | 山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
| 山形県 | 新庄簡易裁判所 | 996-0022 | 新庄市住吉町4-27 | 0233-22-0265 |
| 山形県 | 米沢簡易裁判所 | 992-0045 | 米沢市中央4-9-15 | 0238-22-2165 |
| 山形県 | 赤湯簡易裁判所 | 999-2211 | 南陽市赤湯316 | 0238-43-2217 |
| 山形県 | 長井簡易裁判所 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-7-20 | 0238-88-2073 |
| 山形県 | 鶴岡簡易裁判所 | 997-0035 | 鶴岡市馬場町5-23 | 0235-23-6666 |
| 山形県 | 酒田簡易裁判所 | 998-0037 | 酒田市日吉町1-5-27 | 0234-23-1234 |
| 福島県 | 福島簡易裁判所 | 960-8512 | 福島市花園町5-38 | 024-534-2156(※) |
| 福島県 | 相馬簡易裁判所 | 976-0042 | 相馬市中村字大手先48-1 | 0244-36-5141 |
| 福島県 | 郡山簡易裁判所 | 963-8566 | 郡山市麓山1-2-26 | 024-932-5681 |
| 福島県 | 白河簡易裁判所 | 961-0074 | 白河市郭内146 | 0248-22-5555 |
| 福島県 | 棚倉簡易裁判所 | 963-6131 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1 | 0247-33-3458 |
| 福島県 | 会津若松簡易裁判所 | 965-8540 | 会津若松市追手町6-6 | 0242-26-5734 |
| 福島県 | 田島簡易裁判所 | 967-0004 | 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3 | 0241-62-0211 |
| 福島県 | いわき簡易裁判所 | 970-8026 | いわき市平字八幡小路41 | 0246-22-1348 |
| 福島県 | 福島富岡簡易裁判所 | 979-1111 | 双葉郡富岡町大字小浜字大膳町113 | 0240-22-3008 |
| 茨城県 | 水戸簡易裁判所 | 310-0062 | 水戸市大町1-1-38 | 029-224-8284 |
| 茨城県 | 笠間簡易裁判所 | 309-1611 | 笠間市笠間1753 | 0296-72-0259 |
| 茨城県 | 常陸太田簡易裁判所 | 313-0014 | 常陸太田市木崎二町2019 | 0294-72-0065 |
| 茨城県 | 日立簡易裁判所 | 317-0073 | 日立市幸町2-10-12 | 0294-21-4441 |
| 茨城県 | 土浦簡易裁判所 | 300-8567 | 土浦市中央1-13-12 | 029-821-4359 |
| 茨城県 | 石岡簡易裁判所 | 315-0013 | 石岡市府中1-6-3 | 0299-22-2374 |
| 茨城県 | 龍ヶ崎簡易裁判所 | 301-0824 | 龍ヶ崎市4918 | 0297-62-0100 |
| 茨城県 | 取手簡易裁判所 | 302-0004 | 取手市取手3-2-20 | 0297-72-0156 |
| 茨城県 | 麻生簡易裁判所 | 311-3832 | 行方市麻生143 | 0299-72-0091 |
| 茨城県 | 下妻簡易裁判所 | 304-0067 | 下妻市下妻乙99 | 0296-43-6781 |
| 茨城県 | 下館簡易裁判所 | 308-0041 | 筑西市乙237-6 | 0296-22-4089 |
| 茨城県 | 古河簡易裁判所 | 306-0011 | 古河市東3-4-20 | 0280-32-0291 |
| 栃木県 | 宇都宮簡易裁判所 | 320-8505 | 宇都宮市小幡1-1-38 | 028-621-2111 |
| 栃木県 | 真岡簡易裁判所 | 321-4305 | 真岡市荒町5117-2 | 0285-82-2076 |
| 栃木県 | 大田原簡易裁判所 | 324-0056 | 大田原市中央2-3-25 | 0287-22-2112 |
| 栃木県 | 栃木簡易裁判所 | 328-0035 | 栃木市旭町16-31 | 0282-23-0225 |
| 栃木県 | 小山簡易裁判所 | 323-0031 | 小山市八幡町1-2-11 | 0285-22-3566 |
| 栃木県 | 足利簡易裁判所 | 326-0057 | 足利市丸山町621 | 0284-41-3118 |
| 群馬県 | 前橋簡易裁判所 | 371-8531 | 前橋市大手町3-1-34 | 027-231-4275 |
| 群馬県 | 伊勢崎簡易裁判所 | 372-0031 | 伊勢崎市今泉町1-1216-1 | 0270-25-0887 |
| 群馬県 | 中之条簡易裁判所 | 377-0424 | 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 | 0279-75-2138 |
| 群馬県 | 沼田簡易裁判所 | 378-0045 | 沼田市材木町甲150 | 0278-22-2709 |
| 群馬県 | 太田簡易裁判所 | 373-8531 | 太田市浜町17-5 | 0276-45-7751 |
| 群馬県 | 館林簡易裁判所 | 374-0029 | 館林市仲町2-36 | 0276-72-3011 |
| 群馬県 | 桐生簡易裁判所 | 376-8531 | 桐生市相生町2-371-5 | 0277-53-2391 |
| 群馬県 | 高崎簡易裁判所 | 370-8531 | 高崎市高松町26-2 | 027-322-3541 |
| 群馬県 | 藤岡簡易裁判所 | 375-0024 | 藤岡市藤岡812-4 | 0274-22-0279 |
| 群馬県 | 群馬富岡簡易裁判所 | 370-2316 | 富岡市富岡1383-1 | 0274-62-2258 |
| 埼玉県 | さいたま簡易裁判所 | 330-0063 | さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-4111 |
| 埼玉県 | 川口簡易裁判所 | 332-0032 | 川口市中青木2-22-5 | 048-252-3770 |
| 埼玉県 | 大宮簡易裁判所 | 330-0803 | さいたま市大宮区高鼻町3-140 | 048-641-4288 |
| 埼玉県 | 久喜簡易裁判所 | 346-0016 | 久喜市東1-15-3 | 0480-21-0157 |
| 埼玉県 | 越谷簡易裁判所 | 343-0023 | 越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0127 |
| 埼玉県 | 川越簡易裁判所 | 350-8531 | 川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3020 |
| 埼玉県 | 所沢簡易裁判所 | 359-0042 | 所沢市並木6-1-4 | 04-2996-1801 |
| 埼玉県 | 飯能簡易裁判所 | 357-0021 | 飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 |
| 埼玉県 | 熊谷簡易裁判所 | 360-0041 | 熊谷市宮町1-68 | 048-500-3123 |
| 埼玉県 | 本庄簡易裁判所 | 367-0031 | 本庄市北堀1394-3 | 0495-22-2514 |
| 埼玉県 | 秩父簡易裁判所 | 368-0035 | 秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
| 千葉県 | 千葉簡易裁判所 | 260-0013 | 千葉市中央区中央4-11-27 | 043-333-5292 |
| 千葉県 | 市川簡易裁判所 | 272-8511 | 市川市鬼高2-20-20 | 047-334-3241 |
| 千葉県 | 佐倉簡易裁判所 | 285-0038 | 佐倉市弥勒町92 | 043-484-1215 |
| 千葉県 | 千葉一宮簡易裁判所 | 299-4397 | 長生郡一宮町一宮2791 | 0475-42-3531 |
| 千葉県 | 松戸簡易裁判所 | 271-8522 | 松戸市岩瀬無番地 | 047-368-5141 |
| 千葉県 | 木更津簡易裁判所 | 292-0832 | 木更津市新田2-5-1 | 0438-22-3774 |
| 千葉県 | 館山簡易裁判所 | 294-0045 | 館山市北条1073 | 0470-22-2273 |
| 千葉県 | 八日市場簡易裁判所 | 289-2144 | 匝瑳市八日市場イ-2760 | 0479-72-1300 |
| 千葉県 | 銚子簡易裁判所 | 288-0817 | 銚子市清川町4-9-4 | 0479-22-1249 |
| 千葉県 | 東金簡易裁判所 | 283-0005 | 東金市田間2354-2 | 0475-52-2331 |
| 千葉県 | 佐原簡易裁判所 | 287-0003 | 香取市佐原イ3375 | 0478-52-3040 |
| 東京都 | 東京簡易裁判所 | 130-8636 | 墨田区錦糸4-16-7 | 03-5819-0267 |
| 東京都 | 八丈島簡易裁判所 | 100-1401 | 八丈島八丈町大賀郷1485-1 | 04996-2-0037 |
| 東京都 | 伊豆大島簡易裁判所 | 100-0101 | 大島町元町字家の上445-10 | 04992-2-1165 |
| 東京都 | 新島簡易裁判所 | 100-0402 | 新島村本村3-2-2 | 04992-5-1210 |
| 東京都 | 立川簡易裁判所 | 190-8572 | 立川市緑町10-4 | 042-845-0281 |
| 東京都 | 八王子簡易裁判所 | 192-8516 | 八王子市明神町4-21-1 | 042-642-7020 |
| 東京都 | 武蔵野簡易裁判所 | 180-0006 | 武蔵野市中町2-4-12 | 0422-52-2692 |
| 東京都 | 青梅簡易裁判所 | 198-0031 | 青梅市師岡町1-1300-1 | 0428-22-2459 |
| 東京都 | 町田簡易裁判所 | 194-0022 | 町田市森野2-28-11 | 042-727-5011 |
| 神奈川県 | 横浜簡易裁判所 | 231-0021 | 横浜市中区日本大通9 | 045-662-6971 |
| 神奈川県 | 神奈川簡易裁判所 | 221-0822 | 横浜市神奈川区西神奈川1-11-1 | 045-321-8045 |
| 神奈川県 | 保土ヶ谷簡易裁判所 | 240-0062 | 横浜市保土ヶ谷区岡沢町239 | 045-331-5991 |
| 神奈川県 | 鎌倉簡易裁判所 | 248-0014 | 鎌倉市由比ガ浜2-23-22 | 0467-22-2202 |
| 神奈川県 | 藤沢簡易裁判所 | 251-0054 | 藤沢市朝日町1-8 | 0466-22-2684 |
| 神奈川県 | 相模原簡易裁判所 | 252-0236 | 相模原市富士見6-10-1 | 042-716-3187 |
| 神奈川県 | 川崎簡易裁判所 | 210-8559 | 川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-233-8174 |
| 神奈川県 | 横須賀簡易裁判所 | 238-8510 | 横須賀市新港町1-9 | 046-823-1907 |
| 神奈川県 | 小田原簡易裁判所 | 250-0012 | 小田原市本町1-7-9 | 0465-40-3187 |
| 神奈川県 | 平塚簡易裁判所 | 254-0045 | 平塚市見附町43-9 | 0463-31-0513 |
| 神奈川県 | 厚木簡易裁判所 | 243-0003 | 厚木市寿町3-5-3 | 046-221-2018 |
| 新潟県 | 新潟簡易裁判所 | 951-8512 | 新潟市中央区学校町通1-1 | 025-222-4131 |
| 新潟県 | 新津簡易裁判所 | 956-0031 | 新潟市秋葉区新津4532-5 | 0250-22-0487 |
| 新潟県 | 三条簡易裁判所 | 955-0047 | 三条市東三条2-2-2 | 0256-32-1758 |
| 新潟県 | 新発田簡易裁判所 | 957-0053 | 新発田市中央町4-3-27 | 0254-24-0121 |
| 新潟県 | 村上簡易裁判所 | 958-0837 | 村上市三之町8-16 | 0254-53-2066 |
| 新潟県 | 佐渡簡易裁判所 | 952-1324 | 佐渡市中原356-2 | 0259-52-3151 |
| 新潟県 | 長岡簡易裁判所 | 940-1151 | 長岡市三和3-9-28 | 0258-35-2141 |
| 新潟県 | 十日町簡易裁判所 | 948-0065 | 十日町市子442 | 025-752-2086 |
| 新潟県 | 柏崎簡易裁判所 | 945-0063 | 柏崎市諏訪町10-37 | 0257-22-2090 |
| 新潟県 | 南魚沼簡易裁判所 | 949-6680 | 南魚沼市六日町1884-子 | 025-772-2450 |
| 新潟県 | 高田簡易裁判所 | 943-0838 | 上越市大手町1-26 | 025-524-5160 |
| 新潟県 | 糸魚川簡易裁判所 | 941-0058 | 糸魚川市寺町2-8-23 | 025-552-0058 |
| 富山県 | 富山簡易裁判所 | 939-8502 | 富山市西田地方町2-9-1 | 076-421-6324(※) |
| 富山県 | 魚津簡易裁判所 | 937-0866 | 魚津市本町1-10-60 | 0765-22-0160 |
| 富山県 | 高岡簡易裁判所 | 933-8546 | 高岡市中川本町10-6 | 0766-22-5151 |
| 富山県 | 砺波簡易裁判所 | 939-1367 | 砺波市広上町8-24 | 0763-32-2118 |
| 石川県 | 金沢簡易裁判所 | 920-8655 | 金沢市丸の内7-1 | 076-262-3221 |
| 石川県 | 小松簡易裁判所 | 923-8541 | 小松市小馬出町11 | 0761-22-8541 |
| 石川県 | 七尾簡易裁判所 | 926-8541 | 七尾市馬出町ハ部1-2 | 0767-52-3135 |
| 石川県 | 輪島簡易裁判所 | 928-8541 | 輪島市河井町15部49-2 | 0768-22-0054 |
| 石川県 | 珠洲簡易裁判所 | 927-1297 | 珠洲市上戸町北方い46-3 | 0768-82-0218 |
| 福井県 | 福井簡易裁判所 | 910-8524 | 福井市春山1-1-1 | 0776-22-5000 |
| 福井県 | 大野簡易裁判所 | 912-8524 | 大野市城町1-5 | 0779-66-2120 |
| 福井県 | 武生簡易裁判所 | 915-8524 | 越前市日野美2-6 | 0778-23-0050 |
| 福井県 | 敦賀簡易裁判所 | 914-8524 | 敦賀市松栄町6-10 | 0770-22-0812 |
| 福井県 | 小浜簡易裁判所 | 917-8524 | 小浜市城内1-1-2 | 0770-52-0003 |
| 山梨県 | 甲府簡易裁判所 | 400-0032 | 甲府市中央1-10-7 | 055-213-2537 |
| 山梨県 | 鰍沢簡易裁判所 | 400-0601 | 南巨摩郡富士川町鰍沢7302 | 0556-22-0040 |
| 山梨県 | 都留簡易裁判所 | 402-0052 | 都留市中央2-1-1 | 0554-43-5626 |
| 山梨県 | 富士吉田簡易裁判所 | 403-0012 | 富士吉田市旭1-1-1 | 0555-22-0573 |
| 長野県 | 長野簡易裁判所 | 380-0846 | 長野市旭町1108 | 026-403-2008 |
| 長野県 | 飯山簡易裁判所 | 389-2253 | 飯山市大字飯山1123 | 0269-62-2125 |
| 長野県 | 上田簡易裁判所 | 386-0023 | 上田市中央西2-3-3 | 0268-40-2201 |
| 長野県 | 佐久簡易裁判所 | 385-0022 | 佐久市岩村田1161 | 0267-67-1538 |
| 長野県 | 松本簡易裁判所 | 390-0873 | 松本市丸の内10-35 | 0263-32-3043 |
| 長野県 | 木曾福島簡易裁判所 | 397-0001 | 木曽郡木曽町福島6205-13 | 0264-22-2021 |
| 長野県 | 大町簡易裁判所 | 398-0002 | 大町市大町4222-1 | 0261-22-0121 |
| 長野県 | 諏訪簡易裁判所 | 392-0004 | 諏訪市諏訪1-24-22 | 0266-52-9211 |
| 長野県 | 岡谷簡易裁判所 | 394-0028 | 岡谷市本町1-9-12 | 0266-22-3195 |
| 長野県 | 飯田簡易裁判所 | 395-0015 | 飯田市江戸町1-21 | 0265-22-0189 |
| 長野県 | 伊那簡易裁判所 | 396-0021 | 伊那市西町4841 | 0265-72-2770 |
| 岐阜県 | 岐阜簡易裁判所 | 500-8710 | 岐阜市美江寺町2-4-1 | 058-262-5121 |
| 岐阜県 | 郡上簡易裁判所 | 501-4213 | 郡上市八幡町殿町63-2 | 0575-65-2265 |
| 岐阜県 | 多治見簡易裁判所 | 507-0023 | 多治見市小田町1-22-1 | 0572-22-0698 |
| 岐阜県 | 中津川簡易裁判所 | 508-0045 | 中津川市かやの木町4-2 | 0573-66-1530 |
| 岐阜県 | 御嵩簡易裁判所 | 505-0116 | 可児郡御嵩町御嵩1177 | 0574-67-3111 |
| 岐阜県 | 大垣簡易裁判所 | 503-0888 | 大垣市丸の内1-22 | 0584-78-6184 |
| 岐阜県 | 高山簡易裁判所 | 506-0009 | 高山市花岡町2-63-3 | 0577-32-1140 |
| 静岡県 | 静岡簡易裁判所 | 420-8633 | 静岡市葵区追手町10-80 | 054-252-6111 |
| 静岡県 | 清水簡易裁判所 | 424-0809 | 静岡市清水区天神1-6-15 | 054-366-0326 |
| 静岡県 | 島田簡易裁判所 | 427-0043 | 島田市中溝4-11-10 | 0547-37-3357 |
| 静岡県 | 沼津簡易裁判所 | 410-8550 | 沼津市御幸町21-1 | 055-931-6022 |
| 静岡県 | 三島簡易裁判所 | 411-0033 | 三島市文教町1-3-1 | 055-986-0405 |
| 静岡県 | 熱海簡易裁判所 | 413-8505 | 熱海市春日町3-14 | 0557-81-2989 |
| 静岡県 | 富士簡易裁判所 | 417-8511 | 富士市中央町2-7-1 | 0545-52-0394 |
| 静岡県 | 下田簡易裁判所 | 415-8520 | 下田市4-7-34 | 0558-22-0161 |
| 静岡県 | 浜松簡易裁判所 | 430-8570 | 浜松市中区中央1-12-5 | 053-453-7155 |
| 静岡県 | 掛川簡易裁判所 | 436-0028 | 掛川市亀の甲2-16-1 | 0537-22-3036 |
| 愛知県 | 名古屋簡易裁判所 | 460-8505 | 名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-203-1611 |
| 愛知県 | 名古屋簡易裁判所民事調停部 | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸1-7-5 | 052-203-3421 |
| 愛知県 | 春日井簡易裁判所 | 486-0915 | 春日井市八幡町1-1 | 0568-31-2262 |
| 愛知県 | 瀬戸簡易裁判所 | 489-0805 | 瀬戸市陶原町5-73 | 0561-82-4815 |
| 愛知県 | 津島簡易裁判所 | 496-0047 | 津島市西柳原町3-11 | 0567-26-2746 |
| 愛知県 | 半田簡易裁判所 | 475-0902 | 半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 |
| 愛知県 | 一宮簡易裁判所 | 491-0842 | 一宮市公園通4-17 | 0586-73-3101 |
| 愛知県 | 犬山簡易裁判所 | 484-0086 | 犬山市松本町2-12 | 0568-61-0390 |
| 愛知県 | 岡崎簡易裁判所 | 444-8554 | 岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-4522 |
| 愛知県 | 安城簡易裁判所 | 446-8526 | 安城市横山町毛賀知24-2 | 0566-76-3461 |
| 愛知県 | 豊田簡易裁判所 | 471-0869 | 豊田市十塚町1-25-1 | 0565-32-0329 |
| 愛知県 | 豊橋簡易裁判所 | 440-0884 | 豊橋市大国町110 | 0532-52-3142 |
| 愛知県 | 新城簡易裁判所 | 441-1387 | 新城市北畑40-2 | 0536-22-0059 |
| 三重県 | 津簡易裁判所 | 514-8526 | 津市中央3-1 | 059-226-4614 |
| 三重県 | 鈴鹿簡易裁判所 | 513-0801 | 鈴鹿市神戸3-25-3 | 059-382-0471 |
| 三重県 | 松阪簡易裁判所 | 515-8525 | 松阪市中央町36-1 | 0598-51-0542 |
| 三重県 | 伊賀簡易裁判所 | 518-0873 | 伊賀市上野丸之内130-1 | 0595-21-0002 |
| 三重県 | 伊勢簡易裁判所 | 516-8533 | 伊勢市岡本1-2-6 | 0596-28-3135 |
| 三重県 | 熊野簡易裁判所 | 519-4396 | 熊野市井戸町784 | 0597-85-2145 |
| 三重県 | 尾鷲簡易裁判所 | 519-3615 | 尾鷲市中央町6-23 | 0597-22-0448 |
| 三重県 | 四日市簡易裁判所 | 510-8526 | 四日市市三栄町1-22 | 059-352-7197 |
| 三重県 | 桑名簡易裁判所 | 511-0032 | 桑名市吉之丸12 | 0594-22-0890 |
| 滋賀県 | 大津簡易裁判所 | 520-0044 | 大津市京町3-1-2 | 077-503-8104 |
| 滋賀県 | 甲賀簡易裁判所 | 528-0005 | 甲賀市水口町水口5675-1 | 0748-62-0132 |
| 滋賀県 | 高島簡易裁判所 | 520-1623 | 高島市今津町住吉1-3-8 | 0740-22-2148 |
| 滋賀県 | 彦根簡易裁判所 | 522-0061 | 彦根市金亀町5-50 | 0749-22-0167 |
| 滋賀県 | 東近江簡易裁判所 | 527-0023 | 東近江市八日市緑町8-16 | 0748-22-0397 |
| 滋賀県 | 長浜簡易裁判所 | 526-0058 | 長浜市南呉服町6-22 | 0749-62-0240 |
| 京都府 | 京都簡易裁判所 | 604-8550 | 京都市中京区菊屋町 | 075-211-4111 |
| 京都府 | 伏見簡易裁判所 | 612-8034 | 京都市伏見区桃山町泰長老 | 075-601-2354 |
| 京都府 | 右京簡易裁判所 | 616-8162 | 京都市右京区太秦蜂岡町29 | 075-861-1220 |
| 京都府 | 向日町簡易裁判所 | 617-0004 | 向日市鶏冠井町西金村5-2 | 075-931-6043 |
| 京都府 | 木津簡易裁判所 | 619-0214 | 木津川市木津南垣外110 | 0774-72-0155 |
| 京都府 | 宇治簡易裁判所 | 611-0021 | 宇治市宇治琵琶33-3 | 0774-21-2394 |
| 京都府 | 園部簡易裁判所 | 622-0004 | 南丹市園部町小桜町30 | 0771-62-0237 |
| 京都府 | 亀岡簡易裁判所 | 621-0805 | 亀岡市安町野々神31-10 | 0771-22-0409 |
| 京都府 | 舞鶴簡易裁判所 | 624-0853 | 舞鶴市字南田辺小字南裏町149 | 0773-75-2332 |
| 京都府 | 宮津簡易裁判所 | 626-0017 | 宮津市字島崎2043-1 | 0772-22-2074 |
| 京都府 | 京丹後簡易裁判所 | 627-0012 | 京丹後市峰山町杉谷288-2 | 0772-62-0201 |
| 京都府 | 福知山簡易裁判所 | 620-0035 | 福知山市字内記9 | 0773-22-2209 |
| 大阪府 | 大阪簡易裁判所 | 530-8523 | 大阪市北区西天満2-1-10 | 06-6363-1281 |
| 大阪府 | 大阪池田簡易裁判所 | 563-0041 | 池田市満寿美町8-7 | 072-751-2049 |
| 大阪府 | 豊中簡易裁判所 | 561-0881 | 豊中市中桜塚3-11-2 | 06-6848-4551 |
| 大阪府 | 吹田簡易裁判所 | 564-0036 | 吹田市寿町1-5-5 | 06-6381-1720 |
| 大阪府 | 茨木簡易裁判所 | 567-0888 | 茨木市駅前4-4-18 | 072-622-2656 |
| 大阪府 | 東大阪簡易裁判所 | 577-8558 | 東大阪市高井田元町2-8-12 | 06-6788-5555 |
| 大阪府 | 枚方簡易裁判所 | 573-8505 | 枚方市大垣内町2-9-37 | 072-845-1261 |
| 大阪府 | 堺簡易裁判所 | 590-8511 | 堺市堺区南瓦町2-28 | 072-223-7001 |
| 大阪府 | 富田林簡易裁判所 | 584-0035 | 富田林市谷川町2-22 | 0721-23-2402 |
| 大阪府 | 羽曳野簡易裁判所 | 583-0857 | 羽曳野市誉田3-15-11 | 072-956-0176 |
| 大阪府 | 岸和田簡易裁判所 | 596-0042 | 岸和田市加守町4-27-2 | 072-441-2400 |
| 大阪府 | 佐野簡易裁判所 | 598-0007 | 泉佐野市上町1-4-5 | 072-462-0676 |
| 兵庫県 | 神戸簡易裁判所 | 650-8565 | 神戸市中央区橘通2-2-1 | 078-341-7521 |
| 兵庫県 | 明石簡易裁判所 | 673-0881 | 明石市天文町2-2-18 | 078-912-3231 |
| 兵庫県 | 伊丹簡易裁判所 | 664-8545 | 伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3071 |
| 兵庫県 | 柏原簡易裁判所 | 669-3309 | 丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 |
| 兵庫県 | 篠山簡易裁判所 | 669-2321 | 篠山市黒岡92 | 079-552-2222 |
| 兵庫県 | 洲本簡易裁判所 | 656-0024 | 洲本市山手1-1-18 | 0799-22-3024 |
| 兵庫県 | 尼崎簡易裁判所 | 661-0026 | 尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 |
| 兵庫県 | 西宮簡易裁判所 | 662-0918 | 西宮市六湛寺町8-9 | 0798-35-9381 |
| 兵庫県 | 姫路簡易裁判所 | 670-0947 | 姫路市北条1-250 | 079-223-2721 |
| 兵庫県 | 加古川簡易裁判所 | 675-0039 | 加古川市加古川町粟津759 | 079-422-2650 |
| 兵庫県 | 社簡易裁判所 | 673-1431 | 加東市社490-2 | 0795-42-0123 |
| 兵庫県 | 龍野簡易裁判所 | 679-4179 | たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 |
| 兵庫県 | 豊岡簡易裁判所 | 668-0042 | 豊岡市京町12-81 | 0796-22-2304 |
| 兵庫県 | 浜坂簡易裁判所 | 669-6701 | 美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
| 奈良県 | 奈良簡易裁判所 | 630-8213 | 奈良市登大路町35 | 0742-26-1271 |
| 奈良県 | 葛城簡易裁判所 | 635-8502 | 大和高田市大字大中101-4 | 0745-53-1012 |
| 奈良県 | 宇陀簡易裁判所 | 633-2170 | 宇陀市大宇陀下茶2126 | 0745-83-0127 |
| 奈良県 | 五條簡易裁判所 | 637-0043 | 五條市新町3-3-1 | 0747-23-0261 |
| 奈良県 | 吉野簡易裁判所 | 638-0821 | 吉野郡大淀町大字下渕350-1 | 0747-52-2490 |
| 和歌山県 | 和歌山簡易裁判所 | 640-8143 | 和歌山市二番丁1 | 073-422-4191 |
| 和歌山県 | 湯浅簡易裁判所 | 643-0004 | 有田郡湯浅町湯浅1794-31 | 0737-62-2473 |
| 和歌山県 | 妙寺簡易裁判所 | 649-7113 | 伊都郡かつらぎ町妙寺111 | 0736-22-0033 |
| 和歌山県 | 橋本簡易裁判所 | 648-0072 | 橋本市東家5-2-4 | 0736-32-0314 |
| 和歌山県 | 御坊簡易裁判所 | 644-0011 | 御坊市湯川町財部515-2 | 0738-22-0006 |
| 和歌山県 | 田辺簡易裁判所 | 646-0033 | 田辺市新屋敷町5 | 0739-22-2801 |
| 和歌山県 | 串本簡易裁判所 | 649-3503 | 東牟婁郡串本町串本1531-1 | 0735-62-0212 |
| 和歌山県 | 新宮簡易裁判所 | 647-0015 | 新宮市千穂3-7-13 | 0735-22-2007 |
| 鳥取県 | 鳥取簡易裁判所 | 680-0011 | 鳥取市東町2-223 | 0857-22-2171 |
| 鳥取県 | 倉吉簡易裁判所 | 682-0824 | 倉吉市仲ノ町734 | 0858-22-2911 |
| 鳥取県 | 米子簡易裁判所 | 683-0826 | 米子市西町62 | 0859-22-2206 |
| 島根県 | 松江簡易裁判所 | 690-8523 | 松江市母衣町68 | 0852-23-1701 |
| 島根県 | 雲南簡易裁判所 | 699-1332 | 雲南市木次町木次980 | 0854-42-0275 |
| 島根県 | 出雲簡易裁判所 | 693-8523 | 出雲市今市町797-2 | 0853-21-2114 |
| 島根県 | 浜田簡易裁判所 | 697-0027 | 浜田市殿町980 | 0855-22-0678 |
| 島根県 | 川本簡易裁判所 | 696-0001 | 邑智郡川本町大字川本340 | 0855-72-0045 |
| 島根県 | 益田簡易裁判所 | 698-0021 | 益田市幸町6-60 | 0856-22-0365 |
| 島根県 | 西郷簡易裁判所 | 685-0015 | 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-1 | 08512-2-0005 |
| 岡山県 | 岡山簡易裁判所 | 700-0807 | 岡山市北区南方1-8-42 | 086-222-6771 |
| 岡山県 | 高梁簡易裁判所 | 716-0013 | 高梁市片原町1 | 0866-22-2051 |
| 岡山県 | 玉野簡易裁判所 | 706-0011 | 玉野市宇野2-2-1 | 0863-21-2908 |
| 岡山県 | 児島簡易裁判所 | 711-0911 | 倉敷市児島小川1-4-14 | 086-473-1400 |
| 岡山県 | 倉敷簡易裁判所 | 710-8558 | 倉敷市幸町3-33 | 086-422-1038 |
| 岡山県 | 玉島簡易裁判所 | 713-8102 | 倉敷市玉島1-2-43 | 086-522-3074 |
| 岡山県 | 笠岡簡易裁判所 | 714-0081 | 笠岡市笠岡1732 | 0865-62-2234 |
| 岡山県 | 新見簡易裁判所 | 718-0011 | 新見市新見1222 | 0867-72-0042 |
| 岡山県 | 津山簡易裁判所 | 708-0051 | 津山市椿高下52 | 0868-22-9326 |
| 岡山県 | 勝山簡易裁判所 | 717-0013 | 真庭市勝山628 | 0867-44-2040 |
| 広島県 | 広島簡易裁判所 | 730-0012 | 広島市中区上八丁堀2-43 | 082-228-0421 |
| 広島県 | 東広島簡易裁判所 | 739-0012 | 東広島市西条朝日町5-23 | 082-422-2279 |
| 広島県 | 可部簡易裁判所 | 731-0221 | 広島市安佐北区可部4-12-24 | 082-812-2205 |
| 広島県 | 大竹簡易裁判所 | 739-0614 | 大竹市白石1-7-6 | 0827-52-2309 |
| 広島県 | 三次簡易裁判所 | 728-0021 | 三次市三次町1725-1 | 0824-63-5141 |
| 広島県 | 庄原簡易裁判所 | 727-0013 | 庄原市西本町1-19-8 | 0824-72-0217 |
| 広島県 | 呉簡易裁判所 | 737-0811 | 呉市西中央4-1-46 | 0823-21-4991 |
| 広島県 | 竹原簡易裁判所 | 725-0021 | 竹原市竹原町3553 | 0846-22-2059 |
| 広島県 | 福山簡易裁判所 | 720-0031 | 福山市三吉町1-7-1 | 084-923-2890 |
| 広島県 | 府中簡易裁判所 | 726-0002 | 府中市鵜飼町542-13 | 0847-45-3268 |
| 広島県 | 尾道簡易裁判所 | 722-0014 | 尾道市新浜1-12-4 | 0848-22-5285 |
| 山口県 | 山口簡易裁判所 | 753-0048 | 山口市駅通1-6-1 | 083-922-1330 |
| 山口県 | 防府簡易裁判所 | 747-0809 | 防府市寿町6-40 | 0835-22-0969 |
| 山口県 | 宇部簡易裁判所 | 755-0033 | 宇部市琴芝町2-2-35 | 0836-21-3197 |
| 山口県 | 船木簡易裁判所 | 757-0216 | 宇部市大字船木183 | 0836-67-0036 |
| 山口県 | 周南簡易裁判所 | 745-0071 | 周南市岐山通り2-5 | 0834-21-2610 |
| 山口県 | 萩簡易裁判所 | 758-0041 | 萩市大字江向469 | 0838-22-0047 |
| 山口県 | 長門簡易裁判所 | 759-4101 | 長門市東深川1342-2 | 0837-22-2708 |
| 山口県 | 岩国簡易裁判所 | 741-0061 | 岩国市錦見1-16-45 | 0827-41-0161 |
| 山口県 | 柳井簡易裁判所 | 742-0021 | 柳井市山根10-20 | 0820-22-0270 |
| 山口県 | 下関簡易裁判所 | 750-0009 | 下関市上田中町8-2-2 | 0832-22-4076 |
| 徳島県 | 徳島簡易裁判所 | 770-8528 | 徳島市徳島町1-5 | 088-603-0111 |
| 徳島県 | 鳴門簡易裁判所 | 772-0017 | 鳴門市撫養町立岩字七枚115 | 088-686-2710 |
| 徳島県 | 吉野川簡易裁判所 | 779-3301 | 吉野川市川島町川島588 | 0883-25-2914 |
| 徳島県 | 阿南簡易裁判所 | 774-0030 | 阿南市富岡町西池田口1-1 | 0884-22-0148 |
| 徳島県 | 牟岐簡易裁判所 | 775-0006 | 海部郡牟岐町大字中村字本村54-2 | 0884-72-0074 |
| 徳島県 | 美馬簡易裁判所 | 779-3610 | 美馬市脇町大字脇町1229-3 | 0883-52-1035 |
| 徳島県 | 徳島池田簡易裁判所 | 778-0002 | 三好市池田町マチ2494-7 | 0883-72-0234 |
| 香川県 | 高松簡易裁判所 | 760-8586 | 高松市丸の内2-27 | 087-851-1848 |
| 香川県 | 土庄簡易裁判所 | 761-4121 | 小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 | 0879-62-0224 |
| 香川県 | 丸亀簡易裁判所 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-4-1 | 0877-23-5113 |
| 香川県 | 善通寺簡易裁判所 | 765-0013 | 善通寺市文京町3-1-1 | 0875-25-3467 |
| 香川県 | 観音寺簡易裁判所 | 768-0060 | 観音寺市観音寺町甲2804-1 | 0875-25-3467 |
| 愛媛県 | 松山簡易裁判所 | 790-8539 | 松山市一番町3-3-8 | 089-903-4374 |
| 愛媛県 | 大洲簡易裁判所 | 795-0012 | 大洲市大洲845 | 0893-24-2038 |
| 愛媛県 | 八幡浜簡易裁判所 | 796-0088 | 八幡浜市1550-6 | 0894-22-0176 |
| 愛媛県 | 今治簡易裁判所 | 794-8508 | 今治市常盤町4-5-3 | 0898-23-0010 |
| 愛媛県 | 西条簡易裁判所 | 793-0023 | 西条市明屋敷165 | 0897-56-0749 |
| 愛媛県 | 新居浜簡易裁判所 | 792-0023 | 新居浜市繁本町2-1 | 0897-32-2743 |
| 愛媛県 | 四国中央簡易裁判所 | 799-0405 | 四国中央市三島中央5-4-28 | 0896-23-2335 |
| 愛媛県 | 宇和島簡易裁判所 | 798-0033 | 宇和島市鶴島町8-16 | 0895-22-0091 |
| 愛媛県 | 愛南簡易裁判所 | 798-4131 | 南宇和郡愛南町城辺甲3827 | 0895-72-0044 |
| 高知県 | 高知簡易裁判所 | 780-8558 | 高知市丸ノ内1-3-5 | 088-822-0340 |
| 高知県 | 安芸簡易裁判所 | 784-0003 | 安芸市久世町9-25 | 0887-35-2065 |
| 高知県 | 須崎簡易裁判所 | 785-0010 | 須崎市鍛冶町2-11 | 0889-42-0046 |
| 高知県 | 中村簡易裁判所 | 787-0028 | 四万十市中村山手通54-1 | 0880-35-3007 |
| 福岡県 | 福岡簡易裁判所 | 810-8653 | 福岡市中央区六本松4-2-4 | 092-781-3141 |
| 福岡県 | 宗像簡易裁判所 | 811-3431 | 宗像市田熊2-3-34 | 0940-36-2024 |
| 福岡県 | 甘木簡易裁判所 | 838-0061 | 朝倉市菩堤寺571 | 0946-22-2113 |
| 福岡県 | 飯塚簡易裁判所 | 820-8506 | 飯塚市新立岩10-29 | 0948-22-1150 |
| 福岡県 | 直方簡易裁判所 | 822-0014 | 直方市丸山町1-4 | 0949-22-0522 |
| 福岡県 | 田川簡易裁判所 | 826-8567 | 田川市千代町1-5 | 0947-42-0163 |
| 福岡県 | 久留米簡易裁判所 | 830-8530 | 久留米市篠山町21 | 0942-32-5387 |
| 福岡県 | うきは簡易裁判所 | 839-1321 | うきは市吉井町343-6 | 0943-75-3271 |
| 福岡県 | 八女簡易裁判所 | 834-0031 | 八女市本町537-4 | 0943-23-4036 |
| 福岡県 | 柳川簡易裁判所 | 832-0045 | 柳川市本町4 | 0944-72-3121 |
| 福岡県 | 大牟田簡易裁判所 | 836-0052 | 大牟田市白金町101 | 0944-53-3503 |
| 福岡県 | 小倉簡易裁判所 | 803-8531 | 北九州市小倉北区金田1-4-1 | 093-561-3431 |
| 福岡県 | 折尾簡易裁判所 | 807-0825 | 北九州市八幡西区折尾4-29-6 | 093-691-0229 |
| 福岡県 | 行橋簡易裁判所 | 824-0001 | 行橋市行事1-8-23 | 0930-22-0035 |
| 佐賀県 | 佐賀簡易裁判所 | 840-0833 | 佐賀市中の小路3-22 | 0952-23-3161 |
| 佐賀県 | 鳥栖簡易裁判所 | 841-0036 | 鳥栖市秋葉町3-28-1 | 0942-82-2212 |
| 佐賀県 | 武雄簡易裁判所 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄5660 | 0954-22-2159 |
| 佐賀県 | 鹿島簡易裁判所 | 849-1311 | 鹿島市大字高津原3575 | 0954-62-2870 |
| 佐賀県 | 伊万里簡易裁判所 | 848-0027 | 伊万里市立花町4107 | 0955-23-3340 |
| 佐賀県 | 唐津簡易裁判所 | 847-0012 | 唐津市大名小路1-1 | 0955-72-2138 |
| 長崎県 | 長崎簡易裁判所 | 850-0033 | 長崎市万才町6-25 | 095-822-6151 |
| 長崎県 | 大村簡易裁判所 | 856-0831 | 大村市東本町287 | 0957-52-3501 |
| 長崎県 | 諫早簡易裁判所 | 854-0071 | 諫早市永昌東町24-12 | 0957-22-0421 |
| 長崎県 | 島原簡易裁判所 | 855-0036 | 島原市城内1-1195-1 | 0957-62-3151 |
| 長崎県 | 五島簡易裁判所 | 853-0001 | 五島市栄町1-7 | 0959-72-3315 |
| 長崎県 | 新上五島簡易裁判所 | 857-4211 | 南松浦郡新上五島町有川郷2276-5 | 0959-42-0044 |
| 長崎県 | 巌原簡易裁判所 | 817-0013 | 対馬市厳原町中村642-1 | 0920-52-0067 |
| 長崎県 | 上県簡易裁判所 | 817-1602 | 対馬市上県町佐須奈甲639-22 | 0920-84-2037 |
| 長崎県 | 佐世保簡易裁判所 | 857-0805 | 佐世保市光月町9-4 | 0956-22-9175 |
| 長崎県 | 平戸簡易裁判所 | 859-5153 | 平戸市戸石川町460 | 0950-22-2004 |
| 長崎県 | 壱岐簡易裁判所 | 811-5133 | 壱岐市郷ノ浦町本村触624-1 | 0920-47-1019 |
| 熊本県 | 熊本簡易裁判所 | 860-8531 | 熊本市中央区京町1-13-11 | 096-325-2121 |
| 熊本県 | 宇城簡易裁判所 | 869-3205 | 宇城市三角町波多438-18 | 0964-52-2149 |
| 熊本県 | 御船簡易裁判所 | 861-3206 | 上益城郡御船町辺田見1250-1 | 096-282-0055 |
| 熊本県 | 阿蘇簡易裁判所 | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2476-1 | 0967-22-0063 |
| 熊本県 | 高森簡易裁判所 | 869-1602 | 阿蘇郡高森町高森1385-6 | 0967-62-0069 |
| 熊本県 | 玉名簡易裁判所 | 865-0051 | 玉名市繁根木54-8 | 0968-72-3037 |
| 熊本県 | 荒尾簡易裁判所 | 864-0041 | 荒尾市荒尾1588 | 0968-63-0164 |
| 熊本県 | 山鹿簡易裁判所 | 861-0501 | 山鹿市山鹿280 | 0968-44-5141 |
| 熊本県 | 八代簡易裁判所 | 866-8585 | 八代市西松江城町1-41 | 0965-32-2175 |
| 熊本県 | 水俣簡易裁判所 | 867-0041 | 水俣市天神町1-1-1 | 0966-62-2307 |
| 熊本県 | 人吉簡易裁判所 | 868-0056 | 人吉市寺町1 | 0966-23-4855 |
| 熊本県 | 天草簡易裁判所 | 863-8585 | 天草市諏訪町16-24 | 0969-23-2004 |
| 熊本県 | 牛深簡易裁判所 | 863-1901 | 天草市牛深町2061-17 | 0969-72-2540 |
| 大分県 | 大分簡易裁判所 | 870-8564 | 大分市荷揚町7-15 | 097-532-7161 |
| 大分県 | 別府簡易裁判所 | 874-0908 | 別府市上田の湯町4-8 | 0977-22-0519 |
| 大分県 | 臼杵簡易裁判所 | 875-0041 | 臼杵市大字臼杵101-2 | 0972-62-2874 |
| 大分県 | 杵築簡易裁判所 | 873-0001 | 杵築市大字杵築1180 | 0978-62-2052 |
| 大分県 | 佐伯簡易裁判所 | 876-0815 | 佐伯市野岡町2-13-2 | 0972-22-0168 |
| 大分県 | 竹田簡易裁判所 | 878-0013 | 竹田市大字竹田2065-1 | 0974-63-2040 |
| 大分県 | 中津簡易裁判所 | 871-0050 | 中津市二ノ丁1260 | 0979-22-2115 |
| 大分県 | 豊後高田簡易裁判所 | 879-0606 | 豊後高田市玉津894 | 0978-22-2061 |
| 大分県 | 日田簡易裁判所 | 877-0012 | 日田市淡窓1-1-53 | 0973-23-3145 |
| 宮崎県 | 宮崎簡易裁判所 | 880-8543 | 宮崎市旭2-3-13 | 0985-23-2261 |
| 宮崎県 | 西都簡易裁判所 | 881-0003 | 西都市大字右松2519-1 | 0983-43-0344 |
| 宮崎県 | 日南簡易裁判所 | 889-2535 | 日南市飫肥3-6-1 | 0987-25-1188 |
| 宮崎県 | 都城簡易裁判所 | 885-0075 | 都城市八幡町2-3 | 0986-23-4131 |
| 宮崎県 | 小林簡易裁判所 | 886-0007 | 小林市大字真方112 | 0984-23-2309 |
| 宮崎県 | 延岡簡易裁判所 | 882-8585 | 延岡市東本小路121 | 0982-32-3291 |
| 宮崎県 | 日向簡易裁判所 | 883-0036 | 日向市南町8-7 | 0982-52-2211 |
| 宮崎県 | 高千穂簡易裁判所 | 882-1101 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井118 | 0982-72-2017 |
| 鹿児島県 | 鹿児島簡易裁判所 | 892-8501 | 鹿児島市山下町13-47 | 099-222-7121 |
| 鹿児島県 | 伊集院簡易裁判所 | 899-2501 | 日置市伊集院町下谷口1543 | 099-272-2538 |
| 鹿児島県 | 種子島簡易裁判所 | 891-3101 | 西之表市西之表16275番地12 | 0997-22-0159 |
| 鹿児島県 | 屋久島簡易裁判所 | 891-4205 | 熊毛郡屋久町宮之浦2445-18 | 0997-42-0014 |
| 鹿児島県 | 知覧簡易裁判所 | 897-0302 | 南九州市知覧町郡6196-1 | 0993-83-2229 |
| 鹿児島県 | 加世田簡易裁判所 | 897-0000 | 南さつま市加世田地頭所町1-3 | 0993-52-2347 |
| 鹿児島県 | 指宿簡易裁判所 | 891-0402 | 指宿市十町244 | 0993-22-2902 |
| 鹿児島県 | 加治木簡易裁判所 | 899-5214 | 姶良市加治木町仮屋町95 | 0995-62-2666 |
| 鹿児島県 | 大口簡易裁判所 | 895-2511 | 伊佐市大口里2235 | 0995-22-0247 |
| 鹿児島県 | 川内簡易裁判所 | 895-0064 | 薩摩川内市花木町2-20 | 0996-22-2154 |
| 鹿児島県 | 出水簡易裁判所 | 899-0201 | 出水市緑町25-6 | 0996-62-0178 |
| 鹿児島県 | 甑島簡易裁判所 | 896-1201 | 薩摩川内市上甑町中甑480-1 | 09969-2-0054 |
| 鹿児島県 | 鹿屋簡易裁判所 | 893-0011 | 鹿屋市打馬1-2-14 | 0994-43-2330 |
| 鹿児島県 | 大隈簡易裁判所 | 899-8102 | 曽於市大隅町岩川6659-9 | 099-482-0006 |
| 鹿児島県 | 名瀬簡易裁判所 | 894-0033 | 奄美市名瀬矢之脇町1-1 | 0997-52-5141 |
| 鹿児島県 | 徳之島簡易裁判所 | 891-7101 | 大島郡徳之島町亀津554-2 | 0997-83-0019 |
| 沖縄県 | 那覇簡易裁判所 | 900-8567 | 那覇市樋川1-14-1 | 098-855-3366 |
| 沖縄県 | 名護簡易裁判所 | 905-0011 | 名護市字宮里451-3 | 0980-52-2642 |
| 沖縄県 | 沖縄簡易裁判所 | 904-2194 | 沖縄市知花6-7-7 | 098-939-0011 |
| 沖縄県 | 沖縄簡易裁判所宣野湾分室 | 901-2214 | 宜野湾市我如古2-37-13 | 098-898-6249 |
| 沖縄県 | 平良簡易裁判所 | 906-0012 | 宮古島市平良字西里345 | 0980-72-3502 |
| 沖縄県 | 石垣簡易裁判所 | 907-0004 | 石垣市字登野城55 | 0980-82-3369 |
親等早見表で親族の範囲
1親族の範囲
①親族は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
一般的に親族というと、親戚より堅苦しい言い方といったものでしょう。
親族になる人については、法律で決められています。
親族人になる人は、次のとおりです。
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
相続人になる人についても、法律で決められています。
親族であっても、相続人にならない人がいます。
親族のうち一定の範囲の人が相続人になるからです。
「親戚」「親類」「家族」は、法律で決められていません。
法律で決められている「親族」より、あいまいな表現です。
親族になる人は、法律で決まっています。
②血族は血縁関係がある人
6親等内の血族は、親族です。
血族とは、血縁関係がある人です。
血縁関係があるとは、生物学上の血縁関係がある人だけではありません。
法律上の血縁関係がある人を含みます。
養子縁組をすると、生物学上の親子関係以外に法律上の親子関係が発生します。
養子縁組は、法律上の血縁関係を作る制度です。
養親と養子は、血族です。
血族は、血縁関係がある人です。
③姻族は血族の配偶者と配偶者の血族
3親等内の姻族は、親族です。
姻族とは、血族の配偶者と配偶者の血族です。
配偶者の血族の配偶者は、姻族ではありません。
配偶者の血族の配偶者は、親族ではありません。
姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。
④親等は親族関係の遠近を表す
6親等内の血族、配偶者と3親等内の姻族は、親族です。
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
1親等、2親等と表現します。
数字が小さいほど、近い関係です。
親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われます。
親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。
2親等早見表で数え方
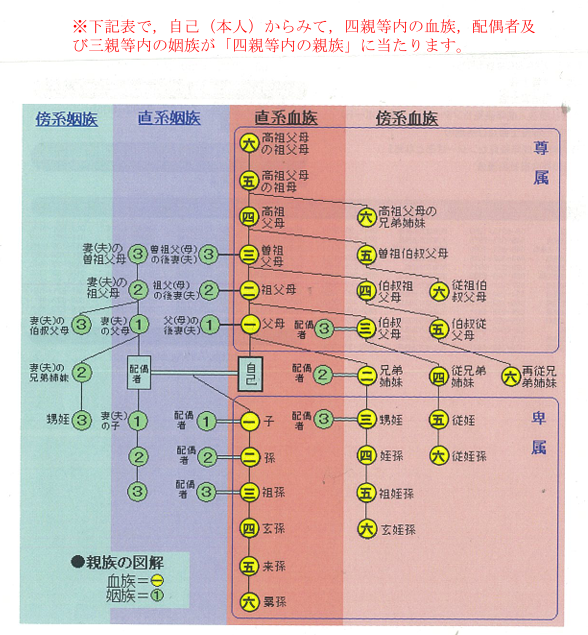
①親子は1親等
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
親子など1世代ちがう関係を1親等と言います。
本人と子どもの関係は、本人→子どもの関係です。
1世代ちがう関係だから、1親等です。
②祖父母と孫は2親等
本人と孫の関係は、本人→子ども→孫の関係です。
2世代ちがう関係だから、2親等です。
本人と祖父母の関係は、本人→親→祖父母の関係です。
2世代ちがう関係だから、2親等です。
③兄弟姉妹は2親等
兄弟の関係は、共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人と兄弟姉妹の関係は、本人→親→兄弟姉妹の関係です。
本人と兄弟姉妹は、2親等です。
④伯叔父母と甥姪は3親等
伯叔父母は、本人の親の兄弟姉妹です。
共通の祖先は、祖父母です。
いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人と伯叔父母は、本人→親→祖父母→伯叔父母の関係です。
本人と伯叔父母は、3親等です。
甥姪は、本人の兄弟姉妹の子どもです。
いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人と甥姪は、本人→親→兄弟姉妹→甥姪の関係です。
本人と甥姪は、3親等です。
⑤いとこは4親等
いとこは、それぞれの親同士が兄弟姉妹です。
共通の祖先は、祖父母です。
いったん、共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人といとこは、本人→親→祖父母→伯叔父母→いとこの関係です。
本人といとこは、4親等です。
⑥親等はどこまでも続く
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
親族のように、法律などで範囲が決められるものではありません。
10代前の先祖は10親等で、100代前の先祖は100親等です。
親等は、どこまでも続きます。
3配偶者は親等がない親族
①配偶者に親等はない
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
本人に、親等はありません。
配偶者にも、親等はありません。
親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われるからです。
②離婚をすると婚姻関係と姻族関係が終了する
離婚をすると、婚姻関係が終了します。
法律上の配偶者でなくなるから、親族でなくなります。
離婚をすると、姻族関係が終了します。
配偶者の血族との親族関係が終了します。
③死別すると姻族関係終了届で親族でなくなる
離婚をすると、婚姻関係が終了します。
配偶者の一方が死亡した場合、婚姻関係が終了します。
配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した場合、希望すれば、復氏をすることができます。
生存配偶者が復氏をしても、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した後も、配偶者の血族と親族のままです。
配偶者が死亡した後、生存配偶者が希望すれば、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。
役所に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。
配偶者が死亡しただけで自動で姻族関係は終了しません。
④事実婚・内縁の配偶者は親族でないし相続人でない
事実婚・内縁の配偶者は、市区町村役場に届出を出していない関係です。
親族になる人は、法律で決められています。
親族になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は親族ではないし相続人ではありません。
4子どもは1親等の親族
①離婚しても子どもは1親等の親族で相続人
親子など1世代ちがう関係は、1親等です。
本人の子どもは、1親等の親族です。
本人が離婚しても、子どもは子どものままです。
離婚して元配偶者が子どもを引き取ることがあります。
離婚すると、元配偶者は除籍されます。
元配偶者が子どもを引き取った場合、自分の戸籍に入れたいと望むことがあるでしょう。
離婚して元配偶者が復氏することがあります。
復氏した後、子どもが元配偶者と同じ氏を名乗ることがあるでしょう。
子どもが未成年である場合、子どもの親権は元配偶者が持つことがあります。
元配偶者が子どもを引き取っても、子どものままです。
子どもが除籍されても、子どものままです。
子どもが別の氏を名乗っていても、子どものままです。
子どもの親権がだれであっても、子どものままです。
子どもと長期間疎遠になっていても、子どものままです。
子どものままだから、子どもは1親等の親族です。
本人が離婚しても、子どもは1親等の親族で相続人です。
②認知した子どもは1親等の親族で相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の親子関係が発生します。
認知された子どもは、本人の子どもです。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出した場合、子どもになります。
市区町村役場に認知届を提出していない場合、生物学上の親子であっても法律上の親子ではありません。
認知した子どもは、1親等の親族で相続人です。
③養子は子どもは1親等の親族で相続人
養子縁組をすると、血縁関係がある親子関係以外に法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になります。
本人が養親となる養子縁組をした場合、養子は子どもです。
養子は、本人の子どもです。
養子は、1親等の親族で相続人です。
④養子に行っても普通養子なら子どもは1親等の親族で相続人
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どもがいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは日常的に聞くことがあるでしょう。
一般的に「養子」と言ったら、普通養子を指しています。
普通養子では、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。
本人の実子が第三者の普通養子となる養子縁組をすることがあります。
第三者の普通養子になっても、実親との親子関係は継続します。
養子に行っても、実子のままです。
第三者の養子になる養子縁組をしても、子どものままです。
普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続するからです。
養子に行っても、実親から見て1親等の親族で相続人です。
養子は、養親の子どもです。
養子に行ったら、養親から見て1親等の親族で相続人です。
養子は、実親にとっても養親にとっても1親等の親族で相続人です。
⑤配偶者の連れ子は1親等の親族だが相続人ではない
3親等内の姻族は、親族です。
配偶者の連れ子は、配偶者の血族です。
配偶者の連れ子は、1親等の姻族だから親族です。
配偶者の連れ子は、本人の子どもではありません。
親族であっても子どもではないから、相続人にはなりません。
配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは、日常的に聞くことがあるでしょう。
配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。
養子は、1親等の血族です。
養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になるからです。
本人の子どもは、相続人になります。
配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。
配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。
⑥子どもが特別養子になると親子関係終了
養子縁組には、普通養子縁組の他に特別養子縁組があります。
特別養子では、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。
特別養子縁組の成立は、親子の縁を切る重大な決定です。
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判が必要です。
特別養子縁組では、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために必要な場合、特別養子縁組の審判がされます。
親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は非常に慎重に判断します。
子どもが特別養子になると、親子関係が終了します。
親子関係が終了するから、子どもは実親の親族ではないし実親の相続人ではありません。
5兄弟姉妹は2親等の親族
①異父兄弟・異母兄弟は2親等の親族で相続人
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。
親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹であっても、同様です。
異父兄弟・異母兄弟は、2親等の親族で相続人です。
②夫婦の連れ子同士に親等はないし相続人ではない
配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。
配偶者の連れ子は、親族です。
夫婦のそれぞれに連れ子がいることがあります。
連れ子から見ると、本人の親の配偶者に連れ子がいるケースです。
夫婦の連れ子同士は、親族ではありません。
連れ子同士は血縁関係がないから、血族ではありません。
姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。
連れ子同士は、姻族ではありません。
配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。
連れ子と実子は、兄弟姉妹です。
親の子どもになるからです。
親が配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、2親等の血族で相続人です。
6相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続財産は時効取得ができない
1取得時効には要件がある
相続登記をしないまま、先延ばしをしている例はたくさんあります。
相続手続は済んでいると思い込んだまま、放置して持ち主が死亡することもあります。
自分のものだと信じて使い続けた自宅なのに、登記を調べてみたら、祖父の名義のままだったという話も多々聞くことです。
他人のものでも自分のものと信じてずっと使い続ければ、自分のものになるはずと思う人も多いでしょう。
時効取得が認められた場合、他人のものでも自分のものになります。
自分のものだと信じて使い続けた自宅だから、時効取得できると考えるかもしれません。
時効取得するためには、要件があります。
要件を満たせば、時効取得することができます。
2時効取得するための要件
①所有の意思がある
単に、自分のために使っている、自分のために持っているだけでは不足です。
所有する意思をもって使っている、持っている必要があります。
借りているものを使っていても、所有する意思は認められません。
長期間借り続けていても、時効取得することはできません。
所有の意思は、使っている人が心の中で思っていることで決まるものではありません。
使うことの原因になった理由や持っている事情によって、外形的に客観的に決まります。
通常、売買の買主は所有する意思を持っています。
泥棒にも、所有の意思があります。
外形的に客観的に、自分のために使っている、自分のために持っているからです。
買ったものがだれのものでも、時効取得ができる可能性があります。
泥棒が盗んだものでも、時効取得ができる可能性があります。
他にも相続人がいることを知りながら使い続けている場合、所有の意思は認められません。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産を使い続けている場合、他の相続人のために管理していると考えられるからです。
他の相続人のために管理していても、所有の意思は認められません。
②公然かつ平穏
公然とは、こっそり使っていたり、隠し持っている場合でないという意味です。
平穏とは、暴行や脅迫によって、持っていたり、使っている場合ではないという意味です。
使っている場合や持っている場合、公然かつ平穏であると推定されます。
③他人の物
法律には、わざわざ「他人の物」と明示してあります。
他人の物と言っていますが、自分のものも含めて考えます。
他人の物でも、時効取得できます。
自分のものを時効取得できるのは、なおさらのことです。
時効制度は長い間、続いてきた平穏な事実を権利として認めようという制度です。
自分のものであっても、長い間に自分のものであるという証拠がなくなることがあります。
だれが所有者なのか分からないと、トラブルになることがあるでしょう。
長い間、平穏に使い続けた事実を権利として認めることで、救済しようとするものだからです。
④善意無過失
善意とは、自分のものと信じていたという意味です。
無過失とは、自分のものと信じていたことについて、落ち度がなかったという意味です。
自分のものと信じており、自分のものと信じることについて落ち度がない場合、10年で時効取得ができます。
自分のものと信じており、自分のものと信じることについて落ち度がないのは、最初の時点で判断します。
最初の時点で、自分のものと信じており、自分のものと信じることについて落ち度がなければ、10年で時効取得ができます。
途中で、自分のものでないのかもと疑うような事実を知ってしまっても、10年で時効取得ができます。
最初の時点で、他人のものと知っていたり、自分のものと信じることに落ち度がある場合でも、20年で時効取得ができます。
⑤時効を援用すること
時効が完成したら、所有者に「時効取得しました」と主張する必要があります。
3相続財産は時効取得ができない
①相続財産は相続人全員の共有財産
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意がまとまるまで、相続人全員の共有財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
②相続財産に所有の意思は認められない
時効取得の要件をすべて満たしたら、時効取得をすることができます。
重要なポイントは、所有の意思があることです。
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産である実家に、一部の相続人が住み続けていることがあります。
相続財産である実家は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の財産を、使っているに過ぎません。
借りているものを使っているのと同様に、所有の意思は認められません。
使うことの原因になった理由や持っている事情によって、外形的に客観的に決まります。
所有の意思は、使っている人が心の中で思っていることで決まるものではありません。
相続財産は、客観的に外形的に相続人全員の共有財産です。
相続財産を使い続けても、所有の意思が認められません。
③所有の意思が認められないと時効取得はできない
時効取得の制度は、長い間、平穏に使い続けた事実を権利として認める制度です。
客観的に外形的に、所有の意思をもって使い続けることが重要です。
代々伝わる実家だからなどの理由は、所有の意思と無関係です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の共有財産を使い続けても、所有の意思は認めれません。
所有の意思が認められないと、時効取得はできません。
④遺産分割協議が成立した後は所有の意思がある
相続財産の分け方は、相続人全員で合意で決める必要があります。
合意をせず実家を使い続けただけで、時効取得はできません。
父に相続が発生して登記簿を確認したところ、祖父の名義のままということがあります。
父が実家を使い続けただけで、時効取得をすることはできません。
祖父の相続のとき、相続人が遺産分割協議をしたでしょう。
遺産分割協議に基づいて、相続手続をしているでしょう。
すべての相続財産について手続をしているのに、実家だけ相続登記を忘れてしまうことがあります。
父が相続することについて、祖父の相続人全員が合意をしていたでしょう。
多くの場合、実家などの不動産は家族にとって重要な財産です。
祖父の相続人全員が合意をしなかったと考えるのは、不自然でしょう。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意があれば、口頭の合意でも有効です。
遺産分割協議が成立した後は、相続した人の財産です。
所有する意思をもって使っていると認められます。
長期間所有の意思をもって使っている場合、時効取得をすることができます。
4時効取得しても登記手続は必要
①~⑤の要件を満たして、時効取得したら所有権を得ることができます。
不動産を時効取得した場合、所有権の移転登記が必要になります。
所有権を時効取得しても、自動で登記されることはありません。
法務局は、時効取得したことが分からないからです。
時効取得による所有権移転登記を申請する場合、登記名義人と時効取得した所有者が協力して申請する必要があります。
登記名義人が死亡している場合、登記名義人の相続人全員の協力が必要です。
時効取得されて不動産の所有権を失う元所有者や元所有者の相続人が登記手続に協力してくれることは、まず考えられません。
登記手続に協力が得られない場合、裁判所に訴えを起こすことになります。
裁判所から、所有権移転登記手続をせよという判決を出してもらう必要があります。
所有権移転登記をせよという判決があれば、時効取得した所有者が単独で登記申請をすることができます。
5時効取得の登記はすみやかに
要件を満たせば、時効取得をすることができます。
時効取得で所有権を失う元所有者は、登記申請に協力してくれないことがほとんどです。
協力してくれないからと言って、登記申請をせずに先延ばしをすることはおすすめできません。
せっかく時効取得した権利を失ってしまうかもしれないからです。
時効取得をした後、所有権移転登記をしない間の登記名義人は、元所有者です。
登記名義があるから、元所有者は不動産を売買などで譲渡することができます。
元所有者から不動産を譲り受けた人は、すぐに所有権移転登記をするでしょう。
権利主張をするためには、登記が必要です。
時効取得したから自分のものだと主張するためには、登記をしておく必要があります。
登記申請は、時効取得する人と不動産を譲り受けた人の競争です。
登記申請は、早い者勝ちだからです。
不動産を譲り受けた人が先に登記をしたら、時効取得した人は権利主張をすることができません。
不動産は、譲り受けた人のものになります。
時効取得をしたら、すみやかに登記手続をすることが重要です。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
不動産を相続した場合、すぐに売却したいといった事情がなければ先延ばししがちです。
先延ばししているうちに、相続登記を忘れてしまいます。
相続登記したものと思い込んでしまうことが多くなります。
実際のところ、何代も前の名義のまま放置されている例はよく見かけます。
何十年も住み続けた自宅なのに、自分のものでないを知るとショックを受けます。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
何十年も住み続けたから、自分のものだと主張したくなるでしょう。
何十年も住み続けた自宅であっても、相続人全員の合意は欠かせません。
長い間経過していると、相続人が死亡することがあります。
相続人の相続人と話し合いが必要になるかもしれません。
関係が薄い相続人かいると、疎遠になっているでしょう。
疎遠な相続人がいると、分け方の合意は難しくなりがちです。
時効取得を持ち出してくること自体、トラブルは始まっています。
日常会話の中で、時効という言葉は軽く使われがちです。
法律上の時効は、考えるよりハードルが高く、認められるのが難しいものです。
きちんと相続登記をしておけば、家族のトラブルにならないことがほとんどでしょう。
相続が発生した後、すみやかに相続登記を済ませましょう。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続手続は司法書士に依頼できる
1相続手続は司法書士に依頼できる
①相続人調査は司法書士に依頼できる
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続が発生した場合、たくさんの相続手続をすることになります。
相続手続の最初の難関は、相続人調査です。
家族にとってだれが相続人になるか当然のことでしょう。
相続手続先に対しては、客観的に証明しなければなりません。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明することです。
戸籍には、その人に身分事項がすべて記載されているからです。
相続人を客観的に証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意しなければなりません。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
遠方の市区町村役場に郵送で戸籍謄本を請求するのは、手間がかかります。
古い戸籍は、活字ではなく手書きで記載されています。
現在と書き方ルールがちがううえに手書きで記載されているから、戸籍謄本の解読は骨が折れる作業です。
手間と時間がかかる相続人調査は、司法書士に依頼することができます。
②相続財産調査は司法書士に依頼できる
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人は、いろいろな財産を持っていたでしょう。
相続財産は、プラスの財産だけではありません。
マイナスの財産も、相続財産になります。
相続人と被相続人が別居していた場合、被相続人の財産状況を詳しく知っていることはあまりないでしょう。
預貯金は、通帳やキャッシュカード、金融機関などからの通知を探します。
手がかりが見つかったら、金融機関に口座の有無を照会します。
不動産は、権利書や固定資産税の領収書を探します。
手がかりが見つかったら、市区町村役場に名寄帳を請求します。
機密性の高い個人情報であることを考慮して、名古屋市など名寄帳を発行していない市区町村役場もあります。
名古屋市では、課税明細書と資産明細書で代用します。
株式は、証券会社や信託銀行からのお手紙や株主総会招集通知や配当通知を探します。
手がかりが見つかったら、金融機関に連絡をして残高証明書を請求します。
証券保管振替機構に対して登録済加入者情報の開示請求をして調べることもできます。
借金は、契約書、借入明細書や督促状を探します。
手がかりが見つかったら、貸主に連絡をして残高証明書を請求します。
信用情報機関に照会すると詳しく確認することができます。
(1)消費者金融からのお借入 日本信用情報機構(JICC)
(2)クレジット会社からのお借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(3)銀行からのお借入 全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
相続財産は、財産ごとに別々の期間に照会して調べていきます。
照会しても、すぐに返事はもらえないことが少なくありません。
根気良く手続をするのは、気が遠くなる作業です。
手間と時間がかかる相続財産調査は、司法書士に依頼することができます。
③相続放棄は司法書士に依頼できる
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産である場合、そのまま相続すると相続人の人生が破綻します。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄のチャンスは、1回限りです。
相続放棄の手続は、司法書士に依頼することができます。
④遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼できる
相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産は、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決定します。
相続人全員の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
相続財産の分け方について、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面が遺産分割協議書です。
相続人全員の合意ができたら、相続手続を進めます。
遺産分割協議書は、相続手続のため相続手続先の人にも分かるように記載することが大切です。
遺産分割協議書の記載が不適切である場合、相続手続を進めることができません。
相続手続をスムーズに進めるため、遺産分割協議書作成は、司法書士に依頼することができます。
⑤相続登記は司法書士に依頼できる
相続財産に不動産が含まれることがあります。
不動産の名義変更が相続登記です。
不動産は重要な財産であることが多いから、相続登記は厳格に審査されます。
一般的に言って、相続登記は手間のかかる難しい手続です。
些細なミスであれば、やり直しをすることで相続登記を通してもらえます。
重大なミスであればやり直しは認められず、いったん取下げて再提出になります。
一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
手間のかかる難しい相続登記は、司法書士に依頼することができます。
2裁判所の書類作成は司法書士に依頼できる
①遺言書の検認は司法書士に依頼できる
被相続人が遺言書を作成していることがあります。
公正証書遺言か自筆証書遺言のいずれかを作成される人がほとんどです。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。
公正証書遺言は、検認を受ける必要はありません。
検認とは、家庭裁判所で遺言書を点検してもらうことです。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。
自筆証書遺言は、手軽です。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局保管の自筆証書遺言は、検認を受ける必要はありません。
法務局保管でない自筆証書遺言は、検認を受ける必要はあります。
法務局保管でない自筆証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に対して自筆証書遺言検認の申立てをします。
遺言書の検認の書類作成は、司法書士に依頼することができます。
②成年後見人選任の申立ては司法書士に依頼できる
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決定します。
相続人の中に認知症の人がいることがあります。
認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。
認知症の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。
認知症の人が遺産分割協議書に記名し押印しても、無効の書類です。
認知症の人は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないから、サポートする人をつける必要があります。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
成年後見人は、認知症の人の代わりに相続財産の分け方の話し合いをします。
成年後見人は、認知症の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
認知症の人や家族は、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てをすることができます。
成年後見人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。
③不在者財産管理人選任の申立ては司法書士に依頼できる
相続財産の分け方を決定するためには、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続人の中に行方不明の人がいることがあります。
行方不明の人は、自分で話し合いをすることができません。
行方不明の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。
行方不明の人は自分で話し合いをすることができないから、代わりの人が話し合いに参加します。
不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりの人です。
不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
行方不明の人の家族は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
不在者財産管理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。
④特別代理人選任の申立ては司法書士に依頼できる
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。
未成年者が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。
未成年者が相続人になる場合、親などの親権者も相続人になっているでしょう。
未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、親などの親権者は子どもを代理することはできません。
未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクをすると他方がソンをする関係です。
親がトクをすると子どもがソンをするから、親などの親権者は子どもを代理することはできません。
親などの親権者が子どもを代理することができない場合、代わりの人が話し合いに参加します。
特別代理人は、未成年者の代わりの人です。
特別代理人は未成年者の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。
特別代理人は、家庭裁判所が選任します。
未成年者の家族は、家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをすることができます。
特別代理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。
3相続手続で司法書士に依頼できないこと
①相続人間に争いがあるときは弁護士
相続手続で司法書士に依頼できることはたくさんあります。
相続手続の過程で紛争に発展した場合、司法書士に依頼することができません。
紛争に発展した場合、代理人となることができるのは弁護士だけです。
司法書士は、相続人に代わって交渉をすることができません。
司法書士は、遺産分割調停の代理人になることもできません。
②相続税申告は税理士
被相続人が資産家である場合、相続税申告が必要になることがあります。
相続材申告が必要になるのは、10%未満の富裕層です。
相続税申告は、司法書士に依頼することはできません。
税務申告の代理は、税理士の業務範囲です。
4相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。
大きい悲しみのなかで、相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。
負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。
その後の相続手続がスムーズになります。
被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。
悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。
相続財産調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。
戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。
財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
死亡届は提出前にコピー
1死亡届は返却されない
①人が死亡したら死亡届
死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。
人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。
死亡届を提出する場合、死亡診断書(死体検案書)が必要になります。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、1枚の用紙に印刷されています。
左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。
死亡届は、届出人が記載します。
死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。
死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書です。
死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したときに作成されます。
死体検案書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したとき以外に作成されます。
死亡診断書と死体検案書の効力に、ちがいはありません。
死亡届を提出すると、戸籍に死亡が記録され住民登録が抹消されます。
②死亡届の提出先
死亡届の提出先は、次の市区町村役場です。
(1)死亡した人の本籍地
(2)届出人の住所地
(3)死亡地
③死亡届の提出期限
死亡届の提出には、提出期限があります。
死亡の事実を知ってから、7日以内です。
国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
④死亡届の届出人
死亡届の届出人は、次のとおりです。
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。
次の人は、届出をすることができます。
(1)同居の親族以外の親族
(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人
(3)任意後見受任者
死亡届の届出義務は、ありません。
⑤届出人が記入した後に使者が市役所に提出できる
死亡届は、届出人が記載します。
死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。
届出人と医師が記入したら、死亡届はできあがりです。
できあがった死亡届は、だれが市区町村役場に持って行っても構いません。
市区町村役場に持って行く人は、届出人ではなく使者だからです。
葬儀業者の人が使者として市区町村役場に持って行っても差し支えありません。
⑥死亡届提出後に埋火葬許可証
死亡届の提出と一緒に、埋火葬許可証の発行申請をします。
埋火葬許可証とは、死亡した人を埋火葬する許可を証明する書類です。
死亡してから24時間経過した後、火葬します。
埋火葬許可証がないと、火葬を執行することができません。
火葬を執行すると、埋火葬許可証に執行済のスタンプが押されます。
執行済の埋火葬許可証は、納骨のときにも必要になります。
無くさないように大切に保管しましょう。
2死亡届は提出前にコピー
①死亡届のコピーが必要になるケース
死亡届は、提出先の市区町村役場の窓口に提出します。
書類に問題がなければ、受理されます。
受理された後、死亡届は返却されません。
死亡届を提出する前に、コピーを取っておきましょう。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、セットになっています。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)のコピーが必要になるからです。
例えば、次の手続で必要になります。
(1)健康保険の喪失
(2)雇用保険の喪失
(3)労災保険の請求
(4)生命保険の請求
(5)自動車保険・損害保険の手続
(6)携帯電話の解約
(7)国民年金・厚生年金・共済年金の受給
(8)埋葬料・葬祭費の請求
(9)自動車などの名義変更
(10)公共料金の名義変更
上記を参考にして、多めにコピーを取っておきましょう。
②死亡届のコピーをとるタイミング
死亡が確認されたら、医師が死亡診断書(死体検案書)を作成します。
死亡日当日に死亡診断書(死体検案書)が渡されます。
届出人が死亡届を作成します。
死亡届を市区町村役場に提出するのは、死亡日当日か翌日でしょう。
死亡届を提出する場合、一緒に埋火葬許可証の発行申請をします。
火葬するためには、埋火葬許可証が必要です。
火葬場を予約するため、死亡届の提出が最優先になります。
少なくとも死亡日の翌日までに死亡届のコピーを取っておくのがおすすめです。
家族が死亡すると、親戚や知人への連絡で忙しくなります。
死亡届の提出期限は、7日以内です。
火葬することを考えると、余裕はありません。
葬儀業者の人が市区町村役場に提出をしてもらう場合、コピーも一緒に依頼するといいでしょう。
③死亡届のコピーでできない手続がある
生命保険会社や保険商品によっては、死亡届のコピーでは手続ができません。
高額な保険金の請求は、保険会社専用の死亡診断書が必要になるでしょう。
担当の医師に作成してもらえるように、依頼しましょう。
医師に死亡診断書を作成してもらう場合、1か月程度かかることがあります。
3コピーを忘れたら死亡届記載事項証明書を請求
①死亡届記載事項証明書を請求できる人
市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。
死亡届のコピーを忘れた場合、死亡届記載事項証明書を発行してもらうことができます。
死亡届記載事項証明書を請求できるのは、利害関係がある人で、かつ、特別な理由がある場合だけです。
死亡届記載事項証明書を請求できる人は、次のとおりです。
(1)配偶者
(2)6親等内の親族
(3)3親等内の姻族
単に、財産上の利害関係があるだけの人は、死亡届記載事項証明書を請求することはできません。
②死亡届記載事項証明書を請求のため特別な理由が必要
上記の人であっても特別な理由がない場合、死亡届記載事項証明書を請求できません。
例えば、特別な理由には次の理由があります。
(1)簡易生命保険の保険受取人であるため、郵便局に提出する
(2)遺族年金の受取人であるため、市町村役場、日本年金機構、共済組合、労働基準監督署に提出する
(3)婚姻や離婚の無効の裁判の申立てのため、家庭裁判所に提出する
(4)戸籍の記載事項の訂正許可の裁判の申立てのため、家庭裁判所に提出する
(5)帰化申請の許可の申立てのため、法務局に提出する
(6)外国人との婚姻を本国政府に報告するため、大使館、領事館に提出する
(7)日本で出生した子どもについて本国にパスポート申請のため、大使館、領事館に提出する
(8)日本で出生した子どもについて本国にパスポート申請の前提として出生登録のため、大使館、領事館に提出する
企業年金の受取人であることは、特別な事由にあたりません。
③死亡届記載事項証明書の請求先
死亡届記載事項証明書の請求先は、市区町村役場か法務局のいずれかです。
死亡届は、死亡者の本籍地の市区町村役場に提出することができます。
死亡者の本籍地の市区町村役場は、1か月間その市区町村役場で保管します。
死亡届は、届出人の住所地や死亡地の市区町村役場に提出されることがあります。
死亡者の本籍地以外の市区町村役場は、1年間その市区町村役場で保管します。
市区町村役場で保管中であれば、死亡届を保管している市区町村役場に請求します。
市区町村役場の保管期間が経過した場合、法務局で保管されます。
法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。
法務局で保管中であれば、死亡届を保管している法務局に請求します。
④死亡届記載事項証明書請求の必要書類
死亡届記載事項証明書請求の必要書類は、次のとおりです。
(1)請求者の本人確認書類
(2)利害関係人であることが分かる戸籍謄本
(3)特別な事由があることが分かる書類
(4)委任状(代理人が請求する場合)
⑤死亡届記載事項証明書の発行手数料
市区町村役場に請求する場合、死亡届記載事項証明書の発行手数料が必要です。
法務局に請求する場合、死亡届記載事項証明書の発行手数料がかかりません。
⑥死亡届記載事項証明書は郵送請求ができる
死亡届記載事項証明書を請求する場合、窓口まで出向いて請求することもできるし、郵送で請求することもできます。
郵送請求をする場合、返信用の切手と封筒を同封しておくと、証明書を送り返してもらうことができます。
4コピーを忘れたら死亡診断書や埋火葬許可証で
市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。
死亡届は、原則として、非公開です。
死亡届記載事項証明書を請求できる人は、限られています。
死亡届記載事項証明書を請求できる人であっても特別な理由が認められない場合、発行してもらえません。
死亡届のコピーを忘れた場合、別の書類を提出することができるかもしれません。
手続先に問い合わせてみましょう。
多くの手続先は、死亡の確認がしたいだけでしょう。
死亡の事実を確認する方法は、複数あります。
医師に依頼して、死亡診断書を作成してもらうことができます。
埋火葬許可証や埋火葬許可証発行済証明書を用意できるでしょう。
死亡の記載がある住民票や戸籍謄本を取得できます。
死亡届のコピーを忘れても、手続ができなくなることはありません。
5遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット
家族が死亡した場合、いちばん最初に行う手続が死亡届の提出です。
ここから、たくさんの相続手続が始まります。
多くの場合、大切な家族を失ったら大きな悲しみに包まれます。
悲しみに包まれていても、日常の家事や仕事をする必要があります。
そのうえ、たくさんの用事と相続手続が押し寄せてきます。
相続は一生の間に何回も経験するものではありません。
相続手続で使われる言葉の多くは法律用語です。
聞き慣れない言葉があふれています。
ほとんどの人にとって、相続手続は不慣れなものです。
大切な家族を亡くして、力を落としているでしょう。
相続手続をするのは、大きな負担になります。
事例によっては、家庭裁判所の助力が必要になる場合があります。
専門家のサポートがないと難しい手続があります。
司法書士は家庭裁判所に提出する書類作成の専門家です。
相続手続を丸ごと依頼することができます。
確実に相続手続をしたい方は司法書士などの専門家に遺産整理業務を依頼することをおすすめします。
尊厳死宣言公正証書で延命治療拒否の意思表示
1尊厳死と安楽死のちがい
高齢化社会が到来して、多くの方は長生きになりました。
現代の医学の発展により、身体状況を管理して、少なからぬ期間の生命維持ができるようになりました。
このような延命治療は苦痛を伴うことが多いです。
大きな苦痛を伴いながら、回復の見込みのない状態で治療を受け続けることは、人間としての尊厳を保てないとも考えられます。
不知の病で回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命治療を避け尊厳を持って自然な死を受け入れることを望む人が増えています。
回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎えることを、尊厳死と言います。
本人の自己決定権を尊重すべきという考えの人は、尊厳死を認める考えになりやすいです。
延命治療をしないことは、医療の放棄であるという考えの人は、尊厳死を認めない考えになりやすいです。
どちらも正しく、どちらも間違いではありません。
法律上は、尊厳死を認めると直接定めたものはありません。
日本医師会や学会などは、尊厳死を認める意見です。
苦痛から解放されるために、医師などが薬物などを積極的に使って死を迎える安楽死とは別物です。
尊厳死は、過度な治療を行わないことで、自然な死を迎えるものです。
2尊厳死宣言書を公正証書にするメリット
尊厳死宣言とは、回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎える意思を示した文書です。
尊厳を持って自然な死を迎える意思を持っていたとしても、医師や家族に伝えていないと意思はかなえられません。
自力で意思表示ができなくなってからでは、尊厳死の希望はかなえられないのです。
法律上は、尊厳死を認めると直接定めたものはありません。
公正証書でなければならないといったルールがあるわけではありません。
公正証書は、公証人に尊厳死を希望していることを伝えて、公証人が作る公的な書類です。
公証人は、身分証明書などで本人確認をしたうえで、本人の意思を確認して、公正証書を作ります。
本人は尊厳死を希望していなかったのではないかなどとトラブルになることがありません。
尊厳死宣言書原本は、公証役場で保管されます。
尊厳死宣言書が偽造ではないかなどといったトラブルとも無縁です。
公証人の作る公正証書は、極めて信頼性が高いものとされています。
公正証書でない尊厳死宣言書の場合、本人の意思であるのかはっきりしていないという疑いが残ります。
本人の意思であるのかはっきりしていないと、医師は慎重な判断をすることになるでしょう。
何より、公正証書にすることは本人の強い意志を感じさせます。
医師は本人の意思であると信頼するからこそ、尊厳死を実現させてくれます。
実際、95%以上の医師が尊厳死宣言の提出があったら、本人の意思を尊重すると答えています。
尊厳死宣言書に強制力はありませんが、高い確率で尊厳死が実現すると言えます。
3尊厳死宣言書の内容
①尊厳死を希望する意思
法律上は、尊厳死を認めると直接定めたものはありません。
だから、記載内容についてもルールがあるわけではありません。
遺言書と同様に、後日トラブルにならないようにするために作成しておくものです。
おおむね、次のような内容を書きます。
過剰な延命措置をしないで、自然な死を迎えることを希望するという内容です。
死が差し迫ったとき、苦痛を和らげて欲しいこと、安らかに最期を迎えることを希望することを表明します。
尊厳死宣言書の核心で、最も重要な点です。
しないで欲しい具体的な治療内容や治療を中止する条件も、書いておきます。
急に心肺停止状態になったとき、蘇生措置を希望するのか、口から食事がとれなくなったら、どうするのかなど具体的に記載します。
②尊厳死を望む理由
尊厳死を望む理由を書くと、尊厳死を希望することの説得力が増します。
例えば、親族が延命治療を受けたとき、本人にとっても家族にとっても医師にとっても苛酷と思えたからなどです。
③家族の同意
尊厳死を望むのであれば、このことを家族に伝え、家族に理解してもらう必要があります。
95%以上の医師が尊厳死宣言の提出があったら、本人の意思を尊重すると答えています。
事前に家族が何も聞かされていなかったら、気持ちが動揺して延命治療を望むでしょう。
本人が強く尊厳死を望んでも、家族が延命治療の継続を望んだら、医師は無視できません。
家族とのトラブルをおそれて、医療関係者は延命治療を続けるでしょう。
尊厳死宣言書に連名で署名してもらうことは有効です。
尊厳死宣言書作成に家族も同席し、家族の同意書と印鑑証明書を添付してもいいでしょう。
最終的に決めるのは、家族と医療関係者です。
④医師に対する免責
尊厳死の実現に尽力してくれた医師らに法的な責任を問われないようにする内容です。
刑事責任については、警察や検察関係者が判断することですが、最大の配慮を求める内容を書いておきましょう。
賠償責任も問わないことを明示します。
⑤尊厳死宣言書の効力
尊厳死宣言書は本人が元気なときに、作ったものであることを書きます。
本人自ら撤回しない限り有効であることを明らかにします。
5尊厳死宣言は遺言書に書いても意味がない
尊厳死宣言も、遺言書も、いわゆる終活で話題にのぼります。
尊厳死宣言は遺言書に書いておけばよいと考える方もいます。
尊厳死宣言書と遺言書は性質の違うものです。
遺言書に尊厳死宣言を書くことは、おすすめできません。
遺言書は被相続人が死亡した後、効力が発生します。
相続が発生した後、遺言書の内容を確認することになるでしょう。
自筆証書遺言であれば、相続発生後、家庭裁判所で開封してもらいます。
家族が遺言書の内容を知っていたとしても、通常は他の家族に内容を秘密にしておくでしょう。
遺言書を見て、尊厳死宣言がされていると気づいても、遅いのです。
延命治療をしないで欲しいという意思表示は、生きているうちに医師に伝わる必要があります。
遺言書の内容を医師ら医療関係者が確認するのも現実的ではありません。
遺言の内容は、法律関係のことだからです。
遺言書に書いて有効になることは、詳細に決められています。
遺言に書いて有効になることの中にも、尊厳死宣言はありません。
6尊厳死宣言を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策をする人はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
尊厳死宣言は人間としての尊厳を維持したいという希望を文書にしたものです。
元気だった時の姿を知っている家族は、ベッドに横たわるだけの姿を見ると動揺します。
回復の見込みのない状態だと分かっていても、大きな苦痛を伴うことを知っていても、どうするかを判断したくない気持ちになるでしょう。
何も判断したくない、判断を先延ばししたいという気持ちから、延命措置が続けられます。
延命措置が続けられれば、苦痛も続きます。
延命措置が続く間、本人も苦痛が続き、見ている家族も苦痛が続くのです。
家族は、後々になっても、本人を苦しめてしまったのではないかと後悔するのです。
尊厳死宣言は、自己決定権を尊重するものです。
自分がどのような治療や措置を受けたいのか、どのような治療や措置を受けたくないのか、どのような最期を迎えたいのか意思を示すものです。
家族は、本人の意思をかなえてあげることができると救われます。
自分自身のためにも、大切な家族のためにも、意思を示してあげましょう。
大切な家族に面倒をかけないために尊厳死宣言書を作成したい方は、すぐに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
家庭裁判所に収入印紙800円
1家庭裁判所の手数料は収入印紙で納入
①申立書に収入印紙800円貼付
家庭裁判所に申立てを提出する場合、手数料を納入します。
手数料は、現金で納入することはできません。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
収入印紙を貼り付けるのは、申立書の右上部です。
収入印紙貼り付け位置に、800円分の収入印紙を貼り付けます。
②額面800円の収入印紙はない
家庭裁判所に納入する手数料が800円であっても、額面800円の収入印紙は存在しません。
例えば、次のように複数の収入印紙を組み合わせます。
・額面400円の収入印紙を2枚
・額面600円の収入印紙1枚と額面200円の収入印紙1枚
・額面200円の収入印紙4枚
申立書の収入印紙貼り付け位置は、大きなスペースではありません。
たくさんの収入印紙を貼り付けるのは、難しいでしょう。
多くても4枚程度で準備するのが、おすすめです。
2収入印紙を購入できるところ
①郵便局の郵便窓口
郵便局の郵便窓口で、収入印紙を購入することができます。
大きな郵便局には、ゆうゆう窓口が設置されています。
ゆうゆう窓口も、収入印紙を取り扱っています。
ゆうゆう窓口であれば、24時間利用可能です。
好きなときにいつでも、収入印紙を購入することができます。
郵便局の郵便窓口では、クレジットカードや電子マネーを使うことができます。
クレジットカードで、収入印紙を購入することはできません。
②コンビニエンスストア
コンビニエンスストアは、いたるところにあり24時間営業しています。
昼間に時間が取れない人にとって、コンビニエンスストアで購入できるのは便利です。
コンビニエンスストアでは、収入印紙を取り扱っていないことがあります。
取り扱っていても、主に200円印紙のみの取り扱いです。
収入印紙を4枚貼り付けることになります。
手間がかかりますが、貼り付けてあれば差し支えありません。
コンビニエンスストアによっては、電子マネーで支払いをすることができます。
③法務局の印紙売りさばき窓口
法務局の印紙売りさばき窓口で収入印紙を購入することができます。
法務局の業務時間中のみ購入することができます。
④名古屋家庭裁判所では売っていない
家庭裁判所に申立てを提出する場合、窓口に持参することができます。
申立書を自分で作成した場合、窓口で確認してもらえると安心でしょう。
名古屋家庭裁判所に申立書を持参する場合、収入印紙は裁判所で販売していません。
名古屋家庭裁判所の窓口に持参する場合、あらかじめ収入印紙を準備しておく必要があります。
⑤専門家に依頼したら準備してもらえる
家庭裁判所に提出する書類は、自分で作成することが難しいかもしれません。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士や弁護士に依頼することができます。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合、収入印紙は専門家が準備してくれます。
3家庭裁判所に収入印紙を提出するときの注意点
①収入印紙に消印をしない
申立書を家庭裁判所に提出するときに、収入印紙800円を貼り付けます。
収入印紙800円は、申立ての手数料です。
手数料を受け取った裁判所が、収入印紙に消印を押します。
申立てをする人は、消印を押しません。
一般的に、領収書や契約書などに収入印紙を貼り付けます。
領収書や契約書などに収入印紙を貼り付けるのは、印紙税の課税文書だからです。
収入印紙を貼って消印をすることで、印紙税を納入します。
申立書は、印紙税の課税文書ではありません。
手数料の納入のために収入印紙800円を貼り付けています。
手数料の納入のためだから、申立てをする人は消印を押しません。
②登記嘱託用収入印紙は貼り付けない
家庭裁判所の手続では、手数料以外に収入印紙が必要になることがあります。
例えば、成年後見開始の申立てをする場合、手数料は800円です。
手数料以外に、収入印紙2600円分を提出します。
収入印紙2600円分は、登記嘱託用です。
成年後見制度を利用している場合、後見登記がされます。
後見開始の審判が確定した場合、裁判所書記官が後見登記を嘱託します。
収入印紙2600円分は、登記嘱託をするとき使う費用です。
成年後見開始の申立書に、貼り付けると裁判所の人が困ります。
登記嘱託用収入印紙は、小袋に入れて提出します。
4収入印紙800円が必要になる主な申立て
①相続放棄の申述
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の申述をする場合、手数料を納めます。
手数料は、800円です。
被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、相続人全員が相続放棄を望むでしょう。
相続放棄は、各相続人が自分で手続する必要があります。
相続放棄の手数料は、相続人1人あたり800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
②相続放棄の期間の伸長の申立て
相続放棄を希望する場合、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続が発生してから長期間経過してから、自分が相続人であることを知ることがあります。
自分が相続人であることを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
相続を単純承認すべきか相続放棄をすべきか判断する3か月の期間を熟慮期間と言います。
被相続人の財産状況が分からない場合、相続を単純承認すべきか相続放棄をすべきか判断できないことがあります。
例えば、借金を何度もしていて返済が終わっているのか返済中であるのか不明であるケースです。
債権者に問い合わせても、即答できないでしょう。
取引状況を即答できない債権者がたくさんいると、3か月以内に判断できません。
熟慮期間内に判断できない場合、相続人は相続放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。
相続放棄の期間の伸長の申立てが認められた場合、原則として、さらに3か月伸長されます。
相続放棄の期間の伸長の申立てをする場合、手数料を納めます。
手数料は、800円です。
相続放棄の期間の伸長の申立ては、各相続人が自分で手続する必要があります。
相続放棄の期間の伸長は、相続人ごとに判断されます。
相続放棄の期間の伸長の申立ての手数料は、相続人1人あたり800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
③相続財産清算人選任の申立て
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人全員が相続放棄をすることができます。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなります。
相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
被相続人が払うべきお金を払わないまま、死亡することがあります。
被相続人にプラスの財産がある場合、財産からお金を払ってもらいたいと望むでしょう。
相続財産清算人は、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
相続財産清算人は、プラスの財産からお金を払って清算をします。
家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらいます。
相続財産清算人選任の申立てをする場合、手数料を納めます。
手数料は、800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
④遺言書検認の申立て
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。
作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。
相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
封がされ得いる遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。
遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書検認の申立てをする場合、手数料を納めます。
手数料は、800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
⑤遺言執行者選任の申立て
自分が死亡した後に自分の財産をだれに引き継いでもらうか、遺言書で決めることができます。
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言書で指名しても、指名された人からご辞退されることがあります。
指名された人が先に死亡することがあります。
家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者選任の申立てをする場合、手数料を納めます。
手数料は、800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
5裁判所に提出する書類作成を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、家族は大きな悲しみに包まれます。
深い悲しみの中で、葬儀を執り行います。
ここから怒涛のような相続手続が始まります。
だれが相続人になるか家族にとっては当然のことと軽く考えがちです。
相続手続先の人に対して、相続人は客観的に証明する必要があります。
大した財産がないから、相続手続はカンタンに思えるかもしれません。
相続手続は、普段聞き慣れない法律用語でいっぱいです。
相続手続先は、相続人のトラブルに巻き込まれないために慎重に判断します。
想像以上に神経を使って、クタクタになります。
家庭裁判所の申立てが必要な手続をなると、さらに難易度は上がります。
司法書士は、相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
スムーズに相続手続を進めたい方は、司法書士に相談することをおすすめします。
失踪宣告で生命保険の請求
1失踪宣告で死亡と見なされる
①普通失踪は生死不明7年満了で死亡
行方不明になってから長期間経過している場合、死亡している可能性が高いことがあります。
失踪宣告は、死亡した可能性が高い行方不明者を法律上死亡した取り扱いにする手続です。
失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
普通失踪は、行方不明になってから7年経過後に失踪宣告の申立てをすることができます。
普通失踪は、生死不明7年満了で死亡と見なされます。
②危難が去ってから1年で特別(危難)失踪
行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。
大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。
特別失踪(危難失踪)とは、次の事情がある人が対象です。
(1)戦地に行った者
(2)沈没した船舶に乗っていた者
(3)その他死亡の原因となる災難に遭遇した者
死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。
特別(危難) 失踪では、失踪期間が1年です。
特別(危難) 失踪は、危難が去ってから1年経過後に失踪宣告の申立てをすることができます。
特別失踪(危難失踪)では、危難が去ったときに死亡と見なされます。
③失踪届で戸籍に反映
失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。
失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。
失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。
死亡したときに提出する死亡届とは別の書類です。
失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。
失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。
失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。
④行方不明のまま認定死亡で死亡届
人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。
海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。
遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。
海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。
死亡の報告書を添えて、市区町村役場に死亡届を提出することができます。
死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。
行政機関が市町村長に対して死亡の報告をしたら、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。
事実上、死亡の推定が認められます。
⑤単なる行方不明は生存扱い
行方不明の人は、法律上生きている人です。
長期間行方不明になっていても、法律上生きている人のままです。
生きているままだから、生命保険の死亡保険金は支払われません。
単なる行方不明の人は、生命保険の死亡保険金は支払われません。
2失踪宣告で生命保険の請求
①戸籍に反映したら生命保険の請求
失踪宣告の審判が確定した場合、市区町村役場に失踪届を提出します。
認定死亡の場合、市区町村役場に死亡届を提出します。
失踪届や死亡届が受理された場合、戸籍に記載されます。
死亡したことが確認できなくても、死亡と取り扱われます。
失踪宣告や死亡の記載がある戸籍謄本を提出して、生命保険を請求します。
生命保険の死亡保険金は、死亡によって給付されます。
失踪宣告や認定死亡は、死亡と同様の効果があります。
生命保険の死亡保険金は、失踪宣告や認定死亡であっても給付されます。
被保険者の死亡が戸籍に反映したら、生命保険を請求することができます。
②団体信用生命保険で住宅ローン完済
団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済に特化した生命保険です。
住宅ローンの債務者が死亡したとき、保険金で住宅ローンが完済になります。
民間の金融機関で住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているのがほとんどです。
住宅ローンの債務者が失踪宣告を受けた場合、保険金で住宅ローンが完済になります。
失踪宣告は、死亡と見なす制度だからです。
団体信用生命保険で住宅ローンは完済になります。
③契約が終了していると保険金が支払われない
生命保険の死亡保険金が給付されるのは、契約が継続している場合のみです。
被保険者が死亡と見なされる前に契約が終了している場合、死亡保険金は給付されません。
保険料の納入ができなくても、直ちに契約が終了するわけではありません。
契約内容によって異なるものの、1か月の猶予期間があります。
生命保険の多くは、解約した場合に解約返戻金が支払われるでしょう。
解約返戻金がある保険で猶予期間内に保険料が納入されなかった場合、保険商品によっては自動振替貸付がされます。
自動振替貸付とは、解約返戻金の範囲で保険料を立て替えて契約を維持する制度です。
普通失踪であれば、失踪期間は7年です。
特別(危難) 失踪であれば、失踪期間は1年です。
自動振替貸付を利用できても、デメリットが大きいでしょう。
保険契約を継続させるため、保険料を納入する必要があります。
④普通失踪は災害特約の対象外
普通失踪は、生死不明7年満了で死亡と見なされます。
生死不明の理由は、問われません。
生命保険商品によっては、災害特約がついていることがあります。
災害特約とは、災害で死亡した場合に保険金を増額してもらうことができる特約です。
普通失踪では、災害による死亡とは認められません。
普通失踪は、災害特約の対象外です。
⑤生きていたら保険金は返還
失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。
失踪宣告がされたけど、実は本人は新天地で元気に生きていたということがあります。
失踪宣告を受けた人が生きていた場合、失踪宣告は取り消されます。
失踪宣告は取り消された場合、受け取った生命保険金は返還しなければなりません。
返す財産は、現に利益を受けている限度においてのみとされています。
手許に現金が残っているのなら、受け取った現金をそのまま返すことができます。
不動産などを購入したのであれば、不動産に形を変えて利益を保有しています。
生活費などで使ったのであれば、その分の預貯金などが減らさずに済んでいるでしょう。
現に利益を受けている限度において、生命保険の保険金を返還しなければなりません。
3生命保険を解約できるのは契約者だけ
①行方不明者が契約していると家族は解約できない
普通失踪であれば、失踪期間は7年です。
特別(危難) 失踪であれば、失踪期間は1年です。
失踪期間経過後に、失踪宣告の申立てができます。
失踪期間経過後に失踪宣告の申立てをしても、失踪宣告がされるとは限りません。
裁判所の調査で、生存が確認されることがあるからです。
失踪宣告がされるまで、保険契約を維持する必要があります。
不確実な死亡保険金をあてにするより、解約返戻金を受け取りたいと考えるかもしれません。
生命保険契約を解約することができるのは、契約者のみです。
契約者以外の人が手続をする場合、契約者から委任状が必要です。
行方不明の人が契約者の場合、契約を解約することはできません。
契約者を差し置いて家族が勝手に解約することはできません。
②不在者財産管理人は解約できる
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を保存管理する人です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
生命保険契約は、行方不明の人の財産です。
生命保険の解約は、行方不明の人の財産の処分と言えます。
本来、不在者財産管理人は、財産の保存と管理しかできません。
行方不明の人の生命保険を解約するためには、家庭裁判所に権限外行為の許可が必要です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て保険契約を解約することができます。
4生命保険契約は調べることができる
①口座の引落記録等で判明
生命保険に入っているはずだが、保険証書がどうしても見つからないこともあるでしょう。
保険証書が見つからなくても、保険契約が無効になることはありません。
保険契約は、保険証書がなくても有効です。
契約の条件を満たせば、保険金は支払われます。
保険証書が見つからなくても、保険会社からの通知が見つかるでしょう。
銀行口座からの引落記録などで、保険会社が判明することも多いものです。
保険会社を探して、相談しましょう。
通常、保険証書には保険の種類や保険の番号が書いてあります。
保険金の支払請求をするとき、保険の種類や番号があると、比較的スムーズに手続できます。
保険の種類や番号が分からない場合、通常より手続に時間がかかります。
②生命保険契約照会制度
保険証書が見つからない場合、どこの保険会社に入っているのかすら分からないこともあるでしょう。
生命保険契約があるかどうか分からない場合、一般社団法人生命保険協会に対して、調査をしてもらうことができます。
調査は、インターネットや郵便で依頼することができます。
調査をしてもらう対象は、一般社団法人生命保険協会に加入している保険会社のみです。
本人が死亡した場合、調査を依頼することができる人は、次のとおりです。
(1)法定相続人
(2)遺言執行者
本人が死亡した場合に必要な書類は、次のとおりです。
(1)調査を依頼する人の本人確認書類
(2)本人と依頼する人の身分関係が分かる戸籍謄本
(3)死亡診断書
調査を依頼するためには、所定の手数料がかかります。
水害や大震災のような災害にあった場合、保険証書が流失したり、焼失することもあります。
自然災害による被害で保険証書を紛失しても、保険契約が無効になることはありません。
多くの方が保険証書を紛失する事態になるので、照会センターが設置されて、特別体制がとられます。
5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
行方不明の相続人や長期間行方不明で死亡の可能性の高い相続人がいる例は、少なくありません。
相続人が行方不明の場合、相続手続を進められなくなります。
相続手続を進めたいのに、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立てなどは、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になるでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
« Older Entries




